| 〜少年時代、その他の音楽の想い出〜 1950年代は、アメリカ音楽だけでなく、中南米音楽も、一斉に日本に入ってきました。 アメリカ経由だったのだとは思いますが、ともかく、様々な外国文化の流入は、その後の日本を、 私を、大きく変えることになりました。 〜ラジオから流れてきた、岡晴夫:「憧れのハワイ航路」 藤山一郎:「青い山脈」 淡谷のり子:「別れのブルース」 奈良光枝:「赤い靴のタンゴ」 岡本敦郎:「白い花の咲く頃」 津村健:「上海帰りのリル」 伊藤久男:「あざみの歌」などの歌を愛唱し、始まったばかりの 「紅白歌合戦」で、赤組キャプテン:宮田輝、白組キャプテン:高橋圭三の戦いに、 真剣に耳をそばだて、ドラマ:「君の名は」 をいらいらしながら聞いていた時代でしたから〜、 小学校高学年の時に観た、「グレンミラー物語」 で受けたカルチャー・ショックは、大変なものでした。 外国映画・音楽好きのスタートとなった、記念すべき映画です。 小さい頃、よく、父に連れられて上京するチャンスがありましたが、父は浅草が好きなようでした。 私は銀座が夢のような街だったことと、夜の銀座の露天で、光るヨーヨーを買ってもらったことを 今でも鮮明に憶えています。 列車の窓から浴びた、ススの匂い。臼井峠では、トンネルに入る前に、窓を閉めさせられたこと。 半日以上かけて、上野駅に着いた時の、期待へのトキメキ…。様々な情景が今でも浮かんできます。  ■ 「Memory : Tokyo」 ■ 「Memory : Tokyo」 何とも垢抜けない、当時の大人の歌のほとんどを、今でも歌えてしまうのが、チョッと切ないのですが、 そもそも、子供が夢中になれる “気のきいた音楽” というものが無かった時代でしたから、 仕方ないのかもしれません。 一曲のライフ・サイクルが長かった事も驚きですが、少年時代の記憶が、成人してからのものとは 全く違った回路で、いつまでも鮮明に保存されている事が、とても不思議です。 朝鮮戦争が始まり、ロス・アンジェルスの都市化と共に、ウエスト・コーストに、ジャズ・メンが移っていった 同じ時期に、遠く日本では、鼻水をたらしながら、「憧れのハワイ航路」 を自分が歌っていたんだな〜。 などと、歴史に重ねてみて、妙な感慨が湧いてきます。 まだ、民間のラジオ放送など無かった時代の事です。 プレスリーを知り、「エデンの東」 「慕情」 「黄金の腕」 「上流社会」 を観てしまった私は、 すっかり外国モノに、心を奪われてしまいました。 石原慎太郎の 「太陽の季節」 「狂った果実」 や、その後、日本人アーティストの出現でブレイクした、 ウエスタン、カリプソ、ロカビリーなどのブームは、全く興味の対象外となってしまったのです。 映画も、日本の青春ものをやっていた 日活映画 だけほとんど観た記憶がありません。 同世代の人たちが、今でも石原裕次郎を好きなのに、私は全くゴメンナサイです。 その代わり東映の時代劇などはよく観ましたから、中村錦之助や東千代の介は今でも懐かしい俳優です。 50年代の時代劇は、西部劇と一緒で時代を超えて魅力があります。 偏った嗜好は、成人してから、日本の現代文学をほとんど読まなくなるという弊害をもたらす事になります。  ■ 「Memory : Inaka」 中学時代 「真田十勇士」 「後藤又兵衛」 「加藤清正」 など戦国武将の単行本が愛読書だったことは、 真田家ゆかりの土地柄だった事と、無縁ではありません。 (なんと言っても、高等学校のマークが“六連銭”でしたから…。) つまらない事ですが、子供の頃は、甲賀忍者の猿飛佐助のほうが、 伊賀忍者の霧隠才蔵よりメジャーで強いと思って、誰もが猿飛役をやりたがったものです。 その後映画で観る限り、伊賀忍者に光が当たっているようで、どうも納得できないものがあります。 〜東映時代劇の全盛期についても、かなりうるさいのですが、その話は、別な折にします。 そして、高校時代は、日本の経済復興と共に、以前にも増して、世界の音楽が、私を夢中にさせていきます。 いつ頃かは忘れましたが、大好きなラジオ番組で、「ポポン・ミュージック・レター」というのがありました。 毎週日曜の午後あたり、2時間番組だったかもしれません。なにしろ、ゆっくりくつろいで楽しめましたから〜。 当時のリクエストは、大抵が映画音楽という時代で、「シェーン」「慕情」「ピクニック」「愛情物語」 「ジャイアント」「バラの刺青」…そんな曲が毎週流れていたものでした。 でも、忘れられないのは、DJの2人:志摩由起夫氏と浦川麗子さん…、大のお気に入りでした。 志摩由起夫氏は、夜の番組で中学時代に直接リクエスト曲のやり取りをして、すっかり、 こちらはお馴染みでしたが、浦川麗子さん…、きれいな声、品のあるおしゃべり〜、 後年、女の子が生まれたとき、真剣に“麗子”とつけようと思ったくらい、いつまでも忘れられない女性でした。 (どんな人か解らずじまいでしたが、これがラジオに秘められた不思議な魅力なんだと思っています。) ♪ タンゴは、ジョージア・ギブス:「キス・オブ・ファイアー=エル・チョクロ」 フランキー・レイン:「ジェラシー」 など、アメリカの歌手が歌って、ヒット・パレードを賑わしていました。 サッチモは、映画に音楽に大活躍で、「キス・オブ・ファイアー」 がラテン物では、印象に残っています。 田舎でも、「ミロンガ」という名の喫茶店まであったほどでしたから、タンゴは大変な人気でした。 様々なジャンルの、最新の音楽は、当時、喫茶店で知ることが多かったように思います。 ■ 「Nat King Cole」 チョッと話がそれますが…。 比較的、開放的な家庭に育ったおかげで、高校時代には 「モナリザ」 という、なじみの喫茶店があったくらい、のびのび過ごし、 喫茶店好きはその頃スタートしました。 店名の由来が、ダ・ヴィンチなのか、キング・コールのヒット曲なのかは今となっては解りませんが、 心ときめく場所でもありました.。 コールの「キサス・キサス・キサス」 「テキエロ・デ・ヒステ」 を聴くたびに、 あの秘密の場所や可愛いお嬢さん…名前は、コール大好きのタアちゃんだったか、 エミちゃんだったか…若かりし頃のほのかな想いが蘇ります。 これらの曲が丁度大ヒットしている頃で、あの店へ行くといつも流れていましたから…。 コールについてはいずれ別なところで取り上げたいと思っています。 高校時代から、縁あって、ちょくちょく上京し、渋谷は、その頃からのお気に入りの場所でした。 田園・白馬車・マリンバ・牡丹など、大きな喫茶店が、最近までありましたが、 「ニュー・パウリスタ」 という名の喫茶店が好きで、よく通いました。狭い入り口を入ると、 何層もの小さいフロアに分かれていて、薄暗い照明が、穴場的な雰囲気をかもしだしていました。 田舎の「モナリザ」も同じような作りで、雰囲気も似ていて、当然音楽もゴキゲンでした。 その後、渋谷のその場所は、そば屋になり、また最近取り壊されてしまったようで、 当時の面影がほとんどなくなってしまいました。 まあ、恋文横丁があった時代の話ですから、相当古いといえます。  ■ 「Les Deux Magots : Paris」 たいていの、ジャズ・ファンが経験したような、ジャズ喫茶通いを、 私は大学時代に経験していません。体育会という硬派の集団の中で、 一日中、体を動かしていましたから、カントリー・ソングのような、 単純で、解りやすい音楽が合っていたのかもしれません。 でも、渋谷の同伴喫茶について、かなり詳しく憶えているのはなぜだろう、 などと一応自問はしています。 現在でも、ライブ・ハウスで、静かにジャズを鑑賞するという習慣も無く、友人と、ジャズ談義などで 熱くなったこともありません。(以前住んでいた家のすぐそばに、ブルー・ノートが出来て、 毎日、その前を通りながら、ついに一度も入ったことがありませんでした。) 強いて、音楽の話で盛り上がったのは、カントリー・ミュージックぐらいです。 それも、歌い方や、歌の内容が主な話題でした。一時、友人達と、グループを組んで、 素人芸を披露したりしていましたから…。 生来、音楽が好きで、その時々、気の向くままに、いろいろな音楽に接してきた結果、 ジャズにも、かなり深入りしていたというのが実情です。 ジャズに関しては、1920年代のアーリー・ジャズから、1960年初期までのハード・バップぐらいが、 私の興味の範囲で、それも、私なりの感覚で、それ以降のジャズは、聴いていて面白くないから…、 という単純な理由です。 ライブ・ハウスに、行かない理由もそんなところです。行けば、きっと新しい発見もあって楽しいのでしょうが…。 断片的に、現在でも、気に入ったアーティストはいますが、ジャズも含めて、理屈ぬきで、のめり込めるような、 魅力ある音楽は見当たりません。 これを称して、年をとったと言うのかもしれませんが、それだけではないとも思っています。  ■ 「Coffee Break」 特別、コーヒーにうるさいわけではないのですが、 10年間ばかり、デザインの仕事を生業としていたことがあり、 喫茶店の設計も手がけた関係で、親しみもあり、どこかへ出かけても、 先ず、喫茶店を探すという癖がついてしまいました。 今では、タバコが吸えて、音楽が流れていて、カレーの匂いのしない喫茶店で、 ゆっくり過ごすことが、私のライフ・スタイルとして、定着しています。 現在、行きつけの喫茶店では、モダン・ジャズを耳にする事が多いのですが 、特に聴き入るということはありません。昔のポップ、カントリー、スィング、タンゴ、ハワイアン、ブルース、 ディキシーなど、ジャンルを問わず、音楽が流れていれば、気分が良いという程度です。 気分の良い店だけに、長く続けてもらいたいものです。 最近の喫茶店に対しては、かなり不満があります。 スタバやドトールのような安直なコーヒー・ショップばかりが増えてしまい、 ゆったり落ち着ける喫茶店がどんどん減っている事です。 少なくとも私にとっての喫茶店は、ゆっくり談笑したり、打ち合わせしたり、タバコをくゆらす場所なのです。 もちろんチョイと苦味のある、マンデリンにも魅力がありますが、先ず、くつろげる場所であって欲しいものです。 食事代と間違えるような、高価なコーヒー代を払って、ホテルのラウンジを常用するなどは、 コーヒー党にとっては邪道なのです。日本には、欧米とは違った喫茶店文化というものがあったはずです。 私個人は、あまり店の人と会話をしないようにしているのですが、それでも、もっとアット・ホームな雰囲気が、 喫茶店にはあったものです。いずれ、現在の反動として違った業態も出てくることでしょうが、坪効率を考えると、 今のところ、単価と回転数を操作するしかないのです。(利便性、効率性優先時代だからこそ、 オアシスであって欲しいものです。) そんなこんなで、少年時代は、我が家で、喫茶店で、映画を観て、結果的には、 沢山の音楽に触れる機会をもてました。  ■ 「Argentine Tango」 ♪♪ 「ラ・クンパルシータ」 「泣き虫」 「さらば草原よ」 「エル・チョクロ」 「バンドネオンの嘆き」 「淡き光に」 フランシスコ・カナロや、ファン・ダリエンソの歯切れの良いバンドネオンの名演奏、 名曲の数々が忘れられず、レコード、テープ、CDと、時代に応じて楽しんでいます。 ♪ 「月下の蘭」 「碧空」 「オレ・グァッパ」 「ヴィオレッタに捧げし歌」 「カミニート」 「ジェラシー」 …。子供の頃 「碧空」 を聴いてから、 アルフレッド・ハウゼ楽団も大好きになりました。 コンチネンタル・タンゴ独特の上品なアンサンブルは、今聴いても新鮮です。 ♪ 「真珠採り」 リカルド・サントス楽団で、ヒット・チャートを飾った懐かしい曲です。 …どんなジャンルの音楽でも、きちっとしたリズムを好む傾向があるのは、タンゴ好きが原因かもしれません。 当時の懐かしい曲を聴くだけで、深く追求した事は無く、タンゴの世界も追いかけると面白いだろうなあ、 といつも思っているのですが、なかなか手が回りません。 ♪ 「バナナボート・ソング」 で、ハリー・ヴェラフォンテが有名になり、ジャマイカ音楽:カリプソもヒットしました。 日本でも、浜村美智子が歌ってかなりヒットし、バナナ娘とか何とか言われていました。 ハリー・ヴェラフォンテは、歌に、映画に大活躍でしたが、私は、彼の声・顔とも嫌いでした。 ♪ カリプソ風のジャズと言えば、有名なソニー・ロリンズの名作:「セント・トーマス」 があります。 陽気なカリプソを、モダンジャズに取り入れた、彼の非凡な才能を感じます。 ♪ キューバ〜メキシコへ渡ったという、マンボの王様:ペレス・プラドが来日し、 マンボの大ブームをおこしたものです。 今でも、マンボを一番の想い出にしている人が多いと思いますが、年寄りから若い者まで夢中になれた、 独特のテンポの良さは、今ブレイクしてもチッともおかしくない、素晴らしい音楽だと思います。 「チェリーピンク・マンボ=セレソ・ローサ」 「パトリシア」 「ハバナ午前3時」 「マンボ・NO5」 「ある恋の物語」 「マンボ・NO8」 レコードで聴いていた頃は気づかなかったのですが、 CDで、あらためて聴いてみると、かなり、ジャズっぽい雰囲気があります。 ♪ ペレス・プラドの「エル・マンボ」 忘れる事の出来ない、S盤アワーのテーマ曲です。 せきたてるような躍動感に溢れた、この曲は、帆足まり子さんという、元気なお姉さんの声とともに、 今も鮮明に憶えています。 エンディング・テーマは、グレン・ミラーを彷彿とさせる、ラルフ・フラナガンの「Singing Wind」 で、 心地よいナンバーでした。 小島正雄、モンティ・本多、志摩由起夫、ロイ・ジェイムス、夜のラジオが楽しみだった頃、 ディスク・ジョッキーの名調子も懐かしく想いだされます。 同じ時期、 L盤アワーも、放送されて、私の外国音楽の大切な情報ソースでしたが、 こちらのディスク・ジョッキーの名前や、テーマ・ミュージックを想いだせません。 そして、これらの番組が、いつ消えていったのかも憶えていません。  ■ 「Mambo」 彼の音楽を使用した映画 「海底の黄金」: 口ひげがトレードマークの、 ギルバート・ローランド。笑った時の、歯が印象的な、リチャード・イーガン。 男勝りの、ジェーン・ラッセルが絡む、カッコいい活劇物。 その、テーマ・ミュージックが、ペレス・プラドの「セレソ・ローサ」 でした。 この曲の大ヒットが、ブームに拍車をかけました。 ☆ 「河の女」 という映画で、主演のソフィア・ローレンが歌った 「マンボ・バカン」 は、 彼女の陽気な雰囲気、豊満な容姿とともに、忘れられない歌で、随分ヒットしたものです。 ♪ ビリー・ヴォーン楽団は、ダンス音楽にロックを取り入れて、モダンなダンス音楽を創り上げ、 サックスの心地よいサウンドは大人気でした。「浪路はるかに」 の大ヒットで、ロッカ・フラという言葉も出来たほどでした。 この曲は、高校時代のものですが、その後上京してから、ラジオ関東の 「ポート・ジョッキー」 という音楽番組の テーマ・ミュージックで再会しました。 日ノ出町に住んでいた先輩のお姉さんが、ラジオ関東に勤めていたということもあって、夜は必ず聴いていましたが、 ボーッという霧笛も幻想的で、シャレた番組だった事を想い出します。 「魅惑のトロピカルランド」 というレコードは、ビリー・ヴォーンの、ラテン音楽を収めたアルバムで、 さわやかで、心地よいサウンドは、永遠の名盤と言えます。いずれ、CDで、買いなおそうと思っています。 ♪ 「チャチャチャは素晴らしい」 「メロンの心」 など、チャチャチャも、キューバ音楽だとおもいますが、 同じようにペレス・プラドで聴いた覚えがあり、森山加代子などの歌で大ブレークしたものでした。  ■ 「Trio Los Panchos」 ♪ 高校生の時、メキシコから、トリオ・ロス・パンチョスが来日。 ライブを見に行きました。 「ソラメンテ・ウナ・ベス」 「アモール」 「シェリトリンド」 「ベサメ・ムーチョ」 甘い、メロディアスな数々の歌に 酔いしれたものでした。その後、彼らよりより実力のあるトリオとして、 ロストレス・ディアマンティスがいると知らされたのですが、 確かにうまさと甘さを感じましたが、直に見た方の印象が強いのは仕方ありません。 社会人になってから、メキシコのレストランで〜、弾き語りの二人から、リクエスト曲を求められ、 「ラクカラチャ」 を思いついたのですが、確か意味がアブラムシだった事を思い出し、 「ソラメンテ・ウナ・ベス」 「バイア・コンディオス」 を歌ってもらった事や、彼らがトリオ・ロス・パンチョスほど 上手くなく、それも仕方ないかと納得して聴いていたことを思い出します。 メキシコへ入る前、サン・アントニオで、アラモの砦に寄ったのですが、西部開拓時代の、 こんなところに生まれなくて良かったなあと思うほど、ちっぽけで頼りない砦跡でした。 デビー・クロケットもジム・ボウイも私には、ジョン・ウェインとリチャード・ウィドマーク、 チョッと古くはスターリング・ヘイドンのスクリーン・イメージしかありませんでしたから、本物の遺品に接して、 感慨深く、とてもブラザーズ・フォーの 「The Green Leaves Of Summer」 や、「San Antonio Rose」 をハンク・トンプソンばりに、口ずさむほどの雰囲気ではありませんでした。  ■ 「The Alamo」 ※ アブラムシで想いだすのは、モデル・ガンのことです。 小さい時から西部劇ファンでしたから、 愛用のコルト・ピースメーカーを、ホルスターから 0.何秒で抜き打ちできるかと日夜練習に励んでいたものです。 少なくともゲイリー・クーパーのレベルにはなっていたはずです。 (彼は、「真昼の決闘」出演のために、監督からの指示で、0.3秒で抜けるまで練習したと、雑誌で読んだ憶えがあります。) 社会人になってから、友人の影響でガス・ガン(弾はBB弾) を集めるようになり、これは実生活に役立ちました。 以前住んでいた場所では時々ゴキブリが出現し、これを仕留めるのが無上の喜びでした。 射程距離も長く、命中率もすこぶる高い優れもので、姿を見て、まず逃がした事がありませんでした。 家族からも信頼が厚く、「パパ、出たよ!」 の声に、おもむろにコルト・コンバット・コマンダーを取り出し (これが一番命中率が高かった) 3〜4メートルの位置から、じっくり狙ってほとんど一発で仕留めたものです。 スケールがやや小ぶりですが、一家の主としての威厳が保てたと思っています。 〜現在高層ビルに越してしまい、標的の無い淋しい生活を強いられています。  ■ 「Colt : Model Gun」 家族でハワイ旅行した際も、皆をワイキキの浜辺へ追いやって、 一人黙々とガン・ショップで、実射の喜びに浸っていたものです。 だからといって本物に憧れるなどという事は当然ありませんから、 かなり幼稚な感じがしないでもないのですが、 友達も相変わらずらしいので、ここは男のロマンということで、自分を納得させるようにしています。 ♪ ハワイアンは、演奏しながら歌える歌謡曲、といったイメージが、昔から強くありました。 出会いが、灰田勝彦、バッキー・白片、大橋節夫、エセル・中田など、 日本人のミュージシャンだった事が大きな原因だと思います。 「小さな竹の橋で」 「赤いレイ」 「南国の夜」 「俺はお前に弱いんだ」 簡単なコードを憶えるだけで、 ウクレレ片手に歌えるお手軽さは、私にとっては、ギター入門編といった感じでした。 「アロハ・オエ」 「タ・フ・ワ・フ・ワイ」 「カイマナ・ヒラ」 「ダヒル・サヨ」 などもかなり身近に感じる歌で、 せいぜいプレスリーの映画で歌われた 「ブルー・ハワイ」 「ハワイアン・ウエディング・ソング」 などで ハワイのイメージが湧いてきた、といった具合でした。 「スィート・レイラニ」 「マナクーラの月」 等を美しいオーケストラで聴いた憶えがあるのですが、 そのLPも今は持っていませんから、私のハワイアンへの思い入れは、他のジャンルより少なかった事は確かです。  ■ 「Hawaii」 学生時代と違って、今では、かなり魅力的な音楽 というイメージを持っています。ビリー・ヴォーンの 「パーリー・シェル」 等がきっかけかもしれません。 また、ハワイへいって、本物に触れたからかもしれません。 時々聴くハワイアン・ミュージックに、懐かしさと安らぎを感じていますが、 強いてこれから掘り下げよう、と思う気持ちはあまりないようです。 ♪ ハワイアンはヒーリング・ミュージックとしても魅力がありますが、 「愛情物語/トゥ−ラブ・アゲイン」:カーメン・カバレロ 「昼下がりの情事/魅惑のワルツ」:パーシー・フェイス 「ティファニーで朝食を/ムーン・リバー」:ヘンリー・マンシーニ 「八十日間世界一周/アラウンド・ザ・ワールド」: ビクター・ヤング…、などが現代でも、イージー・リスニング・ミュージックとして、愛されているようです。 映画音楽のインストは、シーンは目に浮かんでも、音楽としてはパンチに欠けていて、特にワルツものは、 あまり好みではないのですが、それだけに飽きられることがなかったのかもしれません。 ポール・モーリアやニニ・ロッソなどで、たまに聴く、ヨーロッパ映画音楽などは、 昔のイメージが強く残っていて、あまり好きではありません。  ■ 「Les Paul & Mary Ford」 ♪ 「バイア・コンディオス」 は、レス・ポールとメリー・フォードの 多重録音が魅力的で、随分ヒットしました。 おしどりコンビとして有名だった二人は、その他にも 「アイム・ア・フール・トゥ・ケア」 「スモーク・リングス」「バイ・バイ・ブルース」 等、 くつろぎ感一杯のナンバーや、私のバンジョー購入のきっかけになった、 「世界は日の出を待っている」 等など、沢山のヒット・ソングを残してくれました。 もともとジャズ・ギタリストだったらしいのですが、私にとっては、ポピュラー・ミュージックだけで十分です。 ♪ ナット・キング・コールも、「カチート」 「テキエロ・デヒステ」 「キサス・キサス・キサス」 などを歌って大ヒットしました。原語で歌う彼の歌が素晴らしかっただけに、 以前ピアニストだったと後から知って驚きました。 しかもピアニストとしても一流で、私好みということもあって、彼は、私の生涯のアイドルということになりました。 ♪ 「デリカード」 「アンナ」:バイオンというこれらの、ブラジル音楽は、どちらもイタリア映画で知ったのだと 思いますが、これも心地良い音楽でした。あれ以来、このリズムに出会っていません。 「黒いオルフェ」というフランス映画。テーマ曲や、サンバなど、随分流行りましたが、 私には、暗かった印象しか残っていません。 丁度、大学にはいった頃、キューバが共産国になり、アメリカと国交断絶をし、 キューバ音楽の変わりにブラジル音楽が盛んになり、日本にも入ってきたように記憶しています。  ■ 「Bossa Nova」 ♪ジャズサンバという名で、モダンジャズ・プレーヤーの、 スタン・ゲッツが、アントニオ・カルロス・ジョビンや、 ジョアン・ジルベルトなどと、ボサノバを演奏し :「イパネマの娘」 「ワンノート・サンバ」 「おいしい水」など、ボサノバ・ブームがくるのですが、 それらは大学時代以降ということで、今後のページにします。 田舎での少年〜高校生時代。大学という名の体育会生活。卒業の頃に味わった、様々な悲しい出来事、 そして別れ。社会人としてのその後〜。誰でも歩んでくる人生に、私の場合、いつも音楽が身近にありました。 決して失う事の無い、想い出と共にある音楽が、今の、私の大切な財産になっています。 ……… ※ テレビから、「魅惑の宵」 が流れています。「昼下がりの情事」 を放映しています。 ゲーリー・クーパーとオードリー・ヘップバーン主演:1957年。と新聞にあります。 まさにこの頃が、私にとっての懐かしいといえる時代です。 映画の内容は大したことがなかったけれど、音楽だけは今も新鮮さを失っていません。 「エデンの東」 のテーマ曲も、長い間、ヒット・チャートのトップにランクされていた事を想いだします。 ヴィクター・ヤングの名曲ですが、私は、どちらかと言うと、映画音楽のインスト物を、特別好きではありません。 でも、音楽を聴くと、やっぱり昔がよみがえってきます。  ■ 「アパートの鍵貸します」: 1960 Shirley Maclaine & Jack Lemmon これを書いて2〜3日後、ビリー・ワイルダーが、亡くなったと報じられました。 彼は、沢山の様々なジャンルの映画を残しましたが、 「第十七捕虜収容所」 は、忘れられない映画です。 ウイリアム・ホールデンが、珍しくシリアスな役柄を好演していました。 独創的なスパイ映画で、随分ハラハラしたものです。 親しみやすいテーマ・ミュージックは、今でも時々口ずさむことがあります。 彼の最高傑作は、ジャック・レモンとシャーリー・マクレーンの 「アパートの鍵貸します」 でしょう。 シャーリー・マクレーンは好きな女優で、見事な肢体とチャーミングな顔だち、素直な演技は、大のお気に入りです。 ジャック・レモンが、トニー・カーティス、マリリン・モンローと共演した 「お熱いのがお好き」 はシャレた映画でした。 禁酒法下のシカゴ・ギャングとジャズという設定の良さもさることながら、全編、くすぐったい感じのする面白さでした。 オカマ役のジャック・レモンが、彼を好きな老人に、「私、実は男なの」 と打ち明けても、 「人間一つや二つ、欠点はあるものだ」と気の効いたセリフで終わるこの映画は、全編、ユーモアにあふれていました。 いずれ、エディ・コンドンのところで、この話題に触れたいと思います。  ■ 「七年目の浮気」: 1955 Marilyn Monroe 「七年目の浮気」 有名な、スカートのめくれるシーンが、 かなり話題になったものです。 マリリン・モンローは、特別好きだったわけではありませんが、 愛らしい役が多く、言われるような、 グラマー女優の印象を、あまり感じていません。 「バス・ストップ」 「帰らざる河」 での演技でも、女性らしい清純な感じでした。 「ナイアガラ」 では珍しく悪女を演じていましたが。 「七年目の浮気」とよく似ていて、私にとっては、もっと忘れられない映画として、 「女はそれをがまんできない」 があります。当時流行の音楽が楽しめる喜劇映画ですが、 男優は、トム・イーウェルで、女優はモンローどころではない、超ボイン女優のジェーン・マンスフィールドでした。 プラターズや、ファッツ・ドミノ他何人かのロックンロール歌手、そしてジュリー・ロンド本人が出演していたのです。 彼女の印象ばかりが強烈に残っていますが、意外と目鼻立ちにくせのある歌手だなあ、と思ったものです。 詳しいストーリーは忘れましたが、彼女や、プラターズ、ファッツ・ドミノの歌は、40年以上経った今でも、 当時と変わらない新鮮な感動を与えてくれます。 ジュリー・ロンドンは、その後、「西部の人」 であのゲーリー・クーパーと西部劇映画で共演しているのです。 さすがに、ジェーン・ラッセルやモーリン・オハラなどには及ばなかったものの、それなりの存在感はありました。  ■ 「熱砂の舞」 : 1956 Anita Ekberg ついでに、50年代のハリウッド映画は、 かなりのグラマー女優が、スクリーンで活躍しました。 モンロー、マンスフィールド、アニタ・エグバーグ、ダイアナ・ドース、 シルバーナ・マンガーノ、ソフィア・ローレン、 ジーナ・ロロブリジーダなどなど沢山いて、不思議と彼女達は、 愛らしい役柄が多かったように思います。 個人的には、もうチョッと知性的な感じの女優が好きでしたが、彼女達が、50年代のスクリーンを、 一段と華やかにしたことは間違いありません。 確か、ジェーン・マンスフィールドだったと思いますが、自動車事故での、悲惨な写真を見た記憶があります。 当時から、外国俳優のゴシップなどが、日本のメディアに盛んにとりあげられていました。 おかげで結構、情報通だった覚えがあります。  ■ 「Charles Chaplin & Virginia Cherrill」 チョッと異色ですが、私にとって、チャールズ・チャップリンは、 身近で、忘れられないアーティストです。 「街の灯」 「モダン・タイムス」 「独裁者」 「ライム・ライト」 などの作品は、 何度か観る機会があり、特に印象に残っています。 中でも、可憐で上品な、ヴァージニア・チェリルの容姿と、 心温まるラスト・シーンで 「街の灯」 は好きな映画ですが、 「ライム・ライト」 は、テーマ・ミュージックが、アカデミー賞に輝いた、永遠の名曲と言えるでしょう。 また、映画の中で、主人公の、カルヴェロが、自信を無くした、クレア・ブルーム扮するバレリーナに、 「人生に大切なものは、勇気と想像力だ…。」 というセリフは、私にとっても、大切な言葉となっています。 本来、チャップリンの、独特のペーソスと笑いは、あまり好きではないのですが、何といっても、彼と私は同じ誕生日、 ということで、特別な親近感があるのです。 私の人生に、少なからず影響をおよぼした映画人として、チャップリンと、その作品は、忘れる事が出来ません。  音楽も映画も、時間を超越していつまでも心の奥に生き続けていることに、我ながら驚かされます。 音楽も映画も、時間を超越していつまでも心の奥に生き続けていることに、我ながら驚かされます。 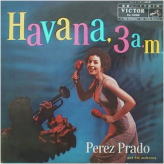 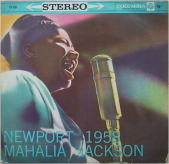  今までのページを振り返ってみました。なんとも、とりとめの無い話になってしまい驚いています。 仕事では、かなり論理性を気にしているのですが、テーマはあっても、その時々に、 思いついた事を書いていくと、結局こういうことになってしまうのです。 〜でも、それも良いかなと思い直して、このまま続ける事にします。 次のページへ 目次へ ホームへ |
| Spotlight 5 |
| ♪ タンゴ:マンボ:その他の音楽 |