今までは、ほぼ時系列で想い出をつづってきましたが、ここらでチョッと方向転換を…。 お気に入り、① レスター・ヤングとビリー・ホリディ ② レスター・ヤングとカウント・ベーシー ③ ハンク・モブリー デクスター・ゴードン ワーデル・グレイ について書いてみようと思います。 6-① レスター・ヤングとビリー・ホリディ  ■ 「Pres & Lady Day」 ■ 「Pres & Lady Day」録音されてから、60数年経ってなお、 私の心を揺さぶる二人、それがビリーとレスターです。 もともとは、カウント・ベーシー楽団が好きで、 そこで二人の世界を知ることになりました。 ビリー・ホリディは、暗い退廃的な歌い方で、あまり好みではなかったのですが、 30年代の彼女の歌は、それまで聴いていたものとはぜんぜん違ったものでした。 というより、レスター・ヤングと一緒のものは、と言い直した方が正しいでしょう。 スタンダード・ナンバーをブルースのように、そして、器楽奏者のように、 自由なフレージングで歌う、ビリー。サックスで歌うレスター。 彼は「歌詞を忘れたら、演奏できない」と言ったそうです。 短いソロの中にも、彼のアイディア豊かなアドリブが存分に表現されて、その斬新さに驚かされます。 彼らのプレイが3分間しかないことで、物足らないと思った事はありません。 むしろ無駄のない歌心が、凝縮されていて心に残ります。 レスターが加わったビリーの歌は、確実に他のものとは異なっています。 レスターの区切るべき時に区切らず、つなぐべき時に区切るといった特異な奏法と、 ビリーの “ずらし” の唱法は見事にフィットし、ジャズの命である、“くつろぎ” を最良の 雰囲気の中で創造しています。 それは、単純にスタイルが似ているという以上に、自分を理解してくれる相手にめぐり合えた喜びと お互いを想う、愛の記録というべきものです。 短い期間の少ない共演ですが、私にとって二人のデュエットは、かけがえのない宝物になっています。 二人は、ルイ・アームストロングの奏法を研究したと言われています。 確かに、キング・オリバーのバンドを辞めて独立した彼が、1925年のベッシー・スミスとの 「St. Louis Blues」 で聴かせる、ベッシーとデュエットしているような、ルイのトランペットは、 それまでの演奏家と歌手の常識をくつがえすインパクトがあったのだろうと想像します。 でも所詮トランペットなのです。優しさ・甘さ・暖かさ、に欠けるのです。 レスターのテナーは、それらを全て持ち合わせています。ソフトな語り口は彼の持ち味ですが、 技術を超えた絶妙なフレージングは、見事にビリーの歌と一体化しています。 特に以下の曲は、最も充実していた時期の共演が中心で、大好きなものばかりです。 ♪ 「Sun Showers」 ♪「This Year's Kisses」 ♪「He's Funny That Way」 ♪「I Can't Get Started」 ♪「Who Wants Love?」 ~レスター以外には、決して見せない、ビリーの若々しく、愛らしい表情が、目に浮かびます。 レスターのテナーも、ふくよかで,張り切っている感じです。 ♪ 「I 'll Never Be The Same」 ♪「A Sailboat In The Moonlight」 ♪「Born To Love」 ♪「Without Your Love」 ~まるで絡みつくような、官能的な雰囲気。これはもう普通の歌手と、奏者の関係を超えています。 スタジオの雰囲気を想像すると、なぜか恥ずかしくなってしまうほどの、親密さです。 ♪ 「The Man I Love」 ♪「I Must Have That Man」 ♪「My First Impression Of You」 ♪「All Of Me」 ~ビリーの甘えるような訴えかけに、なだめるような、さとすような、 優しいレスターの語りかけが印象的です。 気性の激しいビリーが、レスターの前では、素直な自分に戻ってしまうという、愛らしい女性を感じます。 ♪「Foolin' Myself」 ♪「Easy Living」 ♪「I Can't Believe That You're In Love With Me」 ~ゆったり、情感たっぷりに聴かせてくれる歌声。「Foolin' Myself」 も、 特に私のお気に入りの一曲です。 レスターのイントロ、テディ・ウイルソンの美しいピアノ・ソロ、それに続く、 バック・クレイトンのミュート・トランペット。もちろんビリーの熱唱も素敵です。 ♪ 「Trav 'lin All Alone」 ♪「When You're Smiling」 ♪「If Dreams Come True」 ♪「Now They Call It Swing」♪「Back In Your Own Backyard」 ~心地よい明るくスィンギーな演奏。 「When You're Smiling」 で披露する、レスターの軽快で豊な歌心。 バック・クレイトン、テディ・ウイルソンも絶妙なソロを展開します。 この3人は、恐らく、ビリーにとって、自分の可能性を引き出してくれる、得がたいパートナー、 と映っていたに違いありません。 音楽的なフィーリングが似通っていると、私も、この4人に感じています。 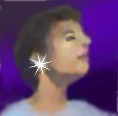 ■ 「Billie Holiday」 ※ これらの曲に共通している、ビリー・ホリディの特徴は、 他のプレイヤーとのセッションでは、決して聴く事の出来ない、 ビリー・ホリディの、甘えるような歌声です。 彼女の声は、一般的には、悪声ですし、声量が豊でもありません。 彼女の歌唱力が、それを逆に生かして、オリジナリティを創り上げているのですが、 それとは別に、レスターとのセッションでは、彼女は、自分の心情を、 レスターだけに聴いて欲しいといった感じの、素直な女らしい気持ちが声に現れているのです。 彼が参加しない他の曲、アルバムと聞き比べてみると、その違いが明白です。 ♪ I'll Never Be The Same ♪ “I'll never be the same Guys have lost their meaning for me I'll never be the same Nothin' s what it once used to be And when the song birds that sing Tell me it's spring I can't believe their song Once love was king But kings can be wrong I''ll never be the same There is such an ache in my heart I'll never be the same Since we're apart But there's a lot that a smile can hide And I know deep down inside I'll never be the same Never be the same again” “失恋の痛手から、私はもう、以前の私ではなくなってしまった” …つらい乙女心を歌った内容です。 テディ・ウイルソンが彼の最高の出来と思わせる、メランコリックなアドリブ・ソロを、 ゆっくりしたリズムの中で展開します。 続く、ビリーが、胸のうちを訴えるように歌いだすと、レスターのサックスが優しく、彼女を包み込みます。 ビリーの切なく、やるせない眼差しと、それを受け止める、レスターの暖かい表情が、目に見えるようです。 素直な二人のデュエットは、聴かせる音楽とは思えないほどの情感に溢れていて、 この一曲に接するだけで、二人は永遠のアイドルです。 ・「He Ain't Got Rhythm」 「This Year's Kisses」 「Why Was I Born?」 「I Must Have That Man」 Buck Clayton(tp) John Jacson(cl) Lester Young(ts) Teddy Wilson(p) Freddie Green(g) Walter Page(b) Jo Jones(ds) 1937年のこれらの演奏で、クラリネットを吹いているJohn Jacson とはベニー・グッドマンのことですが、 彼とレスターとの共演という興味以上に、レスター・ヤングが加わった事で、 このセッションがそれまでとは一変して、優しく、スムーズなものになったことが良く理解できるナンバーです。 サックスで、ビリーの豊な音楽性を引き出せるアーティストは、レスター以外では、 アルト・サックスのジョニー・ホッジスぐらいかと思っています。 ※ ビリーもレスターも、おそらくこのころが、私生活でもプレイでも、もっとも充実していたのでしょう。 特異な歌唱法と、まだ10代の明るさ、あどけなさを、どこかに感じさせるビリー。 20代でありながら、ふくよかで、スムーズで、独特な奏法を完成させているレスター…。 若い二人に接するたびに、甘酸っぱい青春の想い出がよみがえってきます。 1937年~1938年の蜜月時代、サックスと歌に共通してあった明るさが、離れ離れになってから、 影をひそめたような気がします。これは私だけの感想なのかもしれませんが…。  ■ 「Teddy Wilson」 テディ・ウィルソン: ブランズウィック・セッションでの、ビリー・ホリデイ ▽ 1935年: 「Too Hot For Words」 ベニー・グッドマン(Cl) の参加で、 「I Wished On The Moon」 「What A Little Moonlight」 「Miss Brown To You」 「A Sunbonnet Blue」 「Twnty-Four Hours A Day」 ベニー・グッドマンに変わって、セシル・スコット(Cl) 参加で、 「What A Night What A Moon What A girl」 「I'm Painting The Town Red」 「It's Too Hot For Woeds」 20才の、若々しい、ビリー・ホリデイの歌は良いのですが、テナー・サックスに、 ベン・ウエブスターがいるのです。私は、彼の音を聴くだけで、嫌になってしまうのです。 (セシル・スコットは、あの艦長ホレイショ・ホーンブロワーを連想させて、本名とはどうしても思えません。) ・「Yankee Doodle Never Went To Town」 「Eeny Meeny Miny Mo」 「If You Were Mine」 サックスが、チュー・ベリーに変わって、内容的には変わらないのですが、こちらの方が、安心できます。 でも、ビリー・ホリデイにとっては、37年・38年のセッションほどは、感動する出来栄えではありません。 ▽ 1937年: 「Fine & Dandy」 テディ・ウイルソンと、エリントニアンのフロント・ライン(クーティ・ウイリアムス、ジョニー・ホッジス、 ハリー・カーネイなど)とのセッション。 ♪「How Could You」 ♪「Moanin' Low」 などは、音楽的にも素晴らしいものがあり、気に入っています。 このアルバムに、レスターとビリーの最高の記録があります。 デューク・エリントン楽団以外でのジョニー・ホッジスのプレイは好きです。 きちっとしたリズムにのって自由にアドリブを展開する彼のプレイは、レスター・ヤングを思わせる素晴らしさです。 テディ・ウイルソンにとって、ブランズウィック・セッションは、恐らく、彼の生涯のベスト・アルバムだと思いますが、 中でも、ベーシー楽団の、メンバー参加のものが良く、レスター・ヤングと、ビリー・ホリデイの共演のものは、 テディ・ウイルソンも、二人に触発されて、最高のプレイが出来たのではないでしょうか。 ▼ 1941年: 「Mr. Wilson」: 「Smoke Gets In Your Eyes」 「Them There Eyes」 「I Can't Get Started」 「I Surrender Dear」 テディ・ウイルソンの、スタンダード・ナンバーを集めた、聴きやすいアルバムですが、 私には、チョッと退屈な印象です。 ベニー・グッドマン楽団で、レスター・ヤングと、ビリー・ホリディとのコラボレーションで、 名演奏を残した彼ですが、トリオでは、やや線が細く、嫌いではないけれど、是非聴きたい、 というほどではありません。  ■ 「My Lady Day」 ※ 私が、レスター・ヤングとビリー・ホリディの 共演の数々を最も気にいり、あらゆる作品のトップに ランク付けしている理由は、 自分の、過去の想い出を重ねているからにほかなりません。 ……私の音楽へのアプローチは、大抵このスタイルです…。 ※ 十数年前、ボルチモアで、偶然、ビリー・ホリデイの記念館を、訪れる機会がありました。 生い立ちから、数々の活躍の記録が展示されていました。今では、すっかり名士扱いですが、 当時の黒人ジャズ・メンの待遇も同様ですが、生きているうちに、もっと大切にしてもらいたかった というのが、その時の素直な感想でした。 酒と麻薬に身を持ち崩すアーティストが、大勢いた事実は、彼らの人生が、想像を越えた、 絶望感との戦いだった事を物語っています。 私が、ジャズに惹かれるのは、そんな状況でも、明るく、スィングするバイタリティを、 彼らのプレイから感じ取れるからです。 ■ 「ボルティモアの記録」 ♪ 彼女の転機になったと思われる、 「Strange Fruit」 その後の、「God Bless The Child」 「Willow Weep For Me」 「When Your Lover Has Gone」 「Autumn In New York」… ブルース・フィーリングたっぷりで、情感をダイレクトに 表現する歌唱力が評価され、第一人者の地位を築いていったのだと思います。 こんな歌は、私にとっては、暗くて、辛くてたまりません。 ややスィンギーに歌う、「Love Is Here To Stay」 「Remember」 「But Not For Me」 「I Wished On The Moon」 「I Cried For You」…。 高低のイントネーションを多用したフレージングで、説得するように、妙に力んで歌う彼女からは、 レスターと過ごした時期の、あの明るさ、軽快さが微塵もなく、世間の評価に関係なく、 私にとっては、全く魅力を感じません。 いつか、この時期のビリーが聴きたくなるまで、お蔵入りということになります。 大好きな、カウント・ベーシー、ワーデル・グレイと共演している、ビリーのビデオ等を観ても、 特別な感動もわきません。彼女は、1930年代が最も輝いていたのです。 不遇な過去を背負って、なお溌剌としていた、レスターと一緒の頃が、彼女のベストだと私は感じています。 レスターとの共演以外のビリーに魅力を感じないのは、 あまり重いブルース・ナンバーが苦手のせいかもしれません。 スィング・ジャズから始まった、私のジャズの歴史は、ヴォーカルに対しても、 さらっとした上品さを好む傾向にあり、あまりねっとりと歌われると疲れてしまうのです。 ▽ 「The Definitive Billie Holiday / Complete 1933-1944 」 初期の年代別アルバムで、数枚にわたってレスターとの共演がありますが、 二人の生き生きしたプレイが沢山詰っている 「Volume 3 1937-1938」 「Volume 4 1938」 を聴く事がほとんどです。 ここには、アーティ・ショウ楽団での貴重な一曲 ♪「Any Old Time」 も記録されています。 ▽ 「Billie And Lester Jazz Story」 というアルバムを最近買いました。 16曲全部が、既に持っているアルバムに入っている曲ですが、 この編集は素晴らしく、私が聴きたい大抵の曲を網羅しています。イラストも可愛らしく、 便利なので、二人の曲を、と思った時はこれを主に聴く事になりそうです。 ※ レスター・ヤングは、1945年の兵役後からのプレーが全く変わったと言われていますが、 それ以前から音色は変わっていました。 カウント・ベーシー楽団のサックスの僚友、ハーシャル・エバンスの死によって、 かなりの落胆があったと言われていますし、 40年以降、ベーシー楽団を離れてからの演奏を聴くと、アドリブの凄さや、スムーズでやわらかい 独特なスタイルは、より強化されたけれど、心からスウィングしていたビリーとの共演の時とは違って、 音色が、やや重厚になっているような気がします。  ■ 「Lester Young - Nat King Cole Trio」: 1942 ♪ プレス、コール、レッド・カレンダー・トリオでの録音は、 3人が創造性とくつろぎに溢れたプレイを聴かせてくれて、 大好きなセッションですが、レスターのサックスの音色は、 30年代よりやや暗めに感じます。 コールは 「J.A.T.P.」 でハウス・ピアニストとして活躍していますが、 レスターの気に入った演奏も無く、イリノイ・ジャケイなど、趣味の悪いテナー・マンが活躍している 「J.A.T.P.」 のアルバムは、ほとんど嫌いです。 ナット・キング・コールについてはピアニストのページで触れたいと思います。 ※ レスター・ヤングは、私にとって一番のアイドルです。 カウント・ベーシー楽団。カンザスシティ・シックス、セブン。プレスの後継者~、ワーデル・グレイ。デクスター・ゴードン。 ハード・バップ時代に、自分の音にこだわった、ハンク・モブリー等、特別なアーティストへ続けたいと思います。 6-② レスター・ヤングとカウント・ベーシー 〈カウント・ベーシー楽団の魅力〉  ■ 「Count Basie」 ▽ 1937/39年: 「Count Basie The Complete Decca Recordings」 カウント・ベーシー楽団の魅力がギッシリ詰っている、 3枚組みC Dアルバムです。 野性味ある、カンザス・スタイルのジャズが、一流の個人技に支えられて、 ダイナミックに展開されている、 私にとっては、最高にお気に入りのアルバムです。 ♪ 「Honeysuckle Rose」 お馴染みの曲を、小気味良いリズムと、くどいほどのリフであおり、躍動感を作り出す ベーシー・スタイルが、スタートから楽しめます。 ベーシー、プレス、エバンス、クレイトンのスムーズなソロなど、魅力一杯です。 ♪ 「One O'clock Jump」 ベーシー楽団の代表曲。その後沢山聴きましたが、独特のビート、心地よいリズムにのって、 エバンス、プレス、クレイトンがプレイする、ここでの演奏がやはり一番です。 ♪ 「Jumpin'At The Woodside」 「Every Tub」 これぞベーシー楽団の真髄といった最高のジャンピング・ナンバー。 アンサンブルとソロの見事な調和で、エキサイティングで、豊な音楽性に感動します。 クレイトン、エバンス、プレスなど、ベスト・メンバーによるベスト・プレイです。 ♪ 「Swinging The Blues」 「Doggin' Around」 「Shorty George」 この楽団の象徴的、スィング感一杯のリフ・ナンバー。 他のバンドには無いパワフルな魅力がここにあります。 ♪ 「Texas Shuffle」 軽快なリズムに乗って、エディソンのトランペット、ウエルズのトロンボーン、 エバンスのテナー・ソロと、ここでは珍しく、プレスのスムーズな、クラリネット・ソロが聴けます。 ♪ 「Roseland Shuffle」 ベーシーのピアノとプレスのテナー・サックスでの、コール&レスポンスが堪能できるお馴染みの曲。 ♪ 「Pennies From Heaven」 「Exactly You」 「Boogie Woogie」 「Sent For You Yesterday」 「Georgianna」 他、 偉大なブルース歌手ジミー・ラッシングによる、魅力たっぷりのボーカルが堪能できます。 ♪ 「Goodmorning Blues」 「Don't You Miss Your Baby?」 「Blues In The Dark」 クレイトン、ベーシー、ラッシングのしっとりしたブルース・フィーリングは、ラッシングが、 この楽団に不可欠なヴォーカリストであることが良く理解できます。 ♪ 「Blue And Sentimetal」 ハーシャル・エバンスのソロで有名になった、心地よいブルース曲。 彼とプレスのコンビはベーシー楽団の華です。 ♪ 「Booge Woogie」 「Hey Lawdy Mama」 「The Fives」 「How Long Blues」 「Oh! Red」 「Fare Thee Honey, Fare Thee Well」 「Dupree Blues」 等、ベーシーの絶妙な間と、 テクニックが堪能できるピアノ・ソロ。 彼のアーティストとしての創造性と、高い技術が感じ取れます。 ♪ 「Oh, Lady Be Good」 アップ・テンポで、プレスの変わった想像力溢れるアドリブが聴けます。 彼の代表曲ですが、いつも斬新なアドリブなので、原曲を忘れてしまうほどです。 ♪ 「One O'Clock Jump」 「Topsy」 「Swingin' The Blues」 「Every Tub」 「Good Morning Blues」 「Time Out」 「Georgiana」 エディ・ダーハムは、このアルバムに沢山の作・編曲を提供しています。 ギターやトロンボーンの奏者としてだけでなく、ベーシー楽団、カンザスシティ・ジャズにとって 重要な人物だったことが良くわかります。 ポール・ホワイトマンが名づけたといわれる、オールアメリカン・リズム・セクションによる、 躍動感溢れるビートに加えて、モダンジャズへの原動力になった、キラ星の如き スター・プレーヤーによる、見事なアドリブ・ソロ。 この時期がカウント・ベーシー楽団のベスト・メンバーでのベスト・プレイである事に疑いはありません。  ■ 「黒水仙」 : 1946 : Deborah Karr ■ 「黒水仙」 : 1946 : Deborah Karr▽ 1938年: 「Count Basie Live At The Famous Door NYC」 ニューヨークへ進出した、ベーシー楽団のライブ版です。 全体的には、録音状態も、万全とはいいがたく、演奏内容も特に素晴らしいものではありませんが、 ともかく私にとっては、魅力が一杯です。 ♪ 「One Hour」 司会者の紹介を受けて、ヘレン・ヒュームズのヴォーカルが、さりげなく聴けたりします。 ♪ 「Jumpin' at The Woodside」 レスター・ヤングの長いソロ・プレイが楽しめたり、これでもかとばかり繰り返されるリフなども、 ライブならではで、臨場感もたっぷりです。 ♪ 「I Hadn't Anyone Till You」 ジミー・ラッシングのヴォーカルは、ライブで、ひときわゴキゲンです。 ♪ 「King Porter Stomp」 この曲では、ハリー・ジェイムスとプレスの、珍しい共演を聴く事が出来ます。 ♪ 「Oh! Lady Be Good」 プレスと、クレイトンのソロが、中心の曲ですが、観客の談笑が聞こえる中でのプレイは、 質はともかく、あの時代へ、タイム・スリップしたような感覚を味わう事が出来、 最高の気分にひたれます。 これを聴きながら、カウント・ベーシー楽団にとって、レスター・ヤングが、 欠くことのできない、花形プレイヤーだったのだなーと、つくづく感じます。 ▽ 1944年: 「Count Basie and his Orchestra」 ・「Gee Baby ,Ain't I Good To You」 「Lady Be Good」 「Basie Boogie」 など、 戦時中で、プレイヤーの出入りの激しい時代にもかかわらず、素晴らしい演奏内容です。 アーティ・ショーが、ゲストでプレイしています。  ■ 「Count Basie & His Sextet」 ■ 「Count Basie & His Sextet」 ▽ 1950年: 「Count Basie & His Sextet」 ♪「Basie Boogie」 のベスト・プレイを聴けます。ベーシーのプレイは超人的で、 彼がピアニストとしても、一流である事を証明しています。 ・「One O'clok Jump」 「Bass Conversation」 クラーク・テリー(tp)、バディ・デ・フランコ(cl)、ワーデル・グレイ(ts)のフロントラインで、 メンバーが少ないにもかかわらず、かつてのフルバンドばりの、厚みのある名演奏を聴かせてくれます。 ここでのワーデル・グレイは、ベニー・グッドマンとカウント・ベーシーという、両巨頭がほれ込んだ、 貴重な存在だった事が理解できる、のびのびとスィングするテナー・サックスを聴かせてくれます。 ビッグ・バンド受難のこの頃が、カウント・ベーシーにとっても、辛い時期だったろうと想像します。  ■ 「大運河」 : 1959 : フランソア・アルヌール ■ 「大運河」 : 1959 : フランソア・アルヌール▼ 1955年: 「April In Paris」。 ▼ 1956年: 「Basie In London」。 ▼ 1957年: 「Basie/Count Basie Orchestra」。 再生カウントベーシーの、最もビッグバンドとして充実していた時期、 と言われています。確かにオーケストラの統一感・スムーズな音楽性などは、 30年代に比べてはるかに良くなったのかもしれません。 でも、あまりに洗練され、個性がなくなってしまい、普通の白人スウィング・バンドと 変わらなくなってしまった感じで、私には物足りません。 57年の 「Basie=アトミック・ベーシー」 のライナーに “全てニール・へフティのオリジナル曲で、 これ以降のモダンなサウンドの出発点になった”とありますが、 確かにリアル・タイムのベーシーには、イマイチ物足らない感じを抱いていたものでした。 ▼ 1963年: 「This Time By Basie」 クインシー・ジョーンズがアレンジした、このアルバムは全くダメです。 我がカンザスの香り豊かな、ベーシー楽団ではありません。  ■ 「Jazz Kansas City Style」 ■ 「Jazz Kansas City Style」カウント・ベーシー楽団魅力の原点 ▽ 「Jazz-Kansas City Style」 「New Vine Street Blues」 : 1929 / Bennie Moten's Kansas City Orchestra で始まる、 カンザス・ジャズの魅力満載のCDアルバムです。 「Shoe Shine Boy」 「Doggin' Around」 などベーシーとプレスのお馴染みの曲もありますが、 「Dexter Blues」 1941 / Jay Mcshann And His Orchestra では、 若き日のチャーリー・パーカーもプレイしています。 アルバムを通して、ブギ・ウギ、ブルース感覚に溢れたカンザス・スタイルが堪能できます。 やや荒っぽいけれど、リフを多用し、よくスィングするリズムと、個性的なソロ・ワークが特徴で、 洗練されたアレンジによる都会のスィング・ジャズとは一線を画しています。 ※ ダッジ・シティはワイアット・アープやドク・ホリディ、またバット・マスターソンが活躍した 町として有名ですが、こちらはカンザス州。ジャズが盛んになったカンザス・シティは、 ジェシー・ジェイムスの生まれたミズーリ州側の方です。 アメリカの中央に位置し、カウ・ボーイによって辺境地から沢山の牛が集めらた場所で、鉄道の分岐点、 都会への出発点だったことは、ジョン・ウェインの 「赤い河」 など西部劇映画ですっかりお馴染みです。 「赤い河」は 「リオ・ブラボー」 チャンドラーの「三つ数えろ=大いなる眠り」 を撮った ハワード・ホークス監督の作品ですが、共演のモンゴメリー・クリフトが好きではない為、 私の映画ランキングでは、あまり上位ではありません。  ■ 「最初のテキサス人」 : 1956 : Felicia Farr ■ 「最初のテキサス人」 : 1956 : Felicia Farr その後も、悪徳政治家ペンダー・ガストのおかげで、禁酒法も関係なく、30年代は大歓楽街が出現。 ミュージシャンの活躍の場も確保され、新しい土地だけに人種差別も無い自由な街として、 周辺の州から有能なジャズ・メンも、沢山集まってきたのです。 その結果、個人技とグループ・ハーモニーの整合という独自のジャズを完成させたのですが、 その頂点に君臨したのが、カウント・ベーシー楽団だったわけです。 彼を気に入っている理由が、善玉・悪玉入り乱れる世界で、自分の腕だけが頼りに生きた、 西部開拓時代のロマンを感じるからかもしれません。 ※ 白人ビッグ・バンドの魅力が、編曲重視の、一糸乱れぬ洗練されたハーモニーにあったのに比べ、 ベーシー楽団最大の魅力は、単純なヘッド・アレンジを受けて、プレーヤーが、 個々の解釈によるアドリブで、曲全体の魅力を創り出していたことです。 カンザス・シティ・ジャズが、モダン・ジャズの原点であったことは間違いなく、 その要因は、優れたプレイヤー同士のジャム・セッションにあったはずです。 ジャムセッションの魅力は、当然アーティストで決まり、結局のところ、 私のベーシー楽団のスター・プレーヤーは、トランペットは、バック・クレイトンと ハリー・スウィーツ・エディソンであり、ジョー・ニューマンとサド・ジョーンズではなく、 テナーは、レスター・ヤングとハーシャル・エバンスであって、決して、フランク・フォスターと フランク・ウェスでは、満足できないということになってしまうようです。  ■ 「Duke Ellington」 ■ 「Duke Ellington」一般的に言って、黒人ビッグバンドの最高峰は、 デューク・エリントン楽団であることは、間違いないところなんでしょう。 ・「Sophisticated Lady」 「Satin Dole」 「Solitude」 「Caravan」…。 1924年にバンドをもってから、数々の名曲を残し、 個性的なソロ・プレイ、ボーカルをからめた独自の音楽を確立したのですから…。 でも、私はあまり好きではありません。 ボードビル・ショウ的な演出や、ドラマティックで、複雑なアンサンブル・スタイルによる 独特のハーモニーは、どうも波長が合いません。 もうチョッと単純で、心地よいスィング感、リズム感が望ましいところです。 「Take The A Train」 などは歯切れがよく、ビッグ・バンドのテーマ曲の中では、最も気に入ったナンバーなのですが…。 ※ カンザス・シティで、カウント・ベーシー楽団と、ジミー・ラッシングのような関係で、 ピート・ジョンソン楽団と、ジョウ・ターナーがいます。ブルースとジャズが融合した、 独特なカンザス・シティ・スタイルの、中軸を成す両楽団ですが、ここでも私の好みは微妙に分かれます。 ベーシー楽団や、ラッシングは、ジャズに求められる、ある種の上品な表現が 備わっているのに対して、ジョンソン、ターナーのほうは、もろにブルージーです。 (本当のところは、ターナーの声があまり好きではないのです。) カンザス・ジャズのバンドには、気取らない仲間同士の結束、ブルース・フィーリング、 リフの多用、という解りやすくノリ易い、共通したスタイルがあり、ピート・ジョンソンの ブギ・ウギ・ピアノを嫌いではありませんが、ベーシー楽団はそれだけではないのです。  ■ 「Boogie Woogie Pianists」 ■ 「Boogie Woogie Pianists」※ ブルース・シンガーでは、T・ボーン・ウォーカー、B・B・キングなど、 それぞれ気に入ったアーティストはいますが、ジャズとブルースを同時に聴く事はほとんどありません。 但し、カンザス・シティ・ブルースの巨人:ジミー・ラッシングは、 カウント・ベーシー楽団の重要なアーティストとして別格の存在です。 ブルースも取り上げたいのですが、いつになることやら…。 昔、リトル・ウォルターのように吹いてみたいと思って、 ブルース・ハーモニカ(ハープ)を買ったのですが、頓挫したままになっています。 楽器が手頃だからといって、簡単にマスターできるわけではない事を、 当時思い知らされたのですが、いつか、再度挑戦してみようかとも思っています。 スロー・ブルースの心地よいリズム、安心して聴いていられる単純なメロディ、 ヴォーカルと楽器のハーモニー…。黒人のブルースには、彼らの歴史を感じる、 重さ、泥臭さと同時に、優れた音楽性と、くつろぎが感じられて大好きです。 〈レスター・ヤングのベスト・プレー〉  ■ 「Lester Young」 ■ 「Lester Young」 ジャズの歴史に合わせて成長してきたわけではないので、 20年代から60年代までのジャズを、ごちゃ混ぜに聴いて育ってきた事になります。 ですから、古い、新しいという基準で音楽を考えた事がありません。 ジャンルについてもこだわりがありませんから、好きな曲、 好きなアーティスト本位で、今でも、色んな音楽を楽しんでいられるのでしょう。 レスター・ヤングは、沢山のテナー・サックス・プレイヤーの演奏を聞き比べた結果から、 一番素晴らしいテナー・マンだと思っていますし、一番気に入っているアーティストです。 彼のCDは、今でも、ほぼ毎日聴いているという有様ですから、好きだ嫌いだのレベルではないともいえます。 アルバムで特に気に入っているのは、 「The Complete Lester Young」 「Lester Young The Kansas City Sessions」 の2枚かもしれません。 「Lester Young Trio」 も大好きですから、限定する事自体あまり意味がありませんが…。 ▽ 1944年:「The Complete Lester Young」 Buck Clayton(tp) Dicky Wells(tb) Lester Young(ts) Count Basie(p) Freddie Green(g) Rodney Richardson(b) Jo Jones(ds) ♪ 「Six Cats And A Prince 」 これは、3テイクとも素晴らしく、メロディ、リズムとも申し分なく、楽しげにスィングする、 ベーシー、バック・クレイトン、プレス、ディッキー・ウエルズ、のテイクごとに変えたソロを堪能できます。 どれほど各人が自由なアドリブを展開しても、曲全体のまとまりは少しも損なわれない、 見事なハーモニーです。 ♪ 「Lester Leaps Again」 これも、クレイトンの曲ですが、ベーシーとプレスの息の合ったプレイは、 空白の時期を感じさせない見事なものです。 ピアノとサックスの、熱の入ったやり取りを十分楽しめます。 ベーシーの絶妙な「間」は、プレスを触発して、曲全体を包む緊張感と開放感がたまらない魅力です。 ・「After Theatre Jump」 「Destination」 も含め、全曲、力強いスィング感に満ち溢れ、ベーシーを軸にした、メンバーの個人技の凄さ。 カンザスシティ・セブンの最高の演奏を満喫できます。  ■ 「夜の豹」 : 1958 : Kim Novak ■ 「夜の豹」 : 1958 : Kim Novak▽ 1938/44年:「Lester Young The Kansas City Sessions」 38年:Buck Clayton(tp) Young(cl,ts) Eddie Durham(tb,g) Fredde Green(g) Walter Page(b) Jo Jones(ds) ・「Way Down Yonder In New Orleans」 「Countless Blues」 ダーハムのギター、クレイトンのトランペット、プレスによるふくよかな サックスとクラリネットが、なんともレイジーです。 チャーリー・クリスチャンにも影響を与えたという、エディ・ダーハムのギターが楽しめる、 ピアノ・レスの、ブルース・フィーリングたっぷりのセッションです。 ♪ 「I Want A Little Girl」 クレイトンのトランペット、プレスのクラリネットのくつろいだプレイが最高で 思わずハミングしてしまう名演奏です。2テイクの、微妙に違うニュアンスも、たまらない魅力です。 この曲は、ジミー・ラッシングのボーカルものも大好きです。 トラディショナルなスロー・ブルースでの、レスター・ヤングのクラリネットの音色は、 ニューオールリンズ育ちでありながら、洗練されたセンスを感じさせます。 クール・ジャズといわれるスタイルは、ここらあたりを参考にしているのでしょうが、 プレスの “無駄の無い音に隠された叙情性”を、モノに出来ずに、単なるスタイルを真似るだけでは、 チッとも心に響いてこない事を知るべきです。 ♪ 「Pagin' The Devil」 ゆったりしたテンポのブルース。プレスとクレイトンの豊な音色は、 ジャズにくつろぎを求める私を、十分満足させてくれます。 44年:Bill Caleman(tp) Dicky Wells(tb) Young(ts) Joe Bushkin(p) John Simmons(b) Jo Jones(ds) ♪ 「Jo Jo」 「Three Little Wards」 カンザス・ジャズの香りプンプンの、リフ・ナンバー。 ソロイスト達の達者なアドリブが、単純なメロディに彩りを与えています。 ・「I Got Rhythm」 プレス、コールマン、ウェルズのアドリブは、お馴染みのこの曲を、全く違った解釈で、 3テイクも楽しませてくれます。 ※ ビックス・バイダーベックと、トランバウアーの共演で有名な曲: 「Singin' The Blues」 彼の、C・メロディー・サックスでの、レイジーで、豊な音色は、レスター・ヤングに、 少なからず影響を与えたことが解ります。 彼に続く、ビックスの、情感豊なコルネットのソロを聴くと、なんとなくレスター・ヤングと バック・クレイトンとの名コンビを連想させます。 ブルース・フィーリングの素晴らしさは、プレスとクレイトンには当然かないませんが、 ビックスとトラムについては、別なページで、触れたいと思います。  ■ 「Lester Leaps In」 ■ 「Lester Leaps In」▽ 1936/40年:「Lester Leaps In」 ♪ 「Lester Leaps In」 「Taxi War Dance」 「12th Street Rag」 「Dickie' Dream」 「Moten Swing」 ベーシー・オーケストラや、カンザス・シティ・セブンなどでの、プレスの名演が楽しめます。 「Lester Leaps In」 は、ガーシュインの 「I Got Rhythm」 のコード進行を使って、 プレスがリフ・ナンバーとして作ったそうですが、言われてみればそんな感じもします。 ▽ 1944/49年:「The Immortal Lester Young」 ♪「Blue Lester」 ♪「Gost Of A Chance」 「Back Home In Indiana」 「Jump ,Lester ,Jump」 44年兵役直前の、クインテットでのプレイです。これを境に彼の音楽が、人生が、変わっていくのです。 ▽ 1942年:「Lester Young -Nat King Cole Trio」 ♪「Indiana」 「I Can't Get Started」 「Tea For Two」 レッド・カレンダーが参加してのトリオです。プレスとコールの組み合わせは、ジャズで最も必要な、 レイジーでくつろいだ雰囲気に満ちていて申し分ありません。 ▽ 1946年:「Lester Young Trio」 ナット・キング・コール(P)、バディ・リッチ(Ds)のトリオ演奏ですが、スタンダード・ナンバーが心地よく、 一人静かに、ジャズの雰囲気に浸りたい時欠かせない、お気に入りアルバムです。 ♪「The Man I Love」 レスター・ヤングとナット・キング・コールの、息がピッタリ、シャレたフレージングも最高で、 大のお気に入りナンバーです。 ・「Back To The Land」 「I Cover The Waterfront」 「Somebody Loves Me」 「I've Found A New Baby」 「Peg o' My Heart」 「I Want To Be Happy」 「Mean To Me」 全て気に入っています。カウント・ベーシー、テディ・ウイルソン、ナット・キング・コールとそれぞれ 違った味わいがありますが、トリオということもあり、コールとの演奏が一番くつろいだ雰囲気を感じます。 ▽ 1946/58年: 「Lseter Young Prez Conferences」 ♪「These Foolish Things」 「Lester Leaps In」 「D.B.Blues」 「I Got Rhythm」 「Oh,Lady Be Good」 「Sweet Georgia Brown」 復員後から、最後の年までのライブ特集ですが、46年の録音の6曲は、スィング感、 フレージングも申し分なく、言われているブランクを感じさせない素晴らしい演奏です。 特に、プレス自身の曲紹介で始まる 「These Foolish Things」 は、彼のベスト・プレイだと思います。  ■ 「president」 ■ 「president」♪♪♪ 沢山ある、お気に入りの中で、もし、3曲だけ選ぶとしたら、 その時の気分もあるので、難しいのですが、次の曲かもしれません。 ▽ 1936年: 「Jones-Smith Inc.」 ♪ 「Lady,Be Good」 スウィンギーで、レスター・ヤングのアドリブは最高です。 この曲を彼は、その後何度も演奏していますが、これに勝るものを聴いていません。 この録音時の、他の3曲:「Shoe Shine Boy」 「Evenin'」 「Boogie Woogie」 も良くて、 その後の楽団を凝縮するような、見事なプレイに溢れています。 “レスター・ヤングのふわっとした、独特の味がまだ完成されていない” というような、批評を見た事がありましたが、大きなお世話です。 ♪ 「I 'll Never Be The Same」 ビリー・ホリディとの共演の中で、たった一曲と言われたら、この曲でしょう。 ♪ 「Ad-Lib Blues」 チャーリー・クリスチャンとの数少ない共演の中でも、レイジーな二人を満喫できる特別な曲です。 名手達を差し置いて、最初のソロがチャーリー・クリスチャンというのもニクイところです。 当然、プレス、クレイトン、ベーシーのソロも、ブルース・フィーリングに溢れていて見事です。  ■ 「間違えられた男」 : 1957 : Vera Miles ■ 「間違えられた男」 : 1957 : Vera Miles× あまり気に入っていない演奏もあります。 ▼ 1939年: 「Basie's Bad Boys」 「Goin' To Chicago」 「Live And Love Tonight」 ベーシーのオルガン、プレスのクラリネット、ラッシングのヴォーカルまでも元気なく、 スィング感が無い演奏です。 「Love Me Or Leave Me」 ピアノにもどって、パンチの効いたベーシー・サウンドが、ようやく聴けます。 プレスは暗めながら、美しいアドリブを聴かせてくれます。 このアルバムは、全体的には単調な印象で、好きではありません。 ▼ 1939年: 「Glenn Hardmann And His Hammond Five」 「China Boy」 「Exactly Like You」 「On The Sunny Side Of The Street」 「Upright Organ Blues」 「Who?」 「Jazz Me Blues」 折角プレスもサックスとクラリネットで頑張っていますが、 オルガンは苦手ですし、セッションの性格が曖昧な感じも気に入らず、全くいただけません。 ▼ 1956年: 「Pres & Teddy」 「All Of Me」 「Prisoner Of Love」 「Love Me Or Leave Me」 等。 20年後の再会セッションで、素晴らしい出来栄えと言われていますが、そうでしょうか…。 単調な感じで、あまり気に入っていません。 当然、レスター・ヤングとテディ・ウイルソンという事で、嫌いなわけはありませんが、 ベスト・プレイには、程遠いと思います。 ▼ 1955年: 「Pres & Sweets」 ベーシー時代の仲間ですが、これはダメです。レスター・ヤングの出来は良くなく、トランペットは、 ハリー・スウィーツ・エディソンより、バック・クレイトンが好き、という事もあります。 彼は、ビリーとのセッションでも、レスターに勝るとも劣らない、数々の名プレイを残しています。 ▼ 1952年: 「The Presidennt Plays With The Oscar Peterson Trio」 これも、レスター・ヤングは、良くありません。また、スウィンギーなピアノ奏者として 抜群の人気のある、ピーターソンですが、私は好きではありません。 巧すぎて、どの曲を聴いても同じようで…、「味」を感じません。 ▼ 1951年: 「Lester Young Quartet: Live at Birdland」 ピアノ:ジョン・ルイス、ベース:ジーン・ラミー、ドラムス:ジョー・ジョーンズ、のカルテットですが、 レスター・ヤングの、くぐもった音色に魅力がなく、全体として、陽気なスィング感に乏しい アルバムになっています。 ▼ 「Masters of Jazz / Coleman Hawkins & Lester Young」 サックスの巨人二人による、50年代の演奏を集めた、コンピレーション・アルバム。 コールマン・ホーキンスがバド・パウエルと共演し、レスターがホレス・シルバーと一緒だったりと、 夢の共演と言いたいところです…、が、買ってしまったものの、一度しか聴いていません。 レスターの演奏は、51年~56年の放送録音らしいのですが、魅力を感じません。 レスター・ヤングのアルバムは、ダブりながら、沢山CD化されていますが、 1936年~1944年までのものは、沢山購入し、やや違った編集内容を、その時の気分で、 聞き分けているというありさまです。 とも角、いつでも聴けるように、厳選した、5枚ほどのCDは、手元に置いてあります。  ■ 「My President」 ■ 「My President」 ビリー・ホリディは、魅力ある特異なフレージングと、ブルース・フィーリングで、 レスター・ヤング、バック・クレイトン、ジョニー・ホッジス、テディ・ウィルソンなどとの共演で、 不朽の名作を残してくれました。 私をそこへ導いたのは、カウントベーシー楽団で、そもそもベニー・グッドマン楽団が原因なのです。 彼のレコードの中に、 1938年録音: 「One O'clock Jump」 があり、カウント・ベーシーの名前があったのです。 フレッチャー・ヘンダーソンとか、エドガー・サンプソンが、グッドマンのアレンジャーとして有名でしたが、 この曲がカウント・ベーシー楽団のテーマだった事を後で知ったのです。 両者を聴き比べると、グッドマンの方が上品でベーシーの方は、これでもかと、しつこいリフが展開され、 ベーシー楽団の特徴と魅力を体感することになりました。  ■ 「波も涙も暖かい」 : 1959 : Eleannor Parker ■ 「波も涙も暖かい」 : 1959 : Eleannor Parkerレスターヤングとベーシー楽団については、もっと想いがあるのですが、これまでにし、 好みのテナーサックス奏者について続けたいと思っています。 6-③ ハンク・モブリー、デクスター・ゴードン、ワーデル・グレイ  ■ 「Feeling Of Jazz」 ■ 「Feeling Of Jazz」 ~① ハンク・モブリー~ まるく、包み込むような、あたたかい音色が心地よく、私は、テナー・サックスという楽器が好きです。 それと、リリカルのなかにもスィング感があり、ほどほどの、ブルース感覚がただようアーティストが好みです。 となると、黒人で、ヴィブラートを効かせない、歌心あふれるプレーヤーということになり、 30年代のレスター・ヤングはもちろん、40年代は、ワーデル・グレイ、 50年代は、ハンク・モブリーということになります。 彼らより、力強い音ですが、素直な表現力と、優しさに溢れている、デクスター・ゴードンも大好きで、 この四人については、理屈ぬきで気に入っており、サックスといったら、先ずこの人たちです。 ♪ 「Remember」 「Fin De L'affaire」 「Soft Winds」 「Alone Together」 「I see Your Face Before Me」 「Git-Go-Blues」 「The Best Things In Life Are Free」 「Darn That Dream」 「Space Flight」 「Deep In A Dream」 「I should Care」 「Urtra Marine」 これらの曲は、 ▽「Mobleys Message」 ▽「Mobley's 2nd Message」 ▽「Jazz Message #2」 ▽「Hank Mobley Sextet」 ▽「Poppin' Hank Mobley」 ▽「Hank Mobley And His All Stars」 ▽「Hank Mobley Quintet」 ▽「Curtain Call Hank Mobley Quintet」 ▽「Peckin' Time」 ▽「Soul Station」 ▽「Workout」 ▽「Dippin'」 ▽「A Slice Of The Top」 ▽「The Jazz Messengers At The Cafe Bohemia Volume 1 & 2」 手持ちのCDの中から、ゆったりしたモブリーを聴きたい時のために、一枚にまとめた、私のアルバムです。 サックスの持つ、豊かな音色と、リラックスしたモブリーのプレイが、凝縮されています。 彼のアルバムには、必ず、歌ものが入っていて、センスの良さを感じると共に、目指している音楽が、 私の好みに合致しているのです。  ■ 「Hank Mobley」 ■ 「Hank Mobley」※ 彼は、アート・ブレーキー、ホレス・シルバーと一緒に、ハード・バップを旗揚げした、 ジャズ・メッセンジャーズの主要なメンバーで、本来なら、もっと、ハードで、 ファンキーな匂いがしても不思議ではないのですが、彼の、スウィンギーで、優しく、まるい音色は、 丁度、カウント・ベーシー楽団での、レスター・ヤングのような感じで、 調和の取れた、上品さを保つために、欠かせない、重要な役割を担っていたと思います。 人のよさそうな風貌も、音と合っていて、魅力を増しています。 歌心あふれるプレーヤーとして、文句なく、私の大のお気に入りアーティストです。 ▽ 1955年: 「The Jazz Messengers At The Cafe Boemia」 以降、沢山のアルバムを聴いてきましたが、 前述した、「Soft Winds」 「Alone Together」 等、バラッドものは見事ですし、 スピード・ナンバーでの、もそもそした感じの、それでいて、難しいアドリブを次々展開する、 彼の独特のプレイ・スタイルも、身内のようにハラハラした気持ちにさせる…、 不思議なミュージシャンです。 当然、ホレス・シルバー・クインテットの中にも、大好きな曲が、いくつもありますが、別なページにします。 ▽ 1960年: 「Soul Station」 ♪ 「Remember」 「This I Dig Of You」 「Dig Dis」 「Split Feelin's」 「Soul Station」 「If I Should Lose You」 ウイントン・ケリー(P)、ポール・チェンバース(B)、アート・ブレーキー(Ds) メンバー全員が、全曲スィング感に溢れた、最高の出来栄えで、私の、ベスト・アルバムです。 モブリーの音は、知的で、優しく、暖かさに満ちていて、このアルバムは、 イージー・リスニング・ミュージックのような、心地よい響きで、どの曲をとっても“くつろぎ”に満ちています。 ハード・バップなどの枠には収まらない、良質な音楽を楽しめます。 上品なスィング感の中にも、ちょっとファンキーさを漂わせる、ウイントン・ケリーのピアノもゴキゲンです。 フレージングのスムーズさ、ブレーキーの的確なサポートもあって、モブリー・ミュージックのあるべき姿が、 実現したアルバムだと思います。 50年代後半、並みいるハード・バッパーの中で、自分の音を、歌心を、守り通した彼の、 音にたいするこだわりが素晴らしく、その優しい音色は、いつ聴いても、私の心を満たしてくれます。 時に、難しいフレーズを使い、ろれつが回らないような、もどかしさを感じるのですが、それがまた、 彼の素朴な味わいとしての、魅力となっています。 ▽ 1957年: 「Hank Mobley Quintet」 ・ 「Funk In Deep Freeze」 「Wham And They're Off」 「Fin De L'affaire」 「Startin' From Scratch」 「Stella_Wise」 「Base On Balls」 アート・ファーマー(Tp)、ホレス・シルバー(P)、ダグ・ワトキンス(B)、アート・ブレーキー(Ds) 勝手知ったるジャズ・メッセンジャーの、これは、モブリーがリーダーでのアルバムだけに、 ハード・バップのリーダーたちの、落ち着いたプレイを満喫できます。 ▽ 1957年: 「Curtain Call /Hank Mobley Quintet 」 ・ 「Don't Get Too Hip」 「Curtain Call」 「Deep In A Dream」 「The Mobe」 「My Reverie」 「On The Bright Side」 ケニー・ドーハム(T)、ソニー・クラーク(P)、ジミー・ロウサー(B)、アート・ブレーキー(Ds) モブリーのオリジナル曲主体のアルバムです。 ブルーノートの仲間たちと、くつろいだ雰囲気の中で、テナー・サックスの心地よい音色を、 心ゆくまで楽しめます。 ソニー・クラークのピアノは、シルバーとは違って、よりブルージーで、派手さはないけれど、 しっとりしたプレイに好感が持てます。  ■ 「East Of Eden」 : 1955 ■ 「East Of Eden」 : 1955この、2枚のCDも、いつでも聴けるようにそばにおいてあります。 安心してくつろげる、アルバムです。 ホレス・シルバー、ソニー・クラークは、ブルースを目一杯感じさせる、好きなピアニストです。 各自のアドリブ・ソロが、統一のとれた、魅力あるテーマの中で、自由に表現されるという、 ハード・バップの典型的な演奏を満喫できるアルバムです。 ※ マイルス・デイヴィスが、ハード・バップでは、数々の名演奏を残し、 気に入ったナンバーも何曲かありますが、モード以降の演奏には、少しも魅力を感じませんし、 モブリー、ウイントン・ケリー、キャノンボール・アダレイ、など好きなプレイヤーを、 巻き込まないでもらいたかったものです。 スタイルを変えすぎるプレイヤーは、あまり好きではありません。 モブリーが、マイルス・グループに所属していた頃の一枚、 ▽ 1961年:「Work Out」: タイトル曲での長めのソロにも、モブリーの非凡な才能を感じますが、やはり、前述した 「The Best Things In Life Are Free」 「Three Coins In The Fountain'」 などの歌ものを アルバムに入れる、彼の美意識が好きです。 ▽ 1965年:「Dippin'」での、「Recado Bossa Nova」: 覚えやすいテーマと、調子のよさで、随分流行った曲ですが、とも角、この頃は、 カントリーか、ディキシーがメインでしたから、モダン・ジャズも、やってるな!といった程度でした。 その後大好きになるモブリーですが、積極的に聴き始めるのは、もう少し後の事です。 彼は、サックス奏者として、一流ではない。などと書いた記事を見た事があります。 音楽を楽しむ心をもたない、淋しい発言といわざるを得ません。 私にとってのモブリーは、レスター・ヤングと同じく、心を潤してくれ、癒してくれる、 大好きなアーティストなのです。 チョッとテナー・サックスでも…、と思った時 「Remember」 を選ぶ事が多いようです。 ~② デクスター・ゴードン~  ■ 「Dexter Gordon」 ■ 「Dexter Gordon」彼の魅力は、何と言っても、ストレートな表現による、豊な叙情表現です。 低音部の腹に響く音も、テナー・サックスの魅力を十分感じさせてくれます。 堂々とした音色を通して、彼の優しさ・暖かさが伝わってきて、心が安らぎます。 レスター・ヤングのスタイルを、独自の音楽へと昇華させた、素晴らしいプレイヤーだと思います。 ▽ 1945年~1947年: 「Dexter Rides Again」: バド・パウエル、タッド・ダメロンなど、ビ・バップの先駆者と言われる人たちとの演奏ですが、 彼らしい歌心は感じますが、やはりこの中でも、「I Can't Escape From You」のような、 バラッド以外は、あまり心に響きません。 ▽ 1961年:「Dexter Calling」 : 「Soul Sister」 「Ernie's Tune」 ▽ 1962年:「Go!」: 「I Guess I 'll Hang My Tears To Out To Dry」 ▽ 1962年:「A Swingin' Affair」: 「Don't Explain」 「Until The Real Thing Come Along」 ▽ 1963年:「Our Man In Paris」: 「Willow Weep For Me」 「Stairway To The Stars」 ▽ 1965年:「Clubhouse」: 「I'm A Fool To Want You」 ▽ 1967年:「Come Rain Or Come Shine」: 「Misty」 ▽ 1976年:「Biting The Apple」: 「Georgia On My Mind」 これらは、ブルー・ノートでの復活以降の、気に入っているアルバムと曲です。 彼のバラッドは、堂々たる音色に同居する、誠実な優しさ、時に、恥じらいなど、 彼独特のリリシズムが、とても好感が持てて大好きです。 (もちろん、アップテンポのスィンギーな演奏にも、良いものが沢山ありますが)。 最近、彼のバラッド特集のCDがでて、思わず買ってしまったのですが、チョッと選曲に異議があります。 そのうち、自分の好みで作り変えて、楽しもうと思っています。  ■ 「裏窓」 : 1955 ■ 「裏窓」 : 1955アルバムとして、特に気に入っているのは、▽ 1955年: 「Dexter Blows Hot And Cool」 バップ曲と、スタンダード曲が、交互に入っています。 特に、「Cry Me A River」 「I Should Care」 「Tenderly」 など、 スローなスタンダード・ナンバーを聴けるのが幸せです。 彼は、50年代を、ほとんど棒にふったアーティストとして有名ですが、貴重なだけではない、 ウエスト・コーストのサイドメンを従えての、シャレたアルバムです。 ▽ 1955年: 「Daddy Plays The Horn」 ピアノのケニー・ドリューは、61年、67年にも共演していますが、スィンギーで、ファンキーなムードが、 このアルバムを、より魅力的なものにしています。 ・「Daddy Plays The Horn」 「Confirmation」 「Darn That Dream」 「Autumn In New York」 「You Can Depend On Me」 「Number Four」: ゴードンは、ソロの中に、聴いた事のあるメロディを、さりげなくはさんで、お茶目なところを、 ここでも見せています。 全曲スムーズなメロディと、心地よいリズム感に満ちていて、トップに位置する、お気に入りのアルバムです。 ▽ 1963年: 「Our Man In Paris」 チャーリー・パーカー、ビリー・ホリディ、レスター・ヤング、ディジィ・ガレスピイを特集したアルバムで、 スロー・ナンバーはもちろん、バップ・ナンバーも素晴らしく、最も好きなアルバムです。 中でも、バド・パウエルのピアノは、心打たれます。 イメージに、指がついてこないところも、チョッとはありますが、それが、またたまりません。 ♪ 「Willow Weep For Me」 では、少ないソロの中に、きらびやかな、気高さを感じ、心うたれます。 ケニー・クラークのドラムを楽しめる、「A Night In Tunisia」 もよく、再会セッションの、 くつろいだ中での、おなじみの曲目であることから、全曲気に入っています。 ▼ 1986年: 「Round Midnight」 映画の、サントラ盤です。この映画を観ていません。 CDを買ったのですが、曲に、メリハリが無くて、二度と聴きません。 ※ かつて(70年代初期)、ビリー・ホリデイの、伝記映画がありましたが、敢えて観ませんでした。 ビリー・ホリディ役が、シュープリームスの、ダイアナ・ロスでは、話になりません。 彼女を見ると、子供の頃 「ウシュカ・ダラ」 「セ・シ・ボン」 等を歌って人気のあった、 アーサ・キッドを想い出します。あの声、あの顔、チョッと苦手でした。 好きな小説を読んで、広がった素晴らしいイメージが、チープな映画化で、 一気にガッカリさせられることがよくありますが…、 ビリーは私の心の中でそのままにしておきたかったのです。 ▽ 1943年・44年録音の初めての、リーダー・セッションで、 ナット・コール、ハリー・スィーツ・エディソン、レッド・カレンダー、 クリフォード・ジューシー・オーエンスが参加しています。 「I've Found A New Baby」 「Rosetta」 「Sweet Lorraine」 「Blowed And Gone」 : レスター・ヤングのスタイルそのままで、うれしいような、しかし、まだ彼の音楽ではないという感じがします。 ♪ 「Sweet Lorraine」 だけは、なぜかふくよかな音色と、落ち着いたプレイで、大器を予感させます。 タイプの違う二人ですが、レスターの、無駄のない、さらっとしたリリシズムを学んで、 自分のスタイルを確立してからも、そこだけは崩さなかった事が、うれしい限りです。 他にも、フレッチャー・ヘンダーソン、ルイ・アームストロング、ライオネル・ハンプトンという ビッグ・バンドでの、若き日のゴードンを、CDで楽しむ事が出来ますが、 彼のサックスはワン・ホーンでの、しかも、40才前後でのプレイが堂々としていて、充実しているように思います。 一曲だけ、選ぶとすると、 ♪♪ 「Don't Explain」 1962年:「A Swingin' Affair」 になります。 ビリー・ホリディを想いだすという以外に、素直なフレージングと、豊かな音量の中に、 優しさが溢れていて、心がうずきます。 ピアノのソニー・クラークも、控えめな音の中に、切ないばかりの想いが込められていて、 これ以上望めない名演奏といえます。 ~③ ワーデル・グレイ~  ■ 「Wardell Gray」 ■ 「Wardell Gray」 ワーデル・グレイの、自由なアドリブ・ソロは、ライブでのジャムセッションに、 良いものがあるのですが、大聴衆を前にしての、コンサートものは、あまり好きではありません。 録音状態の悪さ、全体として、プレイヤーが、ハイになって、 音をはずしたり、調子に乗りすぎ、気分を害する場合が多いのです。 特に、トランペット・プレイヤーに、その傾向が顕著です。 ワーデル・グレイのサックスは、どのような状況でも、メロディ・スィング感・音色など、 見事で心地よいだけに、残念です。 ▼ 1948年: 「Jazz West Coast Live Hollywood Jazz」 ・ 「What Is This Thing Called Love」 「Back Breaker」 まともな演奏ではない、聴くに堪えないライヴです。 ▼ 1948年: 「Way Out」 ロス・アンジェルスでのライブです。 「Blue Lou」 「Sweet Georgia Brown」 「Just You, Just Me」 「One O'clock Jump」 グレイの、自由奔放なアドリブによる、スィングするソロが楽しめます。 ピアニストは、エロール・ガーナーが参加していますが、 「Tenderly」で、きらびやかな、ピアノ・ソロを披露しています。 ライブものとしては、良い出来といえるのでしょうが、私にとっては、チョッと物足らないアルバムです。 ※ ジャンルが違うのですが、1958年:「Newport 1958 Mahalia Jackson」: ゴスペル・シンガーのマヘリア・ジャクソンが、ニューポートの、ジャズ・フェスティバルでおこなった、 ステージ・ライブ。これだけは、興奮がダイレクトに伝わってきて、ライブのよさを感じさせる、 数少ないお気に入りです。 「I'm On My Way」 「It Don't Cost Very Much」 「Didn't It Rain」 「He's Got The Whole World In His Hands」 等、 ブルースとは違って、希望と自信に満ちた歌、マヘリア・ジャクソンの歌唱力の魅力に満ちています。 ジャズのルーツとしての、ブルースやゴスペルには、興味のある曲や、プレイヤーが数多くいて、 アメリカ音楽の奥の深さを感じます。 ▽ 1946年: 「One For Prez」 ・「The Man I Love」 「Dell's Bells=WHat Is This Thig Called Love」 「One For Prez=How High The Moon」 ビ・バップの場合、このように、もと歌の、コード進行を使って、アドリブをする手法が多いのですが、 ここでも、グレイは、柔らかく、歌心一杯のソロを聴かせてくれます。 ▽ 1950年: 「An Evening At Home With The Bird」 ・「There's A Small Hotel」 チャーリー・パーカーとのライブ共演ですが、ここでの、グレイは、いきなりソロを始めて、 6分間ほどにわたって、リラックスしたアドリブを聴かせてくれます。 自由なフレージングと、スィンギーなプレイは、彼の独壇場です。 パーカーは、最後の1分位の、ソロをとるだけです。 もっとも、2曲目の 「These Foolish Things」 では、パーカーのくつろいだ、スロー・バラッドが聴けますが…。 録音状態も、リスナーの感じもあまり良いものではなく、当時の、アーティストの置かれていた社会的地位が、 うかがえるライブです。 ▽ 1952年: 「Memorial,Vol.2」 ・「Sweet And Lovely」 「Lover Man」 この2曲は、くつろぎに満ちた、非凡なアドリヴを楽しむ事が出来ます。 彼は、全盛期が短く、ハード・バップ以前に亡くなってしまったので、バラッド曲の中からの、 好みが多くなってしまいます。 一番気に入ったCDで、常に手元に置いてあるのは、 ▽ 1948年~1950年:「Light Gray」 これは、大変なお徳用CDで、全部で、24曲もあり、内容も、典型的なバップものから、 スタンダード曲まで、はばひろく、充実しています。 ・1949年: 「Light Gray」 「The Toop」 「Stoned」「Matter And Mind」 アル・ヘイグ(P)、クライド・ロンバルディ(B)、タイニイ・カーン(Ds)。 軽快なスィング感が、グレイの巧みなサックスで、表現されていて、気持ちの良い曲です。 ・1949年:「It's The Talk Of The Town」 アル・ヘイグ(P)、ジミー・レイニー(G)などのバックで、グレイの、ゆったりした、バラッドが楽しめます。 ・ 1949年:♪ 「Easy Living」 「Sweet Lorraine」 これもピアノは、アル・ヘイグで、きれいなピアノ・ソロも聴かせますが、この2曲は、 グレイの最高のバラッド・プレイだと思いますし、私の、最も好きな曲です。 アル・ヘイグは、バド・パウエルと並んで、最高のバップ・ピアニストだそうですが、 アル・ヘイグのどこが良いのかわからず、アレン・イーガーや、スタン・ゲッツの時のピアノを聴いても、 ちっとも良いとは思いません。 ・1950年:「A Sinner Kissed An Angel」 「Blue Gray」 「Grayhound」 「Treadin'」 あまり聴いた事のないメンバーとのセッションですが、リラックスしたスィンギーな、 サックスソロを堪能できます。 1枚のCDに、これだけのバリエーションは、彼のアルバムが少ないだけに、うれしい限りです。  ■ 「現金に手を出すな」 : 1954 ■ 「現金に手を出すな」 : 1954▽ 1950/52年: 「How High The Moon」 主に、Count Basie & His Sextet でのコンピレーション・アルバムで、13曲入ったCDですが、 アルバムの完成度に乏しい感じです。 ・「One O'clock Jump」 「Bass Conversation」 「Basie Boogie」 「I Cried For You」 1950年のこの録音が最も素晴らしく、クラーク・テリーのトランペット、バディ・デフランコのクラリネットも 冴え渡っています。もちろん、ベーシーの超人的なピアノ・ソロ、ワーデル・グレイのリラックスしたテナーも最高です。 「I Cried For You」 は、ヘレン・ヒュームズのヴォーカルも溌剌としています。 しかし、他のナンバーは、あまりにも録音状態が悪すぎてガッカリさせられます。 ・「How High The Moon」 アルバム・タイトルのナンバーで、バードランドのライブですが、ベーシーらしいスィングするリズム感に乏しく、 あまり上等な演奏ではありません。ワーデル・グレイのソロが唯一聴き所といった内容です。 ビッグ・バンドを手放したこの時期、カウント・ベーシーの辛い心情が伝わってくるような気がします。 ・「Out Of Nowhere」 16分以上のジャム・セッションが、なぜか最後に挿入されています。 チェット・ベーカーのトランペット、ソニー・クリスのアルト・サックスなど、本来なら楽しみなところですが、 カウント・ベーシーとは全く関係ない、ビ・バップセッションなのです。どのような状況でも、ワーデル・グレイのサックスは、 はずれが無いというのが、せめてもの救いです。 私は、最初の4曲が素晴らしいので、それだけで満足していますが、全体としてはイマイチのアルバムです。 所詮、クラーク・テリーのトランペットがメインのベーシー・バンドでは、とても納得できないところです。 ※ ワーデル・グレイとデクスター・ゴードンやソニー・スティットとジーン・アモンズなどの、テナー・バトルは、有名で、 一般的に、テナー・サックスのファンとしては、たまらないのかもしれませんが、私は好みません。 楽器の中でも、特にテナー・サックスは、上品と下品の境が、微妙な楽器です。白人のサックス・プレイヤーは、上品ですが、 ファンキーさが無いだけ、物足りませんし、ファンキーがすぎる、黒人プレイヤーも嫌らしいといった具合です。  ■ 「Benny Goodman & Wardell Gray」 ■ 「Benny Goodman & Wardell Gray」※ ワーデル・グレイは、レスター・ヤングを出発点に、スィング・ジャズの重要な、プレイヤーとして、ベニー・グッドマン、 カウント・ベーシーを支え、数々の名演奏を記録しています。 バップ・ナンバーを演奏していてさえ、自在なフレージングと、天性のスウィング感が、 ビ・バップの枠を超えていたのですから、せめて、あと数年活躍していたら、私好みのハード・バップ・ナンバーを 沢山残してくれたはずで、本当に残念です。 ワーデル・グレイと、そっくりな境遇で、私にとって、惜しまれるアーティストとして、 ギタリストのチャーリー・クリスチャンがいます。カウント・ベーシー、ベニー・グッドマン楽団での、あまりにも短いキャリアは、 ジャズの世界にとっても、大きな損失に違いありません。 三人の中では、ワーデル・グレイに、一番、人間的な魅力を感じています。 いい加減とでも言いたくなる、尽きる事のないアドリブ・プレイや、レイジーで、心地よいスィング感は、 天性のジャズ・プレイヤーである事を証明し、やや遊び人的な、雰囲気をもつ風貌は、丁度、シナトラに共通する、 ダンディズムを感じさせます。(この、勝手な想い入れ が出来るところに、音楽の魅力があります。) 私が、音楽に一番期待する “くつろぎ” をワーデル・グレイのテナー・サックスは、与えてくれるのです。 テナー・サックスの音を聴き比べたくて、いつのまにか、沢山のサックス・プレイヤーの、CDが集まってしまいました。 二度と聞きたくないもの、時折聴いているものと、様々です。 その他の、サックス・プレイヤーについては、魅力ある曲と共に、ページを変えて、続けたいと思います。 次のページへ 目次へ ホームへ |