〜 ディキシーランド・ジャズ (オールド・ジャズ・プレイヤー)〜 ♪♪♪ サッチモ、 シドニー・ベシェ、 エディ・コンドン、 ボビー・ハケット、 ビックス&トラム。  ■ 「The Great Race」 : 1965 ■ 「The Great Race」 : 1965「20世紀初頭のアメリカ」 というと、 不思議なことにすぐ頭に浮かぶのがこの映画のことです。 ニューヨーク〜パリ間の自動車レースというテーマでしたが、 これ以上楽しい喜劇映画は観た記憶がありません。 主演のトニー・カーティスは白い衣装で、時々キラッと光る白い歯が象徴的。 ライバル役のジャック・レモンは全身黒装束という解りやすさ。彼の助手役のピーター・フォークの 忠実で姑息な演技。トニー・カーティスの彼女役:ナタリー・ウッドのきわどいお色気。 全編爆笑の仕掛けが満載で、お金をふんだんに使ったハリウッド映画の典型でした。 ☆ お城の中で、トニー・カーティスが悪者とフェンシングで決闘する、手に汗握るカッコいいシーンが、 最近観た 「007 Die Another Day」 の中で、そっくりパクられているのには驚きました。 007も最早、イアン・フレミングの原作ではなく、ストーリーにも行き詰まってしまったのでしょうが、 逆に、40年近く経っても色あせない 「The Great Race」 の素晴らしさを再認識した思いです。 上質な喜劇にふさわしい、ムードたっぷりのヘンリー・マンシーニのテーマ音楽も忘れられません。 Great Race が開催された1908年(T型フォード完成)頃のニューヨーク・ハーレムは、 まだ白人の住宅地で、音楽もクラシックや、オーケストラ中心で、西洋音楽の影響を受けて、 ラグタイムなどが盛んになった時期です。 その後、ハーレムに黒人が住むようになり、またキャバレーなども出来て、 独自のスタイルとしてハーレム・ジャズが発展していくのです。 デューク・エリントンやキャブ・キャロウェイ楽団が有名ですが、 私は、シカゴ、カンザスなどのジャズに比べてハーレム・ジャズは苦手です。 複雑なアレンジやアンサンブルも原因ですが、ボードヴィル・ショウなど、 何となく白人へ媚びる姿勢が感じられるのです。 (観賞するのが白人ということで仕方なかったのかもしれませんが、 あそこまで笑顔を振りまくことはないのに…と 昔の映像を見るにつけ感じるところで、ファッツ・ウォーラーなどにも同じ印象を受けます。)  ■ 「Harlem N.Y.」 音楽的には、単純なメロディ、キチッとしたリズム、 軽快なスィング感など、 私の好みは決まっています。 また、生粋のニューヨークっ子のベニー・カーターなどは 文句無く好きですから、結局、私のミュージシャン評価は、 えらそうな事を言っても、個人的好き嫌いに基づいているだけということになります。 ☆ 「The Great Race」 は当時のハイソな白人中心社会を、 面白おかしく表現した映画として最高なのですが、 この映画は、それより前に見た 「八十日間世界一周」 を参考につくられたものという印象を 当時抱いていました。デヴィット・ニーヴンとシャーリー・マクレーンの主演で、 気球による世界一周という、ジュール・ヴェルヌ小説の映画化でしたが、 主題曲 「Around The World」 は、すっかりスタンダードになっています。 私は、ヴィクター・ヤング・オーケストラものより、フランク・シナトラのヴォーカルが印象に残っています。 …話が違う方向にいきそうなのでここらへんにします。 …………… ハーレム・ジャズなどは成人してから知った音楽ですが、 子供の頃聴いた様々なスタイルのアメリカ音楽の中で、皆が勝手に演奏しているのに、 全体として、心地よいハーモニーを生み出している事が不思議で、 とても魅力的に感じたのが、ディキシー音楽でした。 スィング・ジャズの統制の取れたアンサンブルと違って、かなり自由な音楽だなあ、と感じたものでした。 このジャンルの音楽は、ニューオリンズ、シカゴ・サウスサイド、シカゴ・スタイル、 リバイバル、ディキシーなど等、いろんな名称があるようですが、子供の時の印象のまま、 ここではディキシーランド・ジャズということで良いと思っています。 ディキシー・ランドという言葉には、白人優位主義のニュアンスがあるとかいわれますが、 厳密な解釈は、専門家に任せたいと思います。  ■ 「Baltimore 1」 ▽ 「Dixieland And New Orleans Jazz」 ・「Original Dixieland One Step」 : The Oriiginal Dixieland Five ・「High Society」 : Jelly-Roll Morton's New Orleans Jazzmen ・「Royal Garden Blues」 : Wingy Manone And His Orchestra ・「What Is Thing Called Love」 : Sidney Bechet And His New Orleans Feet Warmers ・「West-End Blues」 : King Oliver And His Orchestra ・「Lost」 : Mezz Mezzrow And His Orchestra ・「Dixieland Stomp」 : Chubby Jackson And His Jacksonville Seven ・「Sun」 : Bix Beiderbecke With Poul Whiteman And His Orchestra ・「Jazz Me Blues」 : Bunny Berigan And HisOrchestra ・「Shirt Tail Stomp」 : Ben's Bad Boys ・「New Orleans Twist」 : Gene Gifford And His Orchestra ・「Farewell Blues」 : Henry Levine And His Dixieland Octet 昔から未だに手元にあり、ディキシーランド・ジャズを好きになった 一番の原因になったレコードです。オムニバスですが、それが良かったのでしょう。 色々なスタイルのディキシー音楽が聴けたのですから。 とも角、昔は、1枚のレコードが貴重でしたから、くりかえし聴いた覚えがあります。 ♪ 「What Is Thing Called Love」 : Sidney Bechet And His New Orleans Feet Warmers ♪ 「Jazz Me Blues」 : Bunny Berigan And HisOrchestra 中でも、この2曲は、最も気に入って、 その頃から、スロー・ブルースや、テンポの良い曲が好きでした。 内容が解らず買ったレコードですが、今考えると、すごいメンバーが揃っています。 最近、CDで探したのですが見つかりませんでした。でも、この2曲のおかげで、 シドニー・ベシェやビックス・バイダーベックのCDも聴くことになったのです。 ▽ 「ステレオによるディキシー大行進」: ビッグ・ジェブ・ドーリーのディキシーランド・バンド このLPの中に♪「St.James Infirmary」 という、マイナー・ブルースの魅力的な曲があります。 この演奏は素晴らしく、サッチモが、28年に吹き込んで有名になったと、 ライナー・ノートには書いてありますが、録音効果も優れ、ヴォーカルも無いこちらの方が、未だに好きです。 このレコードでのプレイヤーの完成度はかなりなものですが、リーダーのトランペット以外のプレイヤーは、 専属関係上記載されていません。 ディキシーのスタンダードばかりを集めた、臨場感抜群のアルバムで、学生時代酔いしれたものです。  ■ 「Original Dixieland Jazz Band」 ▽ 「Original Dixieland Jazz Band」 1917年: ・「Liverty Stable Blues」 ほか22曲。 ジャズ初めてのレコーディングという事で、好奇心から購入したCDです。 第一次世界大戦などは、歴史書でしか知りませんが、 こうした音楽を聴くと、その頃が随分身近に感じられます。 アップ・テンポの曲が多く、アンサンブルも忙しく、そして騒がしく、とてもゆったり楽しめるところまでいきません。 コルネットのニック・ラロッカがリーダーで、トロンボーン、クラリネット、ピアノ、 ドラムというのが、標準の編成ですが、当時としては、画期的な演奏だったのでしょうが、 チョッとしんどい感じです。 ・「Jazz Me Blues」 は、オーソドックスな演奏スタイルで、私の好きな曲でもあり、気に入っています。 ・「St.Louis Blues」 「Royal Garden Blues」 などお馴染みの曲も、ヴォーカルがあったりして面白いのですが、 やはり、白人のグループらしい軽い調子が特徴です。 とも角、史上初のジャズ・レコードという意味で、貴重なアルバムのようですが、 私にとっては、歴史的興味の域を出ない作品で、再び聴いてみたいというほどではありません。  ■ 「Baltimore 2」 ■ 「Baltimore 2」 ※ ルイジアナ州ニューオリンズの 赤線地帯:ストーリーヴィル。 そこで花開いたニューオリンズ・ジャズも、 第一次世界大戦参戦で出兵の為の軍港となるにおよんで、 1917年にストーリーヴィルも閉鎖され、 ミュージシャンは、新たな仕事場を目指して ミシシッピーを北上する事になる…。 世界の変化にジャズも無縁ではないことを物語っています。 沢山の音楽に接しているうちに、 アメリカ社会の歴史や文化に意外と詳しくなっている自分に驚かされます。 今では、音楽の歴史も私なりに一通りの整合性をもって理解できているような気がします。 音楽を楽しむという範囲を超える事がないので、専門的な知識ではありませんが、 特に、ブルース歌手を追っているうちに、アメリカの歴史に関心をもったような気がします。 社会背景を知ることで、子供の頃からの断片的な情報が、ようやく繋がってきたといった感じですし、 音楽の楽しみ方が増したような気がします。 ただ結果的に、愛聴盤には程遠いアルバムもいくつか買うはめになりました。 ルイ・アーム・ストロング (ジャズの第一人者)  ■ 「Louis Armstrong:The Hot Five」 ディキシーランド・ジャズの一番の魅力は、 トランペット、トロンボーン、クラリネットによる、 アンサンブルのハーモニーで、あまりソロ・プレイを意識した事が ないというのが、少年時代の印象でした。 また、50年代以降、リアル・タイムで聴いていたルイが、偉大なアーティストという感じもしませんでした。 成長とともに、ジャズの歴史で、いつも中心にいたのはトランペット(コルネット)であり、 今日アドリブによるソロ・プレイというジャズの形をつくったのが、 ルイ・アームストロングである事を知ったのです。 昔からお馴染みのわりには、彼のヴォーカルをあまり好まず、 トランペットをあまり好きではない私でしたが、興味本位で、何枚かの彼のCDを聴くことになりました。 ▽ 「The Best Of Louis Armstrong : The Hot Five And Hot Seven Recordings」 ・「Heebie Jeebies」 初めてスキャットを使った曲として有名で、ジャズ史における貴重な記録と言えるのでしょう。 ・「Muskrat Ramble」 共演のキッド・オリーの作曲で、スタンダードとしてお馴染みです。 ルイの演奏のなかでも、素直に演奏しているという点で魅力があります。 ・「King Of The Zulus」 ルイの奥さんだったリル・アームストロングのヴォーカルと書いてありますが、 変な嬌声が聞こえるだけで歌らしいものはありません。 ・「Jazz Lips」 スィンギーなアンサンブルですが、それだけといった感じです。 ・「Willie The Weeper」 7人になって演奏に厚みが感じられます。全員のソロを聴けるのが当時は斬新だったはずです。 ・「Wild Man Blues」 スロー・ブルースでのルイのコルネットは、さすがに高らかに響き渡るといった感じです。 ジョニー・ドッズのクラリネットも負けずメロディアスで魅力のあるナンバーです。 ・「Alligator Crawl」 これもスロー・ブルースですが、チューバがノスタルジーを感じさせる音色です。 珍しくバンジョーの短いソロも聴けて、当時の楽器の構成がしのばれます。 ・「Potato Head Blues」 コルネット、クラリネットのソロのフレージングは見事なものがあります。 アンサンブルとソロのハーモニーも心地よい感じです。 ・「Weary Blues」 やや、アップ・テンポの曲で、クラリネット、トロンボーン、コルネットのソロもリズミカルです。 ・「Ory's Creole Trombone」 キッド・オリーの野太いトロンボーンがルイの高い音域のコルネットと良くハモッて、 流れるような演奏が聴けます。 ・「Struttin' With Some Barbecue」 こういう聴き慣れたナンバーは安心していられます。バンジョーの歯切れの良いリズムに、 それぞれのソロが軽快です。 ♪ 「West End Blues」 あまりにも有名な演奏です。スローなリズムの中でけだるい感じのソロ、 そしてルイのスキャットが続き、アール・ハインズのピアノ、ルイの美しいコルネットと文句無しの名演です。 優れた音楽は、時代を超えて聴く人に感動を与える、という好例です。 ・「Squeeze Me」 バンジョーのリズムの上を心地よさそうなコルネットの演奏があり、続いて、 バック・コーラスを率いて、ルイのスキャット、最後はコルネットのメロディと彼の得意のパターンです。 ・「Basin Street Blues」 賑やかな演奏でお馴染みの曲ですが、ここでは、落ち着いた演奏に終始しています。 出来ればスキャットが無しで、コルネットのソロを聴きたかったところです。 ・「Beau Koo Jack」 馴染みのない曲ですが、アップ・テンポのアンサンブルと、良く歌うコルネットが軽快です。 ♪ 「Muggles」 アール・ハインズのきらびやかなピアノ、フレッド・ロビンソンのトロンボーン、 ジミー・ストロングのクラリネット、そしてルイのコルネットと十分なソロを聴かせてくれます。 ♪ 「St. James Infirmary」 昔から、とても気に入っていた曲で、これが本家です。 ルイのヴォーカルで、こんなに淋しい内容の曲だと始めて知りましたが、 できればこれも歌無しで聴きたかったところです。 最後のアンサンブルなど素晴らしいだけに残念です。 ・「Tight Like This」 録音状態のせいで、ピアノのパートのところで音が小さくなり、インパクトにかける嫌いがあります。 ジャズの最初にして、最高の演奏が聴けるということで、このアルバムは有名です。 ホット・ファイブ、ホット・セブン時代のルイ・アームストロングの、 スキャット、アドリブ・プレイはジャズの原点と言われています。 様々な演奏を聴いてしまった現在、特別感動するアルバムではありませんが、 アンサンブルが主体のそれまでのスタイルを変えてしまったこれらの演奏は、 当時のミュージシャンや、リスナーに相当なショックを与えただろうと想像できます。 ■ 「Baltimore 3」 ▽ 「Louis' Jazz / Jazz Story」 ・「Dippermouth Blues」 いかにもニューオリンズ・ジャズと思わせるスタイルです。 当時シカゴを席巻した演奏でしょうが、時代を感じさせます。 ・「Working Man's Blues」 キング・オリバーとルイの コルネットを主体としたオーソドックスなアンサンブルで、 心地よいスロー・ブルースの演奏です。 ・「Tears」 ややテンポが速く、小刻みなリズムが、耳に小うるさく響きます。 ♪ 「Camp Meeting Blues」 これぐらいスローだと、リズムが逆に心地よい感じです。 コルネット、クラリネットのソロもあって、メロディアスなナンバーです。 ・「New Orleans Stomp」 美しいメロディなのにやはりバンジョーとドラムのリズムがチョッとうるさく興味を削いでいます。 ここまでがキング・オリバー・バンドでの演奏です。さすがに古さを感じます。 ・「Everybody Loves My Baby」 クラレンス・ウイリアムス・ブルー・ファイブでの演奏で、 エヴァ・テイラーのヴォーカルものですが、スィンギーで斬新な感じがします。 ♪ 「St. Louis Blues」 ブルース・シンガーのベッシー・スミスとの有名な競演です。 ゆったりしたテンポを情感込めて歌うベッシーに寄り添うように、ルイのコルネットが優しく歌います。 彼のクリエイターとしての力を見る思いです。オリジナル・バンドを作る前の演奏です。 ・「My Heart」 ホット・ファイブでの曲です。アンサンブルが主体ですが、自由に歌うルイのコルネットは、 音色もフレージングも際立っています。 ・「Yes! I'm In The Barrell」 ルイとジョニー・ドッズのソロが聴けます。 ・「The Last Time」 チョッとモダンな感じの曲です。ルイのヴォーカルの後にキッド・オリーのソロも聴けます。 ・「Got No Blues」 コルネットの他に、バンジョー、クラリネット、トロンボーンのソロとテーマのアンサンブルと、 その後のジャズのフォームが出来上がっています。 ・「Weather Bird」 珍しいルイとアール・ハインズの演奏です。アール・ハインズはルイから学んで、 ピアノ・スタイルを確立したといわれていますが、改めてルイ・アームストロングの ジャズにおける影響力を感じる演奏です。 残りの曲は、前のCDとダブっていますので省略しますが、 20年代のルイのトランペットは、後のものとは違い、かなり溌剌としていて勢いを感じます。 50年代からリアル・タイムで聴いていた彼のヴォーカルですが、 実は当初からやっていたとは知りませんでした。 ナット・キング・コールのヴォーカルを大好きな私ですが、ルイのヴォーカルが素晴らしい と言われてもピンときません。これは好みの問題ですから仕方ありません。  ■ 「 The Complete Town Hall Concert」 ▽ 「The Complete Town Hall Concert」: 1947 Louis Armstrong (tp,vo) Bobby Hackett (tp) Jack Teagarden (tb,vo) Peanuts Hucko (cl,ts) Dick Cary (p) Bob Haggart (b) Sidney Catlett (d) George Wettling (d) ・「Introduction By Fred Robbins」 「Cornet Shop Suey」 司会者の案内から聴衆の歓声を受けて、いきなりルイのトランペット・ソロが始まります。 ハイ・トーンのブリリアントな音色は好きな人にはたまらないだろうと思わせる演奏で、 メロディも綺麗です。ディック・キャリーのピアノも良く弾んでいます。 ・「Our Monday Date」 独特のダミ声でのヴォーカルを、ミディアム・テンポのリズムにのって、気持ち良さそうに歌い、 ピアノが上品なスィングを演出します。 ・「Dear Old Southland」 スロー・バラッドをヴィブラートを効かせてじっくり吹いています。マイナーなメロディには 魅力があり、彼の情感豊な表現は説得力があります。 トランペットの勇ましさと、淋しい音色が特徴です。 ・「Big Butter And Fgg Man」 曲目を間違ったらしく途中でルイのセリフが入り、違った展開を見せます。 ヴォーカルも苦笑したりして、聴いているだけでは面白くありません。 他のメンバーが洗練された演奏をしているだけにもう少し完成度が欲しいところです。 ・「Tiger Rag」 スタンダードで、アンサンブルの妙が楽しめます。 ボビー・ハケットとピーナッツ・ハッコーの音色は洗練されていてすぐそれとわかります。 カトレットのドラムもかなり熱の入ったプレイですが、どうも彼をあまり好きになれません。 ・「Struttin' With Some Barbecue」 ハケットのスィングするトランペット、ティーガーデンのトロンボーン、 ハッコーのクラリネットも心地よくメロディアスです。 ルイのトランペットは確かにアドリブも、プレイもすごいとは思いますが、 チョッとハーモニーを欠く感じです。 ♪ 「Sweethearts On Parade」 豊な叙情表現で、落ち着いたプレイ、ヴォーカルが楽しめます。 ティー・ガーデンのトロンボーンとルイのヴォーカルは良い組み合わせで、くつろぎを感じます。 ・「Saint Lous Blues」 お馴染みの曲を軽快に演奏しています。 ノン・ヴィブラートのハケット、ヴィブラートを効かせたルイのトランペットと、 アンサンブルの中でも微妙に違います。 名手達の好き勝手なプレイが、高度なハーモニーを生んでいます。 ♪ 「Pennies From Heaven」 ルイのヴォーカルに、私の好きなハケットの、 強力なサポートが実に良く効果を上げています。 続くティ・ガーデンの男性的な豊な音色も魅力一杯です。 最後のルイのトランペットも上品なくつろぎがあり、素晴らしいスロー・バラッドに仕上がっています。 ♪ 「On The Sunnyside Of the Street」 ハケット達のハーモニーの後、 ルイのヴォーカルですが、やや軽快に、しかしどこにも破綻が無い素晴らしい歌で、 その後沢山聴く事になる、彼のヴォーカルの中でも最高だと思います。 演奏も素晴らしい出来栄えです。 ・「I Can't Give You Anything But Love」 スィンギーなハケットのトランペットを好む私としては、そのまま続けてもらいたいのですが、 ルイのヴォーカルが入り、くだけた雰囲気に変わっていってしまいます。 それがファンには良いのでしょうが、演奏としては気に入らないところです。 ♪ 「Back O'Town Blues」 スロー・ブルースはやはり心地よいものがあります。ここでのヴォーカルは、 ハケットのトランペット、ディック・キャリーのピアノ、そして、ティーガーデンとの掛け合いなどを交えて、 楽しさとくつろぎが一緒に味わえます。ルイのトランペットも最高の音色です。 ♪ 「Ain't Misbehehavin'」 美しいメロディの曲をハケット、ハッコー、ティーガーデンが、ルイのヴォーカルや、 トランペット・ソロを、見事にスィンギーにサポートしています。 ディキシーとスィングの中間といった感じの演奏です。 ・「Rockin' Chair」 ティーガーデンとルイがそれぞれソロをとり、お互いにチャチを入れた感じが楽しいナンバーです。 子供の頃からルイの印象が、このような感じだったことを思い出させます。 ・「Muskrat Ramble」 アップ・テンポのスタンダードでアンサンブルが楽しめます。 ピアノの音が弱いのが気になりますが、さすがに全員手馴れた演奏で安心していられます。 ・「Save It, Pretty Mama」 ピアノをメインに、ルイの落ち着いたヴォーカル、トロンボーンが聴けます。 ♪ 「Saint James Infirmary」 昔から、この淋しいブルース・ナンバーが大好きでした。 ここではティーガーデンが、なんとも味のあるヴォーカルを披露します。 ボビー・ハケットのミュートも絶妙です。 ・「Royal Garden Blues」 有名なナンバーです。スィンギーで、素直なアンサンブルに好感が持てます。 ディキシーのハッピーな面が良く表現されています。 ・「Do You Know What It Means To Miss New Orleans」 前曲の陽気さから一転して、ルイの豊な歌心が見事です。 メロディが綺麗で、バラッドの心地よさを味わえます。 ・「Jack Armstrong Blues」 ティーガーデンとルイの掛け合いで、軽快なナンバーですが、 チョッと録音状態が悪く残念です。 それぞれのソロ、アンサンブルも最後の盛り上がりを見せています。 ルイがビッグ・バンドから、スモール・コンボにして大成功した、記念すべきアルバムです。 ライナー・ノーツによれば、ぶつ付け本番だったらしいのですが、さすがプロと思うと同時に、 時々聴かれる音の破綻や、ハーモニーを崩す、特異な音色がやや気になります。 ハケットの丸みのある音色が好きな私としては、彼が脇役というのが気になりますが、 全体としてみると、各アーティストの質の高いプレイは、ライブ特有の楽しさ、 ジャム・セッション風な自由な雰囲気を十分感じるアルバムになっています。  ■ 「Baltimore 4」 ▽ 「Satchmo At Symphony Hall」: 1947 Louis Armstrong (tp,vo) Jack Teagarden (tb,vo) Barney Bigard (cl) Dick Cary (p) Arvell Shaw (b) Sidney Catlett (d) ・「Muskrat Ramble」 ホット・ファイブで有名ですが、 ここではメンバーのソロが次々展開され、 アーティスト紹介を兼ねていると言った感じです。 ♪ 「Black And Blue」 こういったスロー・ブルースが好きで、 リラックスしたメンバーのプレイに、心和みます。 トランペットとトロンボーンのハーモニーも見事です。 ルイのヴォーカルは20年代より円熟した味わいです。 ・「Royal Garden Blues」 これもスタンダードとしてお馴染みで、素直なアンサンブルが素晴らしい出来栄えですが、 ルイのトランペットがやや頑張りすぎの感じがします。それが、彼の持ち味なんでしょうが…。 ・「Lover」 アップ・テンポをティーガーデンのトロンボーンが確かなテクニックで聴かせます。 曲自体にあまり魅力を感じません。せわしなく変調するのはチョッと苦手です。 ♪ 「Stars Fell On Alabama」 これは、ティーガーデンの十八番で、文句なしにベスト・プレイです。 トロンボーンのもつ、ゆったりしたくつろぎ、彼のブルージーなヴォーカルは、 白人とは思えない雰囲気をもっていて大好きです。 ・「I Cried For You」 ・「Since I Fell For You」 あまり馴染みのない女性ヴォーカリストで、 ブルース・フィーリングを感じますが、どうもピンときません。 アンサンブルだったら魅力があったろうにと思えるスローで素敵な曲だけに、残念です。 ・「Tea For Two」 ・「Body And Soul」 クラリネットのバーニー・ビガードをフィーチャーしたナンバーです。 モダンなフレージングで、ディキシーという雰囲気ではありません。 チョッと技におぼれたような感があり、ベニー・グッドマンぐらい素直にやってほしかったものです。 ・「Steak Face」 ミディアム・テンポのアンサンブルが小気味良いナンバーです。 ルイの頭のてっぺんから出てくるような音は、イマイチ私の気になるところですが…。 シドニー・カトレットはややトリッキーな感じのするドラマーですが、 ここでは、長いソロを熱演しています。 ・「Mahogany Hall Stomp」 いかにもオール・スターズという感じの演奏で、 ルイのトランペットもひときわ張り切っています。 ♪ 「On The Sunny Side Of The Street」 ルイのヴォーカル、ティーガーデンのトロンボーンが、 絶妙なハーモニーで、このアルバムが人気になった原因と思われる熱演です。 ・「High Society」 スタンダードのこの曲をあまり好きではありません。 どうも運動会を思い出してしまうような、それだけ馴染み深いのですが、 せわしないところも原因の一つです。 ・「Baby, Won't You Please Come Home?」 トロンボーンもヴォーカルも心地よく、どうしてもルイより、 ティーガーデンのほうに興味が湧いてしまいます。 ・「That's My Desire」 再び、ヴェルマ・ミドルトンのヴォーカルによるスロー・バラッドです。 ルイのボーカルも含め、あまり感じるものがありません。 ・「“C” Jam Blues」 バーニー・ビガード、アーヴェル・ショウ、シドニー・カトレットの演奏はモダンです。 が、この曲は、レッド・ガーランドのほうが数段素晴らしい出来栄えです。 ・「How High The Moon」 ベースをフィチャーしたこの曲もモダンなナンバーです。 これはディキシーと呼べないスタイルで、でも折角の名曲を…といった印象です。 ・「Boff-Boff」 コールマン・ホーキンスの書いたバップ・ナンバーだそうです。全く魅力を感じません。  ■ 「Louis Armstrong」 タウン・ホール・コンサートのライブと同じ年に 演奏されたものですが、各アーティストをフィーチャーした曲を 盛り込んだり、ややモダンな香りがしたり、コンサート・ホールとは 雰囲気の違うアルバムになっています。 浮ついたところが無く、くつろげる曲が多いのが特徴です。 サッチモは、子供の頃観た、ミュージシャンの伝記映画に必ず顔を出していて、 顔を知っているアーティストとしては、一番最初のミュージシャンだと思います。 それ以来、沢山の曲を聴いてきました。愛想よい顔と、だみ声の歌が印象的で、 何枚かのレコードが家にありましたが、振り返って、あまり印象に残っているアルバムがありません。 彼はあまりにも身近なアーティストでしたし、親善大使的な顔ばかりが記憶にあって、 ジャズのクリエーターとして最高の人なんだと知っても、特別な感慨が湧いてこないのです。 最近は、スムーズで、音色の好きなボビー・ハケットのトランペットを聴くことのほうが多いのですが、 ルイ・アームストロングが偉大なジャズのクリエーターであったことは十分理解できた感じです。 シドニー・ベシェ (孤高のアーティスト)  ■ 「Sidney Bechet」 なんと言っても、子供の頃聴いた、「Petite Fleur」 と 「What Is Thing Called Love」 が、忘れがたく、 CDを探した結果、彼の他の素晴らしい作品も聴くことになりました。 聴き間違えようの無い、ソプラノ・サックスという珍しい楽器による、毒気を帯びたヴァイブレーションは、 正にブルースそのものです。 ニューオリンズに生まれ、サッチモに嫌がれるほどの響き渡る音色と、クリエイティビティをもちながら、 人生の大半を海外で過ごした孤高のアーティスト=シドニー・ベシェ。想い出の曲から出発して、 今ではディキシーといえばサッチモではなく、シドニー・ベシェとエディ・コンドンということになっています。 ▽ 「The Definitive Sidney Bechet」 ・「Wild Cat Blues」 1923年、クラレンス・ウイリアムス・クインテットでの演奏という年代ものです。 当然アンサンブルですが、綺麗なハーモニーを聴かせてくれます。 ・「Texas Moaner Blues」 サッチモと共演しています。メロディもきれいなスロー・ブルースです。 サッチモのお株を奪う、ベシェのソロが聴けます。 ・「Mandy, Make Up Your Mind」 こちらはサッチモのコルネットが先行しますが 、馴染みのない女性ヴォーカルも魅力無く、かなり古さを感じさせる出来栄えです。 ・「I'm A Little Blackbird」 こちらは、サッチモとベシェのサックスが心地よいアンサンブルを成していますが 、どうもヴォーカルが邪魔といったところです。 ここまでがクラレンス・ウイリアムスのブルー・ファイブでの演奏です。 ・「The Basement Blues」 「Shag」 ヴォーカルが入るとどうも苦手です。折角のベシェのサックスの好演も、 曲としての魅力に欠けてしまいます。 ・「Polka Dot Stomp」 「Okey-Doke」 「Characteristic Blues」 「Dear Old Southland」 自由に演奏するベシェのサックスは聴けますが、その他心打つものはありません。 ・「Blackstick」 「Viper Mag」 メロディがきれいでベシェのソロも格調高いものがあります。 当時かなりモダンな感覚だったと思いますが、もの足りません。 ノーブル・シスルのバンド・スタイルが気に入りません。 ・「Chant In The Night」 ベシェがニューオリンズ生まれでありながら、かなりモダンなセンスをもっていた事は 良くわかりますが、ここら辺の音楽は苦手です。 ・「Jungle Drums」 ドラムのズティ・シングルトンとの共作ですが、たいしたものではありません。 ・「Summertime」 39年のテディ・バンのギター共演もあって、ブルー・ノートでの、超有名な演奏です。 哀愁に満ちた音色とアコースティック・ギターのハーモニーは、独創的で魅力があります。 でも、やや淋しさが過ぎるようでもあります。 ♪ 「Sweet Lorraine」 マグシー・スパニアのコルネットとの見事なアンサンブルです。ゆったりとしたリズム、 シャレたソロ・ワークと、40年の録音としてはかなり上品な作品で、私としては、こちらの方が好きです。 ギターの規則正しいリズムの上を、コルネットとソプラノ・サックスが気持ちよく踊っている感じです。 ・「Shake It And Break It」 ニューオリンズ・フィート・ウォーマーズを率いて、ようやく彼のスタイルを見た気がします。 シドニー・ド・パリスのトランペットも良く、ディキシーのくつろぎがあります。 ・「Egyptian Fantasy」 題名どおりスタイルはディキシーですが、メロディが気に入りません。かったるい演奏といえます。 ♪ 「Blue Horizon」 これも有名なナンバーです。シドニー・ド・パリスとのユニゾンがユニークな印象をあたえます。 クラリネットとソプラノ・サックスの使い分けで、ブルーな雰囲気を作り出しています。 彼の豊な才能を感じさせる見事なスロー・ブルースです。 夜中にディキシーを聴く事はほとんど無いのですが、こんな曲は、寝静まった夜中が良く似合う曲です。 ・「Love For Sale」 彼の好きな曲なのかもしれません。ポップ・ナンバーを取りあげるモダンなセンスは感じられます。 カルテットの中で、ソロを吹きとおすところなど、モダン・ジャズの感覚です。 彼のマルチ・プレイヤーとしての魅力が味わえます。 初期の演奏を集めたコンピレーション・アルバムで、 多才で、モダンなセンスをもったアーティストである事が良く理解できます。 素晴らしいナンバーもありますが、40年代の演奏に、より素晴らしい演奏があるようで、このCDの内容も、 全体としてはもう一つといったところです。  ■ 「Baltimore 5」 ▽ 「Sidney Sechet Revolutionary Blues」 1941-1951 ・「At A Georgia Camp Meeting」 「Jelly Roll Blues」 心地よいディキシー音楽独特のアンサンブルと 憶えやすいメロディです。 テンポも歯切れも良い、50年の演奏です。 ・「Shim-Me-Sha Wabble」 これも特徴的なテーマと ディキシーの楽しさに満ちたナンバーです。ベシェもリズミカルでのりの良いソロを聴かせてくれます。 ・「Sister Kate」 クインテットらしい落ち着きがあり、それぞれのソロも見事です。 ディキシーの音楽としての完成度の高さを感じさせる好演です。 ・「Fidgety Feet」 どこかで聴いたような出だしですが、流れるようなリズム感が気持ちよいナンバーです。 ブルー・ノートでの曲はほとんどシャレていて最高です。 ♪ 「Groovin' The Minor」 メズ・メズロウのクラリネットとの共演です。 小さい頃、家にあったメズ・メズロウのレコードに彼の名前が、 チョッとわいせつな意味があるというようなことが書いてあった事を想い出します。 曲良し、演奏良しの見事なナンバーで、かなりのお気に入りです。 ・「I Had It But It's All Gone Now」 変な掛け声から始まりますが、ベシェの侘しげなヴァイブレーションもあって、しっとりした名演奏です。 彼のソプラノ・サックスは私のようにハマッテしまうとどうしようもない魅力に思えます。 ・「Darktown Strutter's Ball」 こういう元気の良いのがディキシーの持ち味でしょうが、あまりにも沢山の曲を聴いてきて、 最近は、スロー・テンポの落ち着いた曲のほうにどうしても興味が移ってしまいます。 ♪ 「Revolutionary Blues」 ディキシー特有のコード・チェンジが美しいミディアム・テンポの曲です。 メズロウとベシェは、あまり仲が良くなかったようなことをどこかで読みましたが、 二人のハーモニーは最高です。 ・「Out Of The Gallion」 これも二人の共演です。やや幻想的なテーマのスロー・ブルースで、 情感を込めたソプラノ・サックスは他の楽器には無い独特の哀愁が漂います。 ベシェの独壇場といったところでしょう。 ・「Changes Made」 このアルバムでは一番新しい51年の作品です。 ディキシーランド・ジャズの典型といった演奏振りです。 当然ニューオリンズ出身の彼としてはお手の物といったこなれたテクニックを聴かせてくれます。 子供の頃はこのアンサンブルが不思議だったものです。 ・「Old Stack O'lee Blues」 「Blame It On The Blues」 しっとりとしたベシェのサックス、 アルバート・ニコラスのクラリネットも美しい音色です。品の良いオールド・ジャズの香りです。 ・「Blue Horizon」 違うアルバムでも聴けます。ソプラノ・サックスの特徴を最大限生かしたベシェの曲です。 ・「Laura」 ポップ・ナンバーを正に切々と歌い上げるベシェのサックスは歌以上の効果をあげています。 ・「Love For Sale」 違うアルバムでも聴けます。スローな曲では彼の表現が最大に効果を上げます。 このいやらしいくらいのヴァイブレーションが毒薬なのです。たまりません。 ・「Mood Indigo」 あまり好きではありません。曲自体が好きではないからです。 ・「Rose Room」 「OH, Lady Be Good」 チョイと気に入りません。スィング感に流されてしまって、ベシェの良さが出ていません。 ♪ 「What Is This Thing Called Love?」 41年ニューオリンズ・フィートウォーマーズの録音の中では、 というよりこのアルバム中この曲が一番好きです。 私の音楽の歴史の中でも5本の指に入る想い出の曲ですから仕方ありません。 それにしてもチャーリー・シェーバースのソロは見事ですし、ベシェの哀愁に満ちたサックスは最高です。 ・「St. Louis Blues」 あまりにも有名なスタンダードで、アレンジもやや凝った嫌いがあります。 ベシェのアドリブも好きにやっている感じです。この曲は素直な表現のほうが好感が持てます。 チョッとモダンな感覚過ぎるといったところです。 ・「Bugle Call Rag / Ole Miss Blues」 アルバム最後にアップ・テンポで、素晴らしいスィングを聴かせてくれます。 まあ、ベニー・グッドマンとは違った解釈ですが、心地よいスィングは、音楽の最も大切な要素なのです。 このアルバムは、シドニー・ベシェの最高の時期の音楽を記録したものとして気に入っています。 オールド・ナンバーからポップ・ナンバー(今では、すっかりスタンダード・ナンバー)まで、 スタイルを超えて、一貫して目一杯頑張る、ベシェのソプラノ・サックスには魅力があります。 特に、このアルバムには音楽的な調和が良くとれた作品が多いように思います。  ■ 「Hawaii 1」 ▽ 「Petite Fleur / Sidney Bechet」 ♪ 「Petite Fleur」 何度聴いても、 いつ聴いても昔がよみがえってきます。 哀愁を帯びた単純なメロディは、不思議な音色と ヴァイブレーションで脳裏に焼きついて離れません。 ・「Old Black Magic」 わけの解らないセリフがグチャグチャ入って折角の曲も台無しです。 ・「Because Of You」 ラブ・バラッドを情感込めて表現するベシェのソプラノ・サックスには味があります。 ・「I Get A Kick out Of You」 これも、スタンダードですが、スモール・コンボの気軽さがあります。 トランペット、トロンボーンのアンサンブルが心地よい響きをもたらしてくれます。 ・「Blues」 ジャングル・ミュージックを思わせる変わったテーマ・リフが特徴です。 ベシェのハリのある高音を生かした、メロディックなソロも特徴的です。 ・「Limehouse Blues」 ここから5曲は、リル・アームストロングのピアノ、ズティ・シングルトンの ドラムのトリオ演奏です。この曲はチャイナ風なアレンジでチョイといただけません。 ・「Rockin' Chair」 テンポが変化し、クラシックなドラムのリズムにのってベシェのソロが冴えています。 ・「Big Butter And Egg Man」 サッチモの奥さんだったリルのヴォーカルが聴けます。 ・「My Melancholy Baby」 ベシェのソロは、滑らかですが、トリオ演奏のやや迫力不足は否めません。 ・「I Gotta Right To Sing The Blues」 ベシェのサックスの音が大きすぎるのか、マイク状態なのか、 ピアノの音色がやや弱いのが残念です。 恐らく、サッチモも嫌がったというベシェのソプラノ・サックスの 飛びぬけた迫力のせいでしょう。ややバランスを欠いた感じがします。 ・「St. Louis Blues」 7人編成のトラディショナル・ジャズが5曲続きます。 ほっとする本来のアンサンブルの魅力があります。 ♪ 「Tin Roof Blues」 こういうスロー・ブルースが大好きです。 トロンボーンのくつろいだソロ、ミュート・トランペットの侘しげなソロ、クラリネットの軽やかなソロ、 と雰囲気があります。 ベシェのソロも全体のハーモニーを生かしてなかなかのものです。 ピアノの美しいソロから、テーマにもどりますが、長い演奏を感じさせない見事な出来栄えです。 ・「The Jazz Me Blues」 私の大好きな曲です。テーマのアンサンブルに続いて、ソロが展開されますが、 やはり、ベシェのソプラノ・サックスの存在感が抜群です。よくまとまった演奏だと思います。 ・「Yes We Have No Banana」 単純なメロディだけに、自由奔放なソロが楽しめます。 厚みのあるアンサンブルもディキシーの醍醐味です。 ・「Menphis Blues」 ヴァイブレーションを十分効かせたベシェのソロに触発されて、 ピアノ、クラリネット、トランペット、トロンボーンと、ねちっこいソロをそれぞれが頑張っています。 エンディングがディキシーらしい雰囲気で盛り上げてくれます。 ・「I Only Have Eyes For You」 「The Man I Love」 「These Foolish Things」 「All Of Me」「Embracable You」 「It Don't Mean A Thing」 この6曲は、57年パリでの録音ですが、 上品なモダン・ジャズ・カルテットというのでは、ベシェの魅力は、半減です。 やはり、ディキシーらしいアンサンブルの中での圧倒的なバイブレーションを効かせた 存在感が、彼の持ち味だとお思います。 このアルバムは、全曲、晩年のパリ在住での録音です。 当然 「Petite Fleur」 だけが目当てで購入したアルバムですが、 何曲かは気に入ったものも有り、彼が、生涯自分のスタイルを通した 素晴らしい音楽人生に共感を憶えます。 サッチモと同じぐらい偉大な存在でありながら、常に自分のスタンスを守った生き方が感じ取れます。 「Petite Fleur」 はピーナツ・ハッコーとボブ・クロスビー&ボブ・キャッツが演奏して、 ヒット・チャートを賑わしたものでした。  ■ 「Hawaii 2 ▽「South Rampert Street Parade」: 36/42年 このアルバムは、スィング全盛期に 、ダンサブル・ディキシー・バンドとして 独特なスタイルを確立した、ボブ・クロスビー楽団の 軽快なディキシーランド・ジャズが楽しめます。 彼の流れを汲む、50年代の西海岸のディキシーも 明るくスィンギーなのですが、私はこれらの音楽を聴くと、 不思議と中学校時代の運動会を想いだしてしまいます。 ディキシーランド・ジャズの日本での普及の仕方は、意外とダサい感じがあったものです。 エディ・コンドン (親しみを感じるアーティスト)  ■ 「Eddie Condon」 彼のレコードを聴いて、ディキシーのカッコよさを知り、 テナー・バンジョーを買い、大学時代、彼のライブ演奏を 聴きに行った私にとっては、エディ・コンドンは、 想い出深いアーティストですし、今も彼の音楽は心地よい 安らぎをあたえてくれます。 ▽ 「Shicago Style Eddie Condon」 シカゴ・スタイル・ジャズは、ニューオリンズ出身の黒人バンドや白人バンド、 ビックスやトラムなどの音楽とも違った、独自のブルース・フィーリングとドライな感覚が 特徴と言われています。 有名なシカゴのオースティン・ハイスクール出身者や、その仲間たちのリーダーとして エディ・コンドンが優れた手腕を発揮した事は広く知られています。 このCDは、そんな価値ある記録と同時に、コンドンの初期の音楽の素晴らしさを味わえる 優れたアルバムです。 ♪ 「Sugar」 「Nobody's Sweetheart」 「There'll Be Some Changes Made」 「I've Found A New Baby」 人気歌手レッド・マッケンジーの世話で実現できた初録音。特徴的なのは、 コルネット、クラリネットにテナー・サックスというフロント・ラインと、 ピアノ、ベース(またはチューバ)、バンジョー、ドラムという強力なリズム陣です。 力強くスウィングするリズムは、チョッとカウント・ベーシーを思い起こしますし、 サックスが最初から参加していることも嬉しいところです。 シカゴ・スタイルの典型といったこの4曲は、馴染み深い曲目ということもあって特に気に入っています。 ・「Oh! Baby」 「Indiana」 カルテット演奏で、コンドン、フランク・テシュマーカー(cl) ジョー・サリバン(p) ジーン・クルーパ(ds) という構成です。クラリネット・ソロは素晴らしいのですが、 クルーパのドラムが、単調でうるさいのが気になります ・「Indiana」 ではコンドンの珍しいヴォーカルが聴けます。 写真で見る彼のイメージ通り、スタイリストらしいチョッと気取った歌い方です。 ♪ 「That's A Serious Thing」 「I'm Gonna Stomp Mr. Henry Lee」 ジャック・ティーガーデンやメズ・メズローが参加しています。 ティーガーデンのヴォーカルはこの頃(29年) からブルース・フィーリングに溢れていて、 トロンボーン・ソロも素晴らしく申し分ありません。 エディ・コンドンのバンジョーも力強く、歯切れのよさが心地良い限りです。 ・「The Minor Drag」 「Harlem Fuss」 ハーレム・ジャズの中心人物、ファッツ・ウォーラーとの共演です。 彼のクリエーターとして、またプロモーターとしての能力が優れている例として有名な演奏です。 でも、コンドンのバンジョーだけが印象的で、気に入ったナンバーではありません。。 ・「Margie」 「Oh, Peter, You're So Nice!」 「Who's Sorry Now?」 ビリー・バンクス(v)名義の録音です。 これはダメです。この歌い方は私には気味悪くて耐えられません。 ・「Madame Dynamite」 「Home Cooking」 正に、禁酒法最後の年の録音。力強いリズム、ソロ・ワークが 適度な変化をつけているけれど、アンサンブルの良さも失っていない。 シカゴ・スタイルの特徴が良く出ている2曲です。 ・「Wolverine Blues」 「Jazz Me Blues」 37年、ジョー・マーサラとシカゴアンズの演奏です。 コンドンは、バンジョーからギターに持ち替えてしまったようです。 丁度不況が終わってコンドンが、ディキシー音楽の復活をを昔のメンバーに 呼びかけた頃だと思います。 特徴あるチャッチャッといったバンジョー特有の歯切れ良い音色が消えて、コンドンの音が 遠のいてしまったのは、曲としての魅力があるだけに残念です。 ・「Love Is Just Around The Corner」 「Carnegie Jump」 38年の演奏で、このあたりから、 コンドンのオリジナル・バンドが復活したようです。 ピーウィー・ラッセル、バド・フリーマンが参加し、演奏もボビー・ハケットとすぐわかる、 よく通る、軽快なコルネット、ジェス・ステイシーのピアノが魅力です。 20年代とは違ってかなりスィングしている感じがします。 ・「Easy To Get」 「China Boy」 バド・フリーマン名義のアルバムで、 彼の心地よいテナー・サックス・ソロが聴けます 。アップ・テンポでスィングしていますが、シカゴ・スタイルの香りもします。 ・「I Ain't Goona Gibe Nobody Home Of My Jelly Roll」 「Ballin' the Jack」 ディキシーランド・ジャズの楽しさ一杯といった演奏です。 カミンスキーのトランペット、ピー・ウィー・ラッセルのクラリネットが魅力的ですし、 ジョー・ブシュキンのピアノもスィンギーです。 ・「A Good Man Is Hard To Find」 (40年) ジェス・ステイシーが、グッドマンの快い承諾で、 当日演奏予定のグッドマン楽団のほうをキャンセルして録音した曰くつきの演奏。とライナーにあります。 グッドマンもオースティン・ハイスクールの連中と腕を磨いた仲間として、興味のあるエピソードです。 落ち着いたテンポで、メロディも美しいナンバーです。 アルバムの内容もすばらしいのですが、興味あるのは時代背景です。 禁酒法時代下(20〜33年)のシカゴで、ニューオリンズのジャズは花開き、 それらの影響を受けて、白人が独自のジャズを創り上げました。 しかし大恐慌(29〜36年頃)によって、ニューヨークへ進出した有能なシカゴアンも職を失っていく。 景気が回復し、それぞれがスィング・バンドなどへ転向していく中で、 コンドンは以前のスタイルの復活へ意欲的に働きかける。 このアルバムには、当時の彼らの人生が垣間見えて、生きた歴史を見る思いです。 少し遅れてカンザスからカウント・ベーシーもニューヨークへ行く事になるのですが、 もともとジャズの発展に、稼ぎ場所としての歓楽街、そこでのギャング・酒・女は不可分だったことが くわかります。私がジャズに親しみを感じる理由でもあります。  ■ 「The Untouchable」 : Robert Stack ☆ 高校時代「どてっ腹に穴をあけろ」というギャング映画があり、 そのテレビ・シリーズ 「アンタッチャブル」 が始まりました。 「ズィー アン タッチャボー! スターリン… ロバート・スタック アズ エリオット・ネス!」 で毎週始まる、緊迫したストーリーに心躍ったものでした。 カポネは既に逮捕されていて、一番の子分、フランク・ニティが 主に活躍したのですが、この俳優が良くて。 今でも、あの苦みばしった悪顔が浮かんできます。声優は確か若山弦蔵だったと思います。 クラシック・カー、トミー・ガン、20年代の建築、インテリアなど、時代考証も確かで、 撃ちあい場面もド迫力がありました。 エリオット・ネス役のロバート・スタックは、ニヒルで物おじしない役柄がピッタリの俳優でした。 吹き替えの日下武史も良かったのかもしれません。 当時、“アンタッチャボー” という言葉は、ひびきの面白さから、友達の間でも、かなり流行ったものです。 あの白黒で見た狂乱の世界を、エディ・コンドン達が共有していた事を想像するだけでゾクゾクします。 ☆ ついでに映画通として…「どてっ腹に穴をあけろ」 と同じ年に 「連邦警察」 という映画がありました。 これは、FBIの発足当初から体制確立までの苦難の道のりを描いた回想録的な映画でしたが、 ジェイムス・スチュアートの主演で、共演がお気に入りのヴェラ・マイルズでした。 アメリカでも有名な事件の数々(KKKのことはこの映画で知りました)と同時に、 人間描写も自然で、思い出深い映画です。 翌年、ヴェラ・マイルスは、あのヒッチ・コックの 「サイコ」 に出演することになるのです。 ☆ 同じくこの頃 「暗黒の大統領カポネ」 も観たのですが、 こちらは、あまり面白くなかったことを憶えています。 但し、この映画のロッド・スタイガーが、私のカポネ像としてずっと定着していましたから、 最近観た 「アンタッチャブル」 でのロバート・デニーロのカポネに、チョッと違和感をおぼえたものでした。 現在、たまに行くライブ・ハウスですが、いつも何か物足らないものを感じます。 ジャズのバック・グラウンドをもたない人間としては、仕方ない事かもしれません。  ■ 「Hawaii 3」 ▽ 「Eddie Condon Dixieland All-Stars」 kaminsky(tp),gowans(vtb),russell(cl),freeman(ts), sullivan(p),condon(g),newcombe(b),tough(ds) ♪ 「There'll Be Some Changes Made」 「Nobody7s Sweetheart」 「Friar's Point Shuffle」 「Someday, Sweetheart」 この4曲は1939年の録音で、シカゴ・スタイルの再現セッションです。 メンバーも旧知の仲、曲目もお馴染みのものとあって、演奏もスムーズです。 当時より、各個人のソロも、アンサンブルも上品でまとまりが良くなっています。 特にバド・フリーマンのテナーが参加しているだけで、ルイの演奏にはないまろやかさが 増しているような気がして、気に入っています。 kaminsky,butterfield,hackett(tp),teagarden(tb),caceres(bs),schroeder(p),condon(g) ,haggart(b),wettling(dr) <russell(cl)-omit kaminsky,hackett-"Swonderful"> ・「When Your Lover Has Gone」 最初と中間のハケットのソロは、美しい音色・メロディが甘いムードを誘います。 ティーガーデンのトロンボーンもレイジーで心地よく、その後のバターフィールドのトランペットも良く 、曲全体を甘いかおりが漂っていて、申し分ありません。 ♪ 「Wherever There's Love」 お気に入りリー・ワイリーのスロー・バラッドです。 彼女の情感溢れる歌を邪魔しないバックのアンサンブルも、ティーガーデンのトロンボーンも甘美です。 ・「Impromptu Ensemble No. 1」 ややアップテンポのスィング・ナンバーです。 ティーガーデンのヴォーカルは、スローでもアップ・テンポでも、ブルース・フィーリングたっぷりです。 ・「'Swonderful」 アンサンブルでのスタートで、曲名を間違えたかなと思わせますが、 バターフィールドのソロ、シュローダーのピアノがスタンダード・ナンバーであることを教えてくれます。 ディキーとスィングの中間で、正にホット・ミュージックといった味わいです。 ♪ 「Someone To Watch Over Me」 ハケットのトランペットとワイリーのヴォーカルというナイスな組み合わせ。 ここでのワイリーの優しく訴えかけるような歌声はたまらない魅力です。 ティーガーデンのトロンボーン・ソロも、曲のイメージにピッタリです。 ♪ 「The Man I Love」 しっとりとしていて、やるせなげなリー・ワイリーの最高のヴォーカルです。 ハケットのトランペットも効果的で、私の大のお気に入りナンバーです。 ・「The Sheik Of Araby」 ティーガーデンのヴォーカルとトロンボーン、アンサンブル・リードのマックス・カミンスキーの トランペットがやや元気がよいのですが、全体にはチョッとだれ気味な感じがします。 ・「Somebody Loves Me」 ティーガーデンのヴォーカル、続くソロ・アーティストも手馴れた感じで安心して聴いていられます。 グループのまとまりの良さを感じる演奏です。(ここまでの8曲は1944年録音) ・「I'll Build A Stairway To Paradise」 今までとはチョッと雰囲気が変わったアンサンブルで上品さも増した感じです。 ・「My One And Only」 スロー・テンポを気持ちよく歌う、ボビー・ハケットのトランペットが実に心地よいナンバーです。 ジョー・ブシュキンのピアノも上品で、この演奏のスタイルを定義するのは困難です。 ・「Oh, Lady Be Good」 レスターで最高の曲ですが、ここでは、アップ・テンポでスィングしています。 マックス・カミンスキーのトランペットがブリリアントな音色です。 ・「Swanee」 バターフィールドの力強いトランペット・ソロが聴けます。お馴染みの曲ですが、過去に、 あまりにもオーバーなヴォーカルを何度も聴いてきたため、曲自体を嫌いになってしまいました。 (ここまでの4曲は1945年録音) ・「Farewell Blues」 これもお馴染みのディキシー・ナンバーです。ここではかなりのアップ・テンポで演奏しています。 好きな曲だけに、この曲はもう少しスローでやってほしかったところです。 ・「Improvisation For The March Of Time」 コンドンの曲ですが、演奏全体の印象は大した感動を呼びません。 ・「She's Funny That Way」 ジョー・ブシュキンのきらびやかなピアノ・ソロと ミディアム・テンポでプレイヤーのソロが続きますが、ムードたっぷりな演奏です。 ・「Stars Fell On Alabama」 バターフィールドのトランペット、ディクソンのクラリネット、 フリーマンのテナーとソロが続いて、アンサンブルで終わるという構成ですが、 これも品のあるスィング・ナンバーといった感じの演奏です。(この4曲は1946年録音)  ■ 「Lee Wiley」 ▽ 「Lee Wiley sings with Eddie Condon All-Stars 1944 & 45」 ヴォーカルのページでとり上げたので省略しますが、 コンドン一家の紅一点として、リー・ワイリーの存在が、 このグループをより品のあるジャズ・グループとして イメージされたことは疑いの無いところです。 大学4年の時、日比谷公会堂へ、エディ・コンドン・オールスターズのライブを聴きに行きました。 バック・クレイトン、ピー・ウィー・ラッセル、ディック・キャリー、バド・フリーマン、ビック・ディッケンソン、 それにジミー・ラッシングまで参加した、いわばジャンルを超越した豪華なキャストでした。 彼は、ダンディで、かなりのスタイリストであることが容姿から見てとれましたし、 期待していたとおりの素晴らしい、コンドン・ジャズを満喫したものでした。 但し、ライブで演奏された曲目を、現在全く憶えていません。 コンドンのバンジョー姿を、見事なコード奏法を見たかったのですが、 彼がそれを使わず、相当ガッカリした事だけは良く憶えています。 その後、フォーク・ソング・ブームで、5弦バンジョーがかなり流行りました。 私は、ビル・モンローなど、ブルー・グラスも好きで、 アール・スクラッグスのスリー・フィンガーによるロール・プレイなど、既にその魅力は知っていました。 しかし、テナー・バンジョーの独特の音色・奏法は、私にとっては特別なものだったのです。 ■ 「San Francisco 1」 厳密な意味でのシカゴ・スタイル・ジャズは、 ニューヨークへ活動の場が移ってから 自然消滅したといわれています。 丁度カンザス・シティ・スタイルが魅力だった カウント・ベーシー楽団が、 次第にスィング・ビッグ・バンドに変わっていったように…。 でも、コンドンやベーシーから出発した音楽も、より洗練されて現在まで継承されているのですから、 彼らの音楽界で果たした功績は不滅といえるのでしょう。 ボビー・ハケット(数少ない好きなトランペッター) 彼は、グレン・ミラー楽団の 「String Of Pearls」 で美しいソロ・プレイを残し、 ベニー・グッドマンのカーネギー・ホール・コンサートに特別出演し、 「I'm Coming Virginia」 でブリリアントな音色を聴かせ、ルイ・アームストロングが、 コンボで成功するきっかけになった、「Town Hall Concert」 で絶妙なサポートをする等、 30年代から、常に第一線で幅広い活躍をしてきた、コルネット、トランペット奏者です。 勿論、エディ・コンドン、リー・ワイリーとのコラボレーションも私にとって重要な記録です。  ■ 「Bobby Hackett」 彼の、上品で甘いトーンと自在なアドリブは、 トランペットが苦手な私の、例外的に好きなアーティストです。 そして、トロンボーン奏者のジャック・ティーガーデンも大好きで、 ここでとりあげたアルバムには、 二人の最も素晴らしい演奏が記録されています。 ▽ 「Coast Concert / Bobby Hackett & His Jazz Band」 : 1955 Bobby Hackett(tp) AbeLincoln(tb)Jack Teagarden(tb,v) Matty Matlock(cl) Don Owens(p) NappyLamare(g,bj) Phil Stephens(b,tu) Nick Fatool(ds) このアルバムは、ハケットとティーガーデンが、 西海岸のプレイヤー達との特別編成で実現したものです。 ロスのディキシーランド・ジュビリーでライブ演奏し、大好評だったことから、 3日後スタジオで録音されたものだそうです。 ジャンルを超えた上品で美しいハーモニー、ソロ・プレイの見事さ。 恐らく私のようにディキシー好きな人でなくとも、抵抗無く受け入れられる音楽だろうと思います。 ♪ 「I Want A Big Butter And Egg Man」 最初からリラックスした演奏で、このアルバムの出来栄えを予感させます。 軽快なスィング感の中に、ディキシーのアンサンブルを取り入れて、 清涼感のあるスタイルを創造しています。 ハケットのトランペット、マティ・マトロックのクラリネット、ティー・ガーデンのトロンボーンなど、 優れた個人技に支えられてハーモニーも実に見事です。 ♪ 「New Orleans」 一転して、スロー・ブルースです。 ハケットのトランペット、ティーガーデンのトロンボーンが情感を込めて歌い上げています。 ニューオリンズの哀愁を残しつつ、上質なジャズを感じます。 ゆったりしたテンポが心地よく、このアルバム一番のお気に入りです。 ・「That' A Plenty」 お馴染みのナンバーを軽快にスィングしています。 アップ・テンポのリズム陣をバックに、それぞれが高度なテクニックで、ソロ・プレイを展開します。 ベース・ソロを取り入れるなど、モダンなセンスに好感が持てます。 テーマでのディキシーらしいアンサンブルも、歯切れ良く溌剌としています。 ♪ 「Basin Street Blues」 ティーガーデンの十八番。彼のヴォーカルは白人でありながら、 品のあるブルース・フィーリングがとても気に入っていて、同じ曲を歌うルイより好きです。 ティーガーデンのトロンボーンは勿論、マティ・マトロックのクラリネット、 ボビー・ハケットの甘く透き通ったトランペットと、質の高いソロによって、 お馴染みのディキシーが上品に生まれ変わっています。 ・「Muskrat Ramble」 これもディキシーのスタンダード・ナンバーです。ミディアム・テンポで、 ハケットの優れたアドリブが、アンサンブルの中で踊っています。 ハーモニーも美しく、良く統制が取れています。 ♪ 「I Guess I'll Have To Change My Plan」 ティーガーデンのスローなトロンボーンから、 ハケットの美しいメロディへ移ります。この二人は、ルイとティーガーデンのデュエットでは、 到底聴かれない暖かさ、優しさ、上品さに満ちていて最高のコンビだと思います。 ・「Royal GardenBlues」 今までに何回聴いてきたか知れないディキシー・ナンバーですが、 ここでは、ピアノ・ソロなども織り込み、センスの良いスィング・ナンバーといった趣です。 ハケットのトランペットは、ミュートを使わなくても、頭に響くような鋭い音色ではないため、 心地よいアンサンブルの雰囲気を壊す事は決してありません。 ・「Struffin' With Some Barbecue」 同じようなテンポで、軽快なディキシー・ナンバーが続きます。 アンサンブルと各プレイヤーのソロが実によく計算されていて、曲全体のまとまりが申し分ありません。 ・「Fidgety Feet」 最後は元気の良いアップ・テンポで全員が溌剌としたプレイを展開しています。 アルバムの中では、最もディキシーランド・ジャズらしいアンサンブル主体の演奏です。 このアルバムは、ディキシーに限らず、全てのジャズ・アルバムの中でも トップ・クラスの出来栄えだと思います。 優れた音楽は、ジャンルを問わないという典型的な例です。  ■ 「Bobby Hackett & Jack Teagarden」 ▽ 「Jazz Ultimate / Bobby Hacket Jack Teagarden」 : 1957 Bobby Hackett(cor) Jack Teagarden(tb) PeanutsHucko(ts) Emie Caceres(cl,bs) Gene Schroeder(p) Billy Bauer(g)Jack Lesberg(b) Buzzy Drootin(ds) ♪ 「Indiana」 お馴染みの曲を心地よいスィング・リズムでプレイしています。 ディキシーとスィング・ジャズの中間といった上品さで好感が持てます。 ピーナッツ・ハッコーのテナー・サックス、ジーン・シュローダーのピアノが、 曲のイメージをモダンにしています。 ♪ 「On Baby」 ハケットを中心としたテーマ・アンサンブルから、カウント・ベーシーを想わせる ピアノのリズムにのせて、各プレイヤーのソロが続きます。 ミディアム・テンポの中間派ジャズといった感じです。 ・「It's Wonderful」 一転してティーガーデンのスローなトロンボーンで雰囲気が変わります。 ボビー・ハケットのブリリアントで特徴あるアドリブは、十分な情感がこもっていて、 二人の作り出す豊な音色が、くつろぎを与えてくれます。 ・「I've Fouind A New Baby」 ミュート・コルネットで始まるお馴染みの曲です。 きちんとしたリズムが心地よいナンバーです。 ・「Sunday」 テーマのハーモニーがディキシーの良さを表現しています。 それぞれのソロもスィング感に満ちていて、軽快な印象です。 ・「Baby, Won't You Please Come Home」 スローからミディアム・テンポで、トロンボーンがソロをとっています。 2本のサックスが良く歌っています。 お馴染みの曲ですが、チョッと変わったアレンジが、ジャム・セッションの雰囲気を作っています。 ・「Everybody Loves My Baby」 ディキシーらしいアップ・テンポの曲です。 トロンボーン、クラリネット、コルネット、サックスのソロも軽快で、シャレた演奏です。 ♪ 「Mama's Gone, Goodbye」 アンサンブルが美しい曲です。 リラックスしたボビー・ハケットのプレイは、ここでも健在です。 彼とジャック・ティガーデンのコンビは、豊なハーモニーとスムーズさがあり、くつろげます。 ・「Way Down Yonder In New Orleans」 レスター・ヤングの演奏で好きな曲ですが、 ディキシーらしく、速いテンポで、クラリネット・ソロを始めとして、 それぞれのソロ・プレイが印象的です。上品にまとまっている感じがします。 ・「55th And Broadway」 スロー・ブルースをトロンボーンがやるせなげな雰囲気で始めると、 ハケットが、もっと情感を込めて吹き、テナー・サックスが続きます。 このナンバーは、ディキシーではなく、完全なジャム・セッションで、 中ではティガーデンのトロンボーンが、ひときわ冴えています。 ・「'S Wonderful」 スタンダード・ナンバーをボビー・ハケットのコルネットが気持ちよく歌います。 彼の豊なアドリブを中心にして、リラックスしたジャム・セッションが楽しめます。 ディキシーをベースにした、中間派ジャズといった感じのするアルバムで、 ディキシーランド・ジャズという枠には収まりきれない自由なスタイルに好感が持てます。 「Coast Concert / Bobby Hackett & His Jazz Band」 「Jazz Ultimate / Bobby Hacket Jack Teagarden」 2枚のアルバムが、1枚のCDに収められ…、この上ない幸せといったところです。 ハケットとティーガーデンの共演は沢山ありますが、完成度から言ってもこのアルバムが一番でしょう。 (現在、30年代のアルバムを探しているところです。)  ■ 「San Francisco 2」 これと良く似たアルバムがあります。 ▽「Rampart And Vine / Rampart Street Paraders」:54年 エディ・ミラー、マティ・マトロックというボブ・クロスビー楽団時代の プレイヤーが中心のアルバムで、 上質で軽快なディキシーが楽しめます。 でも、思い入れもなく、主人公不在といった感じで心に響きません。 ・「Firehouse Five Plus Two」 の曲なども、50年代リアル・タイムで随分聴いた憶えがあります。 が、私の好みは微妙で、西海岸の音楽は聴き易いのですが、もう一つ熱中できません。 早くから、ジェリー・ロール・モートンやキッド・オリーによって、ニューオリンズ・ジャズが 根付いた場所なのですが、どうも、ブルース・フィーリングを感じないのです。 ただハッピーなだけのディキシー音楽というのでは、飽きてしまいます。 何だかんだ言って、私は、プレイヤーの思い入れや、 好き嫌いで音楽を評価しているだけですから、いい加減といえます。 ディキーランド・ジャズではないのですが、 ▽ 「Two Classic Albums from Bobby Hacket」 「Soft Lights and Bobby Hackett」 「IN A MELLOW MOOD Bobby Hackett」 この2つのアルバムがセットになったお徳用CDです。 どちらもオーケストラをバックに、彼の、まるで歌うがごとき優しくゆったりとした音色が楽しめるもので、 24曲全て聴きなじみのあるスタンダードばかりですから、安心して聴けます。 従来、トランペットを夜聴くのは抵抗があったのですが、正にメロー・ムードに溢れていて、 むしろ夜のくつろいだひとときにピッタリのアルバムです。 また、イージー・リスニング音楽をあまり聴かないほうですが、 このようなオシャレなものだったら大歓迎です。 内容的には、 「IN A MELLOW MOOD 」の方が優れていると思いますが、 カップリングの場合贅沢は言えません。 ビックス・バイダーベック&フランキー・トランバウアー (白人ジャズのクリエーター)  ■ 「Frankie Trumbauer & Bix Beiderbecke」 レスター・ヤングが憧れたフランキー・トランバウアーと、 ボビー・ハケットのアイドル:ビックス・バイダーベックの 共演が聴けるということで購入したCDです。 ビックスの名前は子供時代から知っていましたから、懐かしさもありました。 1927年〜28年の録音ですが、彼は、31年には亡くなってしまいますから、 短いながらも貴重な記録といえます。 ▽ 「Bix Beiderbecke Real Jazz Me Blues」 ・「Trumbbology」 ビックスの作曲で、憶えやすいメロディです。独創的なメロディ感覚は感じますが、 あまり好みではありません。 ・「Clarinet Marmalade」 「Ostrich Walk」 「Riverboat Shuffle」 ディキシー・スタイルで、O.D.J.B を思い起こさせます。 アンサンブルもソロも調和がとれていまが、特に素晴らしいとも感じません。 ♪ 「Singin' The Blues」 彼の最も有名な演奏です。トラムのCメロディ・サックスのクリアな中にも 情感漂う美しいメロディが楽しめます。続くビックスの流れるようなフレージングは、 ゆったりしたラングのギターのリズムにのって、実にくつろぎに満ちています。 曲の魅力、プレイヤーの魅力が一致した、アルバムでも一番のナンバーです。 ♪ 「I'm Coming Virginia」 おっとりとしたアンサンブルが魅力です。ラングのギター、 トラムのソフトで暖かいサックス・ソロ、そしてビックスのブリリアントなソロへと続きます。 音色はクリアですが豊な歌心は、ビックスの代表的な演奏として有名になったことが良く理解できます。 ♪ 「Way Down Yonder In New YOrleans」 これも聴きなれた曲で安心できます。 前曲に劣らない、ビックスの透き通ったコルネット・ソロ、ラングの心地よいギターのリズムが楽しめます。 アンサンブルはややクラシックな感じです。 ・「For No Reason At In C」 トラムのCメロディ・サックスが甘く優しいソロを奏で、 ラングのギター・ソロが続きます。 やはり、アコースティック・ギターのソロはややか細く、チョッと息苦しい感じです。 ここでは、ピアノも弾くビックスとのトリオ演奏です。 ・「Three Blind Mice」 妙なアンサンブルで、曲に魅力も無くあまり魅力を感じません。 当時の白人バンドには何かが欠けています。 ・「Blue River」 「There's A Cradie In Caroline」 シーガー・エリスというヴォーカリストが歌っています。 この頃の白人男性の歌は嫌いです。 ・「In A Mist」 ビックスの唯一のピアノ・ソロとのこと。クラシックとラグタイムのあいのこみたいで、 彼の才能は理解できますが、特別心ひかれるものはありません。 ♪ 「Wringin' And Twistin'」 ビックス、トラム、ラングのトリオ演奏です。 レスター・ヤングに影響を与えたトラムの甘く美しいメロディが心地よい響きです。 ラングのギター・ソロもこの程度なら問題なく、ビックスはピアノも弾いて多才なところを見せています。 このアルバムで聴く、トリオものは出色だと思います。 ・「Humpty Dumpty」 トラムのメロディは相変わらず優しく甘いのですが、ヴェヌーティを聴いてガッカリです。 私は基本的に、ジャズにヴァイオリンは似合わないと思っています。 ・「Krazy Kat」 「The Baltimore」 馴染みのない曲で古臭いハーモニー、ヴァイオリンとくればいかにビックスが 見事なコルネットを聴かせてくれても、好きになれません。 ・「There Ain't No Land Like Dixieland To Me」 「There's A Cradie In Caroline」 「Just An Hour Of Love」 「I'm Wonderin' Who」 アーヴィング・カウフマンという知らない歌手が歌っています。 一般的にはインストには感じない古めかさを、この頃のヴォーカルには感じます。ダメです。 ・「Three Blind Mice #1」 「Three Blind Mice #2」 スィング感が無く、曲自体に魅力が乏しいので、 プレイヤーがいくら良い演奏をしても、感動がありません。 ・「Clorinda #1」 「Clorinda #2」 「I'm More Than Satisfied #1」 「I'm More Than Satisfied #2」 ヴォーカルものは苦手です。 ・「At The Jazz Band Ball」 ディキシーには、スィング感、きちっとしたリズムがあって安心して聴けます。 アンサンブルも良く統一されています。 ♪ 「Royal Garden Blues」 お馴染みディキシー・スタンダード・ナンバーです。 やはり曲に魅力があれば、演奏も溌剌としていて、時代を超えて心に響きます。 ここでのビックスのソロは、ルイとは違ってノン・ヴィブラートで、ブリリアントな音色が魅力です。 曲のまとまりも良く聴きやすい演奏です。 ♪ 「Jazz Me Blues」 私の大好きな曲で、アルバム・タイトルにもなっているとおり、 くつろいだディキシーが楽しめます。 ビックスの歯切れの良いコルネットは見事です。アンサンブルも快調です。 ・「Goose Pimples」 アレンジがフレッチャー・ヘンダーソンだそうで、ミディアム・テンポの心地よい ディキシー・スタイルで、ボリュームのあるハーモニーと、ソロ・パートの変化が楽しめます。 ♪ 「Sorry」 いいテンポで、ビックスのコルネットも快調です。 リズムがしっかりしているので、ビックスのコルネットの上手さが良く伝わってきます。 ビックス&ヒズ・ギャングのものはスィング感があって、上質なディキシーを聴かせてくれます。 ・「Cryin' All Day」 ゆったりしたリズムの上を、トラムのサックスが優しく歌います。 ビックスのコルネットも気持ち良さそうです。 このアルバムにはトラムのオーケストラでの演奏が多いのですが、 彼とビックスを聴くとレスター・ヤングとバック・クレイトンを思い起こさせます。 惜しむらくはカウント・ベーシーと分厚いリズム陣が欲しいところです。 ・「A Good Man Is Hard To Find」 これもトラムの歌心に溢れたソロが聴けます。 ゆったりしたテンポで、ピーウイ・ラッセルのクラリネットまでは素晴らしいのですが、 ヴェヌーティのヴァイオリンが邪魔です。でも曲自身に魅力があります。 ・「Since My Best Gal Turned Me Down」 元気の良いディキシー・ナンバーです。 ビックスの澄んだ音色が印象的です 。彼の見事なフレージングは、ボビー・ハケットに受け継がれている事が解ります。 ・「Sugar」 リー・ワイリーでお馴染みの曲です。折角、トランバウアーのソロが良いのに、 ヴァイオリンが歌い、男性のデュオが歌い、さようならといったところです。折角の曲が台無しです。 ♪ 「There'll Come A Time」 アップ・テンポでの綺麗なアンサンブルが魅力です。 ジミー・ドーシーのクラリネット、ビックスのコルネットもリズミカルですが、 トラムのソロは流れるようなフレージングと、優しい音色が印象的です。 スィング感があるのですが、これに黒人のブルース・フィーリングが加われば文句なしといったところです。 ・「Jubilee」 こういった個性の無いダンス音楽風アンサンブルが、当時受けたのかもしれませんが、 馴染みのない曲ということもあって、好きになれません。 ・「Mississippi Mud」 ビング・クロスビーがビックスと掛け合いで歌っています。チョッとかすれた感じの声です。 ビックスのコルネット・ソロは、素晴らしいアドリブと音色で、魅力十分なだけに歌は邪魔でした。 小さい頃、このような歌を沢山聴いて、クロスビーを嫌いになったのです。 ・「Oh Gee!-Oh Joy!」 「Why Do I Love You?」 「Ol' Man River」 「Our Bungalow Of Dreams」 「Lila」 時代ものの男性ヴォーカルは、大嫌いなので、これらのナンバーはダメです。 折角のビックスやトラムの素晴らしいソロも、チンケな歌のおかげで台無しというところです。  ■ 「San Francisco 3」 ※ このCDを聴いて強く感じる事は、 この頃の白人音楽は、個性の無いダンス音楽風アンサンブル (シンフォニック・ジャズ)が主流で、 私が最もジャズの魅力と感じている “きちっとしたリズム” “躍動感” “ブルース感覚” が欠落しているということです。 ビックスやトラムが、豊な歌心をもった優れたアーティストであることは、 彼らのソロ・プレイによく現れています。 くつろぎに満ちた、何曲かの好きな演奏もありますが、全体の印象はディキシー以外は、スィング感が無い音楽だな、 というものです。ブルース・フィーリングは、求めても無理でしょうが。 この頃の演奏が、もう一つ物足らないのは、その後スタンダード・ナンバーになるような、優れた曲が、 20年代にはあまり無かった事も大きな原因と思われます。 ※ 彼をモデルにした 「情熱の狂奏曲」 という映画が カーク・ダグラス、ドリス・デイ主演で作られていたようです。 幼い頃で、全く記憶にありませんが、カーク・ダグラスのビックスというのはイメージしずらいところです。 もし、リバイバルがあっても、二の足を踏むことでしょう。 私は、ルイ・アームストロングよりもう少し上品で、くつろぎを与えてくれる音楽、アーティストを好みます。 例えば、ルイよりビックスの影響が強い、ボビー・ハケットの音色が好きですし、 トラムを参考にし、フォー・ビートのきちっとしたリズムの上を漂う、 レスター・ヤングのテナーがこの上なく好きです。 また、ルイの突出したソロをメインとした演奏より、エディ・コンドンの、 調和の取れたディキシー・スタイルを好みます。 そして、ルイのスィング感を、ブラス&サックスのコール&レスポンスに昇華させた、 グッドマンのスィング・アンサンブルが好きです。 しかし 「West End Blues」 等で聴くルイの音楽は、20年代、ジャズに求められる全ての要素を、 既に、彼が持ち合わせていたことを、このアルバムは思い起こさせます。 おかしなことに、このアルバムによって、ルイ・アームストロングが、 ジャズの最高のクリエーターであることを再認識した思いです。  ■ 「My Leica & Contax」 ※ 古い・新しいという捉え方で、 音楽や映画に接した事の無い私ですが、 技術力に関しては、時代を感じる事が多く、 カメラの進歩もその一つです。 携帯電話での盗み撮りが大きな問題になっていますが、高画質な映像が、 お手軽にモノにできる魅力を考えると、用途はまだまだ広がる可能性を秘めていると思います。 十数年前、商業施設の視察の為、アメリカへ行った時の事を想い出します。 撮影禁止が多い事を予想して、行く前に対応を考えていったのです。 ・既成の皮製ショルダー・バッグ、内部は型崩れ防止にダンボール張り。 バッグ正面一部を8センチ角切り取り、裏からハーフ・ミラー貼り。 キャノンA1・24ミリF2レンズ装着。ASA400フィルム。 距離は3メートル・プログラム設定。オート・ワインダー、シャッター・レリーズ取り付け…。 内側が暗いと、鏡にしか見えないハーフ・ミラーの特性を利用した優れものでした。 この装置は、我ながら見事な成果をあげました。肘でバッグを固定して、 手の中のレリーズを押すだけですから、横向きの状態で、全く気づかれず、 どこでも写真が撮れたものです。 本当は、それほど大した目的も意味も無かったのですが、自前の装置で、 堂々と盗み撮りできる快感を、存分に味わう事が出来ました。 ・露出計の無いライカに、キャノンの24ミリレンズと特製ファインダーは、 今でも、虚栄心を満たしてくれる、お気に入りの組み合わせです。 フィルムの技術も向上しているので、間違いなく写ってしまうのですが、 適度なフレアーや、独特のカラー再現性は、現在の高度なレンズ技術では難しい、 不完全さの魅力があって、写すことの楽しさを想いださせてくれます。 (レコードにこだわる、音楽マニアの気持ちかもしれません。) ズーム・レンズも取り揃えたものの、結局、24ミリと85ミリの短焦点レンズが大好きで、 マクロ・レンズとの3本以外、あまり出番が無かったものです。 今ではお手軽な、デジカメばかりですが、電池が無いと動かないものには、 基本的に愛着が湧かず、時計も手巻き、というこだわりは今でもあります。 ※ 昔の技術では不可能な表現というものも、確かに沢山ありますが、郷愁とは関係なく、 昨今の音楽や映画は、技術に頼りすぎて、心に響くものが少なくなったように感じています。 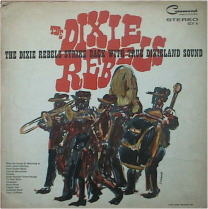  ■ 「Dixieland Jazz」 ■ 「Dixieland Jazz」ディキシーランド・ミュージックはこの辺にして、カントリー・ミュージックの想い出へ続けたいと思います。 次のページへ 目次へ ホームへ |