〜ハードボイルド小説〜 このページでは、辛い時代に夢中になって読んだ、 ハードボイルド小説の主人公の想い出を中心に、気ままに綴ってみようと思います。      「 ロス・マクドナルド/レイモンド・チャンドラー/ダシェル・ハメット/ロス・トーマス」 現在、ゆったりした雰囲気の中でしか、音楽を聴いたり、本を読まないのは、 辛い時代のなごりかもしれません。 特に社会人になりたての頃は、必死で仕事をし、勉強をして、 それでも余った空白の時間を埋めるために、さまざまな分野の本を読み漁りました。 サルトルの「存在と無」「嘔吐」「出口無し」…、どんな本だったかすら忘れましたが、 当時でさえ、本の内容を理解していたかどうかは怪しいものです。 もちろん実存主義に傾倒していたわけではありませんが、 あの頃、サルトルはかなり日本でもてはやされていました。 今振り返ってみると、無意識のうちに、生きることの意味を探していたような気はしています。 たて続けに起こった身内の不幸については、気力も、体力もありましたし、 スポーツと遊びに明け暮れていた学生時代の反動から、 むしろやる気を起こしてくれる起爆剤になりましたが、 どうにも解決できなかったのが、恋人との別れによる脱力感でした。 ふと一人になって、彼女の顔が浮かび、楽しい日々を想い出す瞬間、 身体が崩れ落ちるような、絶望的な感覚に襲われたものでした。 恐らく、最愛の人を失った人は、皆同じ気持ちになるのでしょうが…。 心なごませてくれるはずの音楽…、特にカントリー・ソングは、 楽しかった日々が蘇るのが辛く、50年代までのアーティストの曲を一人では聴けませんでした。 比較的想い出に絡まないモダン・ジャズを集中して聴いたのは、その頃の事です。 ミステリー小説で、ジョン・ル・カレや、ロス・マクドナルドが好きな理由が、 やや難解な文章のせいかな、と思っています。洋書を読んだのも同じ理由だったはずです。 集中して読まないと理解できないような書物が、当時は唯一の救いでしたから。 現在、それら全ての出来事が、懐かしく、時に甘酸っぱい青春の想い出として、 音楽や、小説を通して蘇ってくる幸せを感じています。 時の経過は、喜びも悲しみも全て、懐かしい想い出に変えてくれる、…今だから言えることです。 前置きが長くなりました。イギリスのスパイ・冒険小説と同じように、 そんな辛い時代に親しんだ本が、アメリカのハードボイルド小説でした。 私が熱中していた頃は、ダシェルハメット、レイモンド・チャンドラー、ロス・マクドナルドが、 ハードボイルド小説の、三大巨匠とか言われていたので、この三人を中心に想い出を綴ってみます.。 ロス・トーマス、マイケル・リューイン、ロバート・B・パーカー なども紙面が許せば…。 もし私が、あのような体験をしていなかったら、 果してロス・マクドナルドの小説にあれほど熱中できたか、今となってはわかりませんが、 彼の小説には、二人のものとは違った魅力を感じていました。 読書に短絡的な娯楽だけを求めていたなら、彼の作品は、きっと1〜2冊でやめていたような気がします。 それで思いつく作家にミッキー・スピレインがいます。 彼を本格的ハードボイルド作家と呼ぶことに、相当抵抗がありました。 いずれそこらへんについての、私の想い出や、こだわりを書いてみようと思っています。。 ★ ロス・マクドナルド 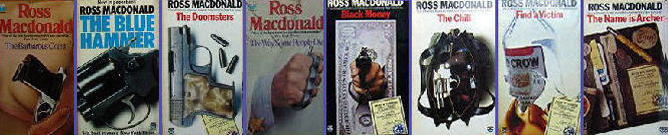 「凶悪の浜/ブルー・ハンマー/運命/人の死にゆく道/ブラック・マネー/さむけ/犠牲者は誰だ/我が名はアーチャー」 小説の主人公像というのは、読んでいるうちに何となくイメージが浮かぶものでしょうが、 私の場合は、すぐ映画俳優を思い浮かべるようです。 小説を読むより、映画:「動く標的」を先に観ましたから、 リュー・アーチャーは、文句なしにポール・ニューマンでした。 ついでながら、イメージが混乱したのは、フィリップ・マーローでした。 子供の頃観た映画では、「マルタの鷹」も「三つ数えろ」もハンフリー・ボガードが演じていました。 当時は、主人公のキャラクターを、相当タフな男としてとらえていたはずです。 ハンフリー・ボガードのイメージは、他の映画で既に出来上がっていましたから…。 後に本を読むようになって、 「大いなる眠り」の映画が、実は「三つ数えろ」だった事を知って驚きました。 「マルタの鷹」のサム・スペードは、文句なしにハンフリー・ボガードですが、 そうなると、フィリップ・マーローは誰だ、ということになります。 本の印象では、もう少し優しいキャラクターが頭に浮かびましたし、 異なった小説の主人公が、同じ俳優のイメージという事はありえませんから…。 オシャレな感じで、私の好きなケーリー・グラントかな?、と思った時期もありますが、 その後、「さらば愛しき人よ」 リメイク版の「大いなる眠り」を観て、 ロバート・ミッチャムで決まり、ということになりました。 今では、あの眠たそうな目をしたマーローということで、すっかり納得しています。 もちろん、「ロング・グッドバイ」のエリオット・グールドでは、決してありません。 本題へもどりますが、ロス・マクドナルドのリュー・アーチャー・シリーズは、全て読みました。 現在、ポケット・ミステリー・ブックと洋書しか残っていませんが、 特に初期の作品では、創元推理文庫にも随分お世話になりました。 「動く標的」「魔のプール」「人の死にゆく道」「象牙色の嘲笑」「死体置場で会おう」「犠牲者は誰だ」 「わが名はアーチャー/短編」「凶悪の浜」「運命」「ギャルトン事件」「ウィチャリー家の女」 「縞模様の霊柩車」「さむけ」「ドルの向こう側」「ブラック・マネー」「一瞬の敵」「別れの顔」 「地中の男」「眠れる美女」「ブルーハンマー」 ロス・マクドナルドの描く、子供を中心とした家庭内の悲劇、病めるアメリカ社会〜、 自分の住む世界とは、全く関係の無い出来事のように捉えて読んでいたものですが、 40年近く経って、それら全ての病を、今の日本社会が抱えている事に驚きます。 戦後ずっと、日本はアメリカを理想の国として模倣してきたのですから、当然かもしれませんが〜。  「動く標的」 ロス・マクドナルドとの出会いが、この映画でした。 まだ彼の名も知らず、小説も読んでいない頃でした。 ハーパーはある夫人から行方不明となった夫の捜索を依頼される。 ハンフリー・ボガードとおしどり夫婦と言われていた、 ローレン・バコールが、その依頼主を演じていました。 離婚でもめているハーパーの奥さんが、ジャネット・リー、 落ち目の元人気女優役で、シェリー・ウィンターズが、 途中で殺されてしまうパイロット役で、ロバート・ワグナーと、出演者も豪華、 失踪した夫が大富豪というのですから、私立探偵ものではお馴染み、豪華な設定でした。 ストーリーは省略しますが、この映画で忘れられないシーンがあります。 ハーパーが、犯人に、殺す気なら戸口に着く前に撃てと言って車を降りる。 彼はハーパーの背中に銃を向けるが、撃つことができない。 ハーパーが歩き出す時の、もういい加減にしてよ、という表情や手の仕草…、 友人に裏切られた、やるせない気持ちと、ほとほと嫌気がさしたといった、 ポール・ニューマンのラスト・シーンでのカッコイイ演技は、今でも鮮明に憶えています。 そもそも、朝、コーヒーを切らしたハーパーが、 ゴミ箱から、出がらしのコーヒーを拾っていれるオープニングからして、 なんとも粋な映画を予感させるものでしたが…。 映画での名前は、ルー・ハーパーでしたが、後に小説で、リュー・アーチャーであることを知りました。  後年、「スティング」で、 ロバート・レッドフォードが、いかさま師のプロのニューマンを頼って 家を訪れた時、いきなり手洗いの中に、氷をぶっこんで 無造作に顔を洗うシーンを観て、ふとあの映画を想いだしたものです。 彼は、チョッとシャイな表情を見せる時も魅力がありますが、 ダンディでカッコいいショットが、他の映画にも沢山あります。 ハードボイルド小説の主人公は、 同じ犯人探しでも、ポアロやホームズのように、先ず殺人事件があり、 物語の大半を、犯人のトリックを解き明かすことで、読者を楽しませるといったものとは違います。 依頼を受ける時点では、さしたる事件性を感じないものの、読者と同時進行で捜査活動を続けるうちに、 複雑に絡み合った人間関係に巻き込まれ、それらを解きほぐしていく過程で、 新たな事件が起こり、より深く事件に巻き込まれることで、やがて全貌が見えてくるといった展開ですから、 イギリスの伝統的探偵小説とは全く違った、一人称独特のスリリングなストーリーを楽しめます。 そして、全編、ハードボイルド独特の、気の効いたセリフに満ちている、というわけです。 権威も後ろ盾もない一匹狼で、しがない人生を背負った人物というのが主人公ですから、 時には突然拳銃の台尻で殴られて気絶し、その間に新たな殺人事件が進行している、 というのもお約束です。 当然、金や地位や名誉に惑わされない、自分なりの人生哲学と、強固な意志をもっているのですが…。  「The Drowning Pool/魔のプール」 「The Drowning Pool/魔のプール」このページのトップに、洋書の表紙がありますが、 手元に日本語の本が残っていないので、 恐らく創元推理文庫で読んだのだと思います。 映画名は「新・動く標的」でした。 ポール・ニューマンの素敵な奥さん、ジョアン・ウッドワードが共演していた事で、 どちらかといえば「動く標的」より気に入っているかもしれません。 雰囲気のあるアンティーク・ショップ…、店内には、ポール・ニューマン扮するハーパー、 そこへ、サングラスをかけた上品な女性が、チリンとドアの音をたて入ってきて、そっと彼に近寄る…。 記憶がおぼろですが、映画はこんなオシャレなシーンで始まったような気がしています。 その女性、実生活では奥さんのジョアン・ウッドワードで、 役柄上は、以前彼と交際をしていた間柄で、大金持ちの依頼主でもあるというわけです。 “If you didn't look at her face she was less than thirty, quick_bodied and silm as a girl〜” 「顔を見なければその女は30前に見えた。 女としてはきびきびした身のこなしで、からだもしまっている。〜」 私の映画での記憶が間違っているのか、映画が小説と違うのか確かめようもありませんが、 小説の始まりは、このように依頼人の女性:モード・スロカムが、 アーチャーの探偵事務所に、戸惑いながら訪ねてくる場面から始まっています。 夫宛に妻が不倫をしているという匿名の手紙が来たので、差出人を見つけて欲しいという依頼をして、 その場で手紙を渡しています。映画では大邸宅へ行ってから手紙を読んだはずですが〜。 まあ、映画と小説で違うのはそこだけではありませんし、私の記憶による出だしのほうが粋というものです。  この二人の映画は、「レーサー」はじめ何作か観ていましたから、 この二人の映画は、「レーサー」はじめ何作か観ていましたから、“いいなあ、夫婦でいつも仲良く…”なんて、すぐ感じたものです。 ポール・ニューマンはもちろん、ジョアン・ウッドワードの 聡明そうな顔が好きでした。 それで想い出すのは、チャールズ・ブロンソン…、 女房のジル・アイアランドとよく共演していましたが、 上品さでは雲泥の差があるというものです。 アメリカ南部の、古く悪しき因習に縛られて窒息しそうな人生をおくる、 大金持ち家族の、悲惨な末路を描いたストーリーでした。 土地に眠る、石油の利権を巡っての争いを絡め、 本筋は、娘の誕生にまつわる忌まわしい過去から現在への狂気…、マクドナルド得意の因縁話です。 ストーリーの中心人物、はねっかえりの妙に色気づいた娘役は、 後に「ワーキング・ガール」で素敵なキャリア・ウーマンぶりを発揮した、メラニー・グリフィスでした。 また、警察官で悩める父親という複雑な役を、アンソニー・フランシオサが熱演していました。 が、なんと言っても、ジョアン・ウッドワードの悲劇のヒロインの姿が忘れられません。 小説から離れた独自の映画なら、ポール・ニューマンが、全てのしがらみを断ち切って、 二人で再出発というハッピーエンドになるのに…、切ないラスト・シーンでした。 ただ、ハーパーが、水治療法のための部屋に閉じ込められ、危うく溺死しそうになるシーンで、 一緒にいた悪党の女房の、水に濡れて身体に張り付いた下着姿が、 妙にエロティックだったと感じたのは、私だけではないはずで、 ここらが、映画にしかできないエンターテインメント…観客へのサービスといえそうです。 この他には、リュー・アーチャーを題材にした映画は無かったはずですが、 彼のその後の作品は、より娯楽性に欠けるものばかりですから、 たとえ映画化しても、興行的に成功したか疑問ではあります。 この2本の映画は、上映時は相当話題になりました。 「動く標的」「魔のプール」は、映画のイメージが強く残っているせいか、 アーチャー・シリーズの中では、珍しく華やかで面白い作品として記憶されています。  「Find a Victim/犠牲者は誰だ」 Chapter 1 “He was the ghastliest hitchhiker who ever thumbed me. He rose on his knees in the ditch. His eyes were black holes in his yellow face, his mouth a bright smear of red like a clown's painted grin. The arm he raised overbalanced him. He fell forward on his face again.” “これまでも、親指をあげるヒッチハイカー に呼びとめられたものだが、 その男は見たこともないほど凄惨な姿だった。溝のなかに両膝をついて体をおこしていたのだ。 眼は黄色い顔にあいた黒 い穴だったし、口ときたら、サーカスの道化役が口紅を塗って 笑顔を作る ように、赤い色が明るくべっとりとついていた。 腕を上げたので身体の平衡を失ったのだった。もとのままに顔ごと前にのめってしまった。” まず依頼人の要請を受けて捜査を開始するというのが、いつものパターンでしたから、 いきなりショッキングなシーンから始まり、否応無しに不可解な事件に巻き込まれていくという、 彼にしては珍しい小説として、いつまでも心に残っている作品です。 サクラメントへ行く途中の道路で、銃で撃たれて瀕死の男を発見し、 救急車を呼ぶが、撃たれたトラックの運転手は病院で死亡し、 トラックと積荷が消えていた〜。 次々起こる殺人や暴力シーンは、ハードボイルド小説の定石というものの、 親子・夫婦間での複雑な心理的葛藤、悲劇的なラストの描写などから、 彼の作風が変わっていくことを予感させる作品です。  「The Chill/さむけ」 法廷の証人台を降りたところで、突然青年に 新婚旅行初日に失踪した妻を捜して欲しいと依頼されたアーチャー…、 まもなく彼女の居所はつかめたが、 夫に迷惑がかかるから戻るつもりはないという、 彼女の過去の出来事が、今でも尾をひいているらしい〜。 この作品を彼の最高傑作と言う人が多いようです。 人間の内面にある孤独、狂気といった隠れた部分を、主人公の観察によって、 鋭く描き出すという点が、それまでの作品より強く出ているかもしれません。 謎解きの面白さも、それまでの作品より優れているかもしれませんが、 消え去った愛情、しかし現実から逃れることのできない人間の弱さ…、 ストーリー全体を覆う、どんより重苦しい雰囲気のこの話を、 現代日本の社会に置き換えた時、「さむけ」を覚えるほどの現実感があるのが怖いところです。 少年時代の心の傷、親子や夫婦間における根強い不信感、病めるアメリカ…、 彼の扱う題材が一貫しているということに、凄いエネルギーを感じます。 全ての作品をここで紹介するのも意味の無いことなので、 特徴的な描写、彼についての記述などを拾い出してみました。  「ドルの向こう側」 この小説も、厳しい父親のせいで感化院に入れられた17才の少年が、 実は、養子であった事実を知り、生みの親を探すため脱走し、 その院長の依頼でアーチャーが捜索を開始、 次々と明らかになる、忌まわしい過去と現在の因縁といった、 彼の得意な分野、切ないストーリーです。 読み応えがある作品として、当時一番気に入っていました。 ロス・マクドナルドは、オイディプスに負うところが多いと解説にあります。 私はオイディプスをよく知りませんが、それに関連した記述があります。 「ドルの向こう側」の一部抜粋です。 “〜、一時間たった。 スザンナがステーキを焼いてくれ、彼女は食欲なさそうに食べていた。 二人で中庭の大理石のテイブルにつき、彼女が、 身元を探す伝説のこと、その発生をいろいろ話してくれた。 オイディプス、ハムレット、スティヴン・デダルズ。 彼女の父親がそのような科目を大学で教えていたのだ。 時間を過ごすのには役立ったが、少年に関する私の不安をやわらげることにはならなかった。 ハムレットは血なまぐさい最期をとげた。オイディプスは父親を殺し、母を妻とし、 やがて自らも盲となった。〜”  「眠れる美女」 「眠れる美女」巻末の解説で、各務三郎氏が、 彼の小説で頻繁に出現する鳥との関連で、 オイディプスについて触れています。 その中で、ロス・マクドナルドが自身の創作に開眼したのは 「ギャルトン事件」で、それが、ギリシャ悲劇、 特にソポクレスの「オイディプス王」に触発されたものであることは、 彼自身の告白にまつまでもありません。との記述があります。  「別れの顔」 「別れの顔」本文からの抜粋…、 〜私は、彼女をとらえている恐怖がしだいに理解できた。 彼女は、ニックがハロウとミセズ・トラスクの二人を殺し、 自分がその触媒の役割を果したのだと、信じているか、 そう疑っている。心の底の暗い一隅の、記憶の彼方、 意識下のどこかで、幼児であった自分が、あの通りで 自分の母親を殺したのだ、という、誤ってはいるが、 ひそかな罪の意識を感じているのだ。 この本の訳者:菊池光氏の解説で、批評家のジョン・レナードの記事が紹介され、 ロス・マクドナルドの成長期に影響を与えた事柄をリスト・アップしています。 1・三歳のとき、父が家庭を見捨てたこと。 2・係累がやたらに多いこと…彼らは皆貧乏であり、このゆえ長老教会派的、 陰鬱な雰囲気の中で彼は育てられた。 3・カナダ出身…実在を認めようとせず、ただただ働きづくめの粗野な産業社会。 4・母の“良い夢”としてのカリフォルニアへの思い出…これがあとで価値あるものとして 彼に影響を及ぼすことになる。〜〜。 初期のリュー・アーチャーものは、警句や、映画スターの卵、金力家、 殴り合いなどでにぎやかに彩られていたが、 「ギャルトン事件」につづく「運命」あたりから作風は急激な変化をとげた。 すなわち、マクドナルドの心理学や社会学への興味、 家庭生活への関心、小説のなかに敢えて自己を投入させようとする試み、 抑制のきいた簡潔な文体などが、顕著になり、その総合が、探偵小説から アメリカ文学の主流へと追いやった。 レナードは、この変化は単に偶発的なものではなく、マクドナルド自身は 語りたがらないけれども、一部は個人的な悲劇に起因していると述べている。 音楽でも、映画でも、小説でも、まず体験することが先でしたから、 評論家の話など、当時は興味もなかったものです。 なるほど、今になって彼の作品を振りかえってみると、ハメットやチャンドラーの後継者としての ハードボイルド作家ということで単純に括るには、無理があるかもしれないという気にはなります。 ただ、現代のような一億総評論家時代とは違って、外国ミステリー小説が珍しかったあの頃、 一々、作家や著書の分析をしながら本を読む人など、ほとんどいなかったはずです。   「一瞬の敵/我が名はアーチャー/ギャルトン事件/さむけ/地中の男」 ロス・マクドナルドの描いたアメリカ社会における悲劇は、遅まきながら現代日本に蔓延しています。 それだけに、彼の小説は古さを感じさせず、ファンとしては嬉しいものの…複雑な思いです。 やや読書の楽しい想い出から外れて、地味な話になってしまいましたから、 そろそろ、古きよき時代のタフ・ガイが活躍する、ハードボイルド作家の話題へ移りたいと思います。 それにしても、“タフ・ガイ”…懐かしい響きです。 この言葉、50年代の末頃に、日活映画の宣伝文句でもよく目にしました。 石原裕次郎がタフ・ガイ、小林旭がマイト・ガイ、他にもダンプ・ガイとか何とか。 日活映画が嫌いで、ほとんど観なかった私は、そんな呼び方をせせら笑っていたものです。 ドリス・デイのヒット曲:「ガイ・イズ・ア・ガイ」…日本では江利チエミが歌っていたなあ…。 また小説に関係の無い、単なる想い出話になりそうなので次へ進みます。 ★ レイモンド・チャンドラー  「Trouble Is My Business/Smart-Aleck Kill」 「Trouble Is My Business/Smart-Aleck Kill」フィリップ・マーローと言えば、ハードボイルドの代名詞となっているほど有名な私立探偵です。 いかなる危険や体制の圧力にも屈しない、タフで意地っ張りの男、そして心優しいセンチメンタリスト…。 フィリップ・マーローがこれほどまで有名なのは、もちろんチャンドラーの、生き生きとした描写、 シャレた文体によるところが多いのは当然ですが、恐らく映画の影響もかなりあるはずです。 個人的にも、今となっては、小説より映画の印象のほうが強く残っています。 「大いなる眠り」 「さらば愛しき女よ」 「高い窓」 「湖中の女」 「かわいい女」 「長いお別れ」 「プレイバック」 主な著書はこれくらいですから全て読みましたが、アール・スタンレー・ガードナーや、 エド・マクベインなどに比べると、かなり寡作といえます。 上の写真は、「Trouble Is My Business」 「Smart_Aleck Kill」 昔懸命になって読んだ、ペイパー・バック版の表紙です。 「Trouble Is My Business」には、「Red Wind」 「I'll Be Waiting」 「Goldfish」 「Guns At Gyrano's」」 「Smart_Aleck Kill」には、「Pick-Up on Noon Street」 「Nevada Gas」 「Spanish Blood」 という短編小説が含まれています。  「ヌーン街で拾ったもの」 このポケット・ミステリー・ブックには、 下の4つの物語が入っています。 「「怖じけついてちゃ商売にならない/Trouble Is My Business」 「殺しに鵜のまねは通用しない/Smart_Aleck Kill」 「Pick-Up on Noon Street/ヌーン街で拾ったもの」 「指さす男」。 「指さす男」は、洋書では読んだ事がありません。 彼が他にどれだけ短編小説を書いたのか知りませんが、 主人公がフィリップ・マーローではないものは、あまり愛着が湧かないところです。 「Trouble Is My Business」「Smart_Aleck Kill」「Red Wind」の3話は、ジョニー・ダルマスで一緒ですが、 他にも、ピート・アングリッシュ、ジョニー・デ・ルース、サム・デラグェラ、トニー・レセック、テッド・マルヴァーン、 おまけに、ハメットの「コンチネンタル・オプ」みたいに名無しの主人公まで登場します。 どれも短い物語ということが、いっそう主人公への感情移入を妨げているようです。 以下、相変らず映画と小説がごっちゃになりますが、 私の想い出深い作品について、映画のシーンなどを思い浮べながら綴ってみようと思います。  「Farewell, My Lovely/さらば愛しき人よ」 「Farewell, My Lovely/さらば愛しき人よ」フィリップ・マーローを主人公にした、 私の一番好きな小説で、映画の記憶も鮮明に残っています。 画面も、よき時代の雰囲気が漂っていました。 大男マロイから、ベルマという女を捜し出すことを依頼されたマーロー、 マロイは彼女と一緒に銀行強盗をし、刑務所から出てきたばかりで、 8年も逢っていない彼女に、どうしても再会したい〜〜。 それ以降、あれやこれや、はでなアクション・シーンがたっぷりあって、 ラストの衝撃的なシーンへ〜。 事件の鍵が賭博船にあると知って、マーロウは、マロイと一緒に乗り込んだ。 そこでも激しい銃撃戦があって、船室に乱入した2人の前に、マロイの恋人ベルマがいた。 今や大金持ち夫人に収まっている彼女にとって、 共に犯罪を犯した相棒が出所して、自分を捜し始めたことを知り、 自らの過去を知る関係者たちを、次々消さなければならなかったのだ。 ようやく再会できた喜びに浸るマロイに向かって、彼女はマーローを殺すように指示、 迷ったものの、彼女の言うとおりにしようとマーローに近づいたところを後ろから、刑事に撃たれる。 その間隙をぬって、マーロウは拳銃を拾い、ベルマを撃ち殺した。 悪党で無骨な大男の、愛する女性を一途に想い続ける姿が、なんともいじらしく切なく、 また、そんな彼をもてあそんだ女がなんとも憎らしく、フィリップ・マーローが彼に同情し、 最後には仇を討つとあって、女性が殺されたとはいうものの、正直、ざまあみろと思ったものです。 この憎たらしい女を演じていたシャーロット・ランプリングという女優、 その後、「評決」という、ポール・ニューマンの法廷ものに出演していましたが、好みではありません。 友情に厚く、優しい心をもつ男、しかし、悪党ならたとえ女でも容赦しない強い正義感… ハードボイルドの典型的なヒーローが活躍する小説として、一番気に入った作品です。 また、ロバート・ミッチャムのフィリップ・マーローが、いかにもピッタリの役どころで、 そのカッコイイ姿とともに忘れられない映画です。 彼のことは以前にも触れたような気がしますから、あまりくどくど書きませんが、 おっとりした風貌、眠たげな目に、醜い社会にはほとほと嫌気をさしているといった雰囲気を感じて、 ポール・ニューマンのアーチャー同様、マーローは彼しか考えられないというほど、気に入っています。 リュー・アーチャーやサム・スペードより、基本的には女性に優しいフィリップ・マーローですから、 なおさらロバート・ミッチャムが似合うのかもしれません。 この映画の中ほどで、 例によって暴漢に頭を殴られ、気がついた場所が女郎屋…。 怪物みたいな大女の主人に、マーローがとっちめられるのですが、その彼女、 次のシーンで、自分の好きな女に乱暴したということで、逆上した遊び人にあっけなく殺されます。 その、チンピラ男が若き日のシルベスタ・スタローンでした。 他でもこういったシーンを観て、よく思うのですが、 ハリウッド俳優として成功するまでには、誰でも相当な下積みの苦労があるようです。 チャラチャラしたタレントが、すぐ主役を張れる日本の映画界とのレベルの差を痛感します。  「三つ数えろ/The Big Sleep=大いなる眠り」 「三つ数えろ/The Big Sleep=大いなる眠り」リッチな依頼主のことを考慮し、きちっとした身だしなみを確認して、 マーロウが颯爽と訪ねた先は、富豪スターンウッド将軍の邸宅。 そこで半身不随の老将軍から、次女がゆすられているので、 その処理をしてくれと頼まれる。 同時に、長女の旦那が行方不明になっていることも知らされた。 脅迫状の差出人を探り出し、その家へ入ってみると、 死体の傍らで裸姿の次女が呆然と佇んでいた。 彼女は、ここで怪しげな写真を撮られていたのだった。 〜捜査を進めるうちに、狙った容疑者は次々と殺されていく〜。 ギャングとの撃ちあいなど、派手なエピソードを盛り込んで話は進んでいくのですが、 複雑なプロットのために、チョッとわかりずらいところもあります。  短編小説での、様々な主人公を経て、このヒーローを生み出したのでしょう。 短編小説での、様々な主人公を経て、このヒーローを生み出したのでしょう。私立探偵フィリップ・マーロー誕生の記念すべき第1作目 「大いなる眠り」の映画です。 戦後間もなくの映画ですから、当然リバイバルで観たのですが、 内容はほとんど忘れています。 それでもローレン・バコール扮する将軍の長女が、マーロー役の ハンフリー・ボガートに、私生活同様、想いを寄せていたなんてところだけは不思議と頭に残っています。 この映画の記憶が薄いわりに、「マルタの鷹」の内容をしっかり記憶していることから、 フィリップ・マーローをハンフリー・ボガードが演じることを無意識に拒否しているせいかもしれません。 彼は、「カサブランカ」や「アフリカの女王」のような、男の優しさを演じても、 もちろん素晴らしいのですが、私の中では、フィリップ・マーローを演じるには、 タフすぎると同時に、カッコ良過ぎるような気がしています。 小説を読んで、そのように感じた事ということもありますが、 ロバート・ミッチャムのほうが、漂う雰囲気に加えて、やや人間的な弱さを感じて、 マーローには似合っていると思っています。 二人の映画も沢山観たので、自分の中で、勝手なイメージが出来上がってしまっています。 それだけに公平な評価はできず、それは映画に限らず、趣味の音楽でも同じことのようです。  「大いなる眠り」 「さらば愛しき人よ」に続いて フィリップ・マーローをロバート・ミッチャムが演じていましたが、 なんとも幸運な事に、深夜のテレビで偶然めぐり合いました。 この映画、驚いたのはロスではなくて、現代のロンドンが舞台。 それだけに、ミステリー風仕立てにはなっていましたが、 肝心のハードボイルド・スピリッツが消えてしまい、 映画としては、メリハリにかけていた気はします。 長女役の、サラ・マイルズという女優には馴染みが無いのですが、 ジョーン・コリンズに、何十年ぶりに巡り逢えたのが嬉しかったものです。  グレゴリ−・ペックが、非情なガンマンぶりを発揮した グレゴリ−・ペックが、非情なガンマンぶりを発揮した「無頼の群れ」で共演していましたが、 子供心にセクシーな魅力を感じたものです。 この映画、不思議とゲーリー・クーパーの「西部の人」を想い出させます。 内容的には全く違うのですが、ここに出ていた歌手のジュリー・ロンドン、 鼻筋が通った顔立ちが、ジョーン・コリンズとよく似ているのです。 妖艶なイメージが定着しているジョーン・コリンズですが、 私は「白昼の決闘」のヒロイン=ジェニファー・ジョーンズと、同じような魅力的な女性 というイメージを抱いています。 相手役が、同じグレゴリ−・ペックだったせいかもしれませんが…。 「ジャッカルの日」のエドワード・フォックスがチンケなゆすり屋、 ギャングのボスが個性派俳優のオリバー・リード、その部下が「西部の男パラディン」の リチャード・ブーンと、英米混合の豪華な俳優が出演していた映画です。 ジェームス・スチュアートは、「裏窓」でのベッド姿が気に入られたのかよくわかりませんが、 今度は寝たきり老人でした。 年をとりたくないものだと思わせる変貌ぶりに、ガッカリしたものです。 次女役は知らない女優でしたが、ヤク中の色情狂で、挙句の果てはスッポンポンに…、 比較的新しい映画とはいえ、あまり露骨な描写というのもいただけません。 ロバート・ミッチャムがフィリップ・マーローということで、雰囲気はありましたが、 一般的な評価はイマイチなのかもしれません。 私としては、思わぬ拾い物をした気分ですから、十分満足しましたが〜。 最近、面白い映画にトンとお目にかからないので、 こういった馴染みの映画に巡りあうと、盲目的に気に入ってしまう傾向があるようです。 小説の話になっていませんが、 やはり映像のイメージが強いので、こういうことになってしまいます。 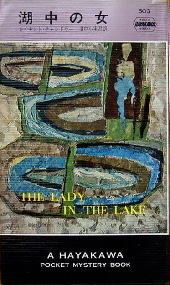 「湖中の女」 彼の作品は、たいてい映画化されていますから、 この作品もそうかもしれませんが、観ていないのでわかりません。 “トレロア・ビルは、今でもそうだが、ロスアンジェルスの西側、 六番街にちかい、オリーヴ・ストリートにある。 ビルの前の歩道には白と黒のゴムブロックがしいてあり、 戦争がはじまったので、政府にゴムを供出するためか、 掘り起こしていた。それを、トレロア・ビルの管理人らしい、 色の青い無帽の男が、恋人でもつれていかれるような顔で見つめている。〜” 「湖中の女」の書き出しですが、私が生まれて間もなく…、 丁度、第二次大戦の真っ盛りの中での作品というのですから、 今更ながら、アメリカの懐の広さを感じます。 “マーローは、化粧品会社の社長から、 警察沙汰にならないように注意して妻を捜して欲しい、との依頼を受けた。 一ヶ月前に、サンバーナディオの湖のある別荘から失踪し、 情夫とメキシコで結婚するという電話はあったものの、 二人がメキシコへ行ったという形跡はないとのこと。 情夫の家から捜査を始めたマーローだったが、意外なことに情夫は自宅にいた。 彼は、メキシコへ行ったことも無く、夫人にも会っていないという。 〜マーローは別荘へ向かった〜。 管理人と話をしながら、二人は水の澄んだ静かな湖を見ていた。 突然、管理人が大声を上げて指さした先に、深い緑色の水の底でゆらめく、人間の腕が〜〜。” ショッキングな描写もさることながら、警官の出番が多く、オシャレな会話が少ないために、 全体に重苦しい雰囲気がするのは、戦時中の小説のせいかもしれません。 しかし、この小説の一番の特徴は、本格ハードボイルドというより、 イギリスの本格推理小説のような匂いがすることです。  文章全体に張り巡らされた巧妙なプロットは、 主人公による、クライマックスでの一気呵成の謎解きのための伏線…。 ホームズやポアロでは定石のこの手法を、この小説でみる思いです。 推理小説好きな人にとっては、読み応えのある小説だと思います。 私も謎解きは嫌いではありませんが、一人称のハードボイルド小説の良さは、 主人公と読者が、常に情報を共有していることだと思っていますから、 この小説のラストでの、たたみかけるような謎解きには、チョッと違和感を感じます。 それに、できればハードボイルドでの犯人は、ギャングや、警官という 特殊な人種であって欲しくないという、個人的な希望もあります。 この小説が戦時中に書かれ、私が読んだのが30年近く過ぎてから、 さらに30年ほど経ってから、これを書いているのですから、なんとも不思議な感覚です。 そして、30年もたってから、凄く気になったことがあります。 “キングズリィは、ほんとに、ゆっくり視線をあげて、おれの目をのぞきこんだ。 「〜。そこにあれはいたのかね?」キングズリィは、フッと息をついた。 おれはうなずいた。「ぼくを、ホテルにつれていくのは、いやそうだったが、 話をきくまでは金はわたさない、といったもんですからね。〜」” フィリップ・マーローは、自分のことを「おれ」とは言わなかったはずだけど〜、 でも、この本は、間違いなくその昔私が買ったものですから、 当時から、「おれ」だったのは間違いありません。…訳者を見たら、田中小実昌氏でした。 昔、テレビ番組で、彼が、ツルツル頭に画家用の帽子をチョコンとのせて、 大橋巨泉を相手に、推理小説の翻訳について語っていたことを想い出しました。 イレブンPMだったかもしれません。 「外国の小説は、自分なりにこだわりをもって訳すように心がけている〜」。 あの時は、全く気にも留めなかったのですが、こんな事を指していたのでしょう。 今になって、マーローが自分のことを「おれ」と言っているのを読んで、 マイク・ハマーが、新宿の歌舞伎町で捜査活動をしているような、 品のなさを感じるというのも、全くもって不思議な話です。 偶然巻末の解説で、向井敏氏も同じこだわりをもっていることを書いています。 サム・スペードは「おれ」でいいけど、マーローは「わたし」でなくては〜。 その小さな違いが、小説や主人公のイメージを大きく変えてしまうのです。 ちなみに、この本を読んでいる頃、数十曲の歌を作った憶えがあります。 ほとんどカントリー風の失恋の歌というのも、今思うと恥ずかしいのですが、 当時はそんな気分でしたから〜。 そして、歌詞では全て「おれ」を使っていました。 「ぼく」「わたし」では、あまりにも惨めったらしいと考えていたはずですが、 ブルース調の、和製カントリー・ソングの雰囲気にはピッタリでした。 日本のフォークソングが大嫌いなのも、女々しい内容と、「ぼく」のせいですから、 変なこだわりをもっている…困った性分です。 昔は「日本語を守る会」を、金田一京介と推進している気分でしたから、 言葉づかいにはうるさい方で、それは体育会の名残だったのでしょう。 最近では、世の中に迎合して、かなりいい加減になってしまいましたが、 こんなところで、青春時代のこだわりを想い出すとは…我ながら苦笑ものです。  「The High Window/高い窓」 マーローは、パサデナの裕福な未亡人から、 亡夫がコレクションした、貴重なコインを盗まれたので、 取り戻してほしいという依頼を受けた。 傲慢な態度の未亡人は、息子の嫁を疑っていたのだが〜。 次々と起こる殺人事件を通して、やがてマーローの捜査は、 8年前に自宅の窓から転落した、未亡人の夫の不可解な死という、 忌まわしい過去の真相へと迫っていく。 ハードボイルドの名作として、彼の著書の中でも好きな作品でした。 洒脱な文章で、思わず引き込まれる魅力に溢れているということもありますが、 未亡人の秘書:マールに対する、マーローの優しい心遣いが心地よく、 この小説を気に入っている大きな理由でもあります。 ハードボイルドの主人公はこうではなくては、といった見事な作品ですが、 ペーパー・バックの表紙が、ハンフリー・ボガードをイメージしているのは気に入りません。 過去の呪縛から抜け出せない、精神的に不安定な秘書や、 傲慢な未亡人は、「魔のプール」を連想させ、 ふと、ロス・マクドナルドの小説かな、と勘違いをしてしまいますが、 彼の重厚なタッチと比べると、こちらはぐっと軽快です。 “I said: Until you guys own your own souls you do'nt own mine. Until you guys can be trusted every time and always, in all times and coditions, to seek the truth out and find it and let the chips fall where they may-until that time comes, I have a right to listen to my conscience,and protect my client the best way I can. Until I'm sure you won't do him more harm than you'll do the truth good. Or until I'm hauled before somebody that can make me talk.” “私はいった。君達が自分たちの魂を自分のものにするまで、 私の魂を任せるわけにはいかない。 君たちがどんな時でも、いつも信頼できて、あくまで真実を求めて、真実をつきとめ、 他人がどういおうと構わぬというのなら、別だ…、 その時が来るまで、私は私の良心に従って動き、私の依頼人を全力を尽くして守る権利がある。 君たちが私の依頼人が不利になることをせず、あくまで真実を追求する事を私が確信できるまでだ。 あるいは、私の口を開かせることができる人間のところへ私が引っぱって行かれるまでだ。” …警官の不条理に対して、マーローが語っているシーンですが、 私立探偵:フィリップ・マーローのアイデンティティを知る、見事な文章です。 イギリスの探偵小説は、私立探偵のほうが警官より権威をもっていて、 それがなんとも不自然な感じがするものですが、 こちらアメリカでは、私立探偵は、特に警官からは毛嫌いされ、 チョッと問題を起こしたら、すぐ探偵免許をとりあげられる恐れのある弱い立場です。 そして、それが本来の姿だろうとも思っています。 しかし、我らがヒーロー達は、 警官以上に正義感が強く、いかなる脅迫にも屈しないタフな精神をもっています。 だから、警官ではなく、何の束縛も受けない私立探偵になったのです。 孤独で、自分の価値観を貫き通す、そのタフな生きかたが魅力なのです。 彼らが、離婚問題は決して扱わない、というのも共通したお約束です。  “I filled and lit my pipe and sat there smoking, Nobody came in, nobody called, nothing happened, nobody cared whether i died or went to El Paso.” “パイプにタバコを詰め、火をつけて、煙を吸いながら、座りなおした。 誰もくる者がなく、誰も電話をかけて来なくて、何事も起こらず、 私が死のうが、エルパソに行こうが誰も関心を持たなかった。” 孤独な時代、マーローにならって、パイプタバコを吸いながら、 こんな文章に浸っていた頃の自分が、懐かしく想い出されます パイプは、チョッとふかしてはデスクに置いておき、 また気が向いたら、くわえてふかすということが出来て、読書の時などはとても便利です。 もちろん、火もちをよくするための修行は十分積んでいますから、 ほおって置いても、火が消えてしまうなどという、みっともない事はありません。  「長いお別れ/ロング・グッドバイ」 フィリップ・マーロウはふとしたことから、 テリー・レノックスという見知らぬ酔っ払いを助ける。 何故かテリーのことが気になるマーロウ。 偶然の出会いから、馴染みの酒場で酒を飲み交わす仲となる二人。 しかしある事件により、レノックスは国外に逃亡しなければならなくなる〜。 〜ハードボイルドの巨匠が、みずみずしい文体と非情な視線で、 男の友情を描き出した、畢生(ひっせい)の傑作。 「長いお別れ」が手元に無いので、他の本の解説から抜粋しました。 小説は昔読んだきりで、曖昧な記憶しか残っていませんが、 映画は、比較的最近になってテレビで観たので、ハッキリ憶えています。 随分ストーリーが変わっていましたが、それなりに面白い映画でした。 真夜中に、腹をすかせた猫に起こされたマーローが、スーパー・マーケットで ペットフードを買ってあげるが、猫はそれも気に入らないのか、プイと外へ出て行ってしまう。 入れ替わりに、マーローの友人が入ってきた。 夫婦喧嘩をして家を飛び出した彼が、メキシコへ行きたいというので、 マーロウは、メキシコ国境まで車で送っていった。 翌朝、帰ってきたマーロウを待っていたのは友人が妻を殺し、逃亡を幇助したという嫌疑…、 警察にしょっ引かれたが、やがて友人がメキシコで自殺したということで彼は釈放される。 翌日、資産家で作家の夫をもつ夫人から、行方不明の夫を探してほしいという依頼を受け、 その捜査から戻ってくると、今度は大勢のヤクザが待っていて、 友人が大金を奪い、お前も何か知ってるはずだと詰問される。 そのやくざは、資産家の作家とも関係があり、事件は複雑に絡み合っていた。 〜〜夫人の暗躍を不信に思ったマーローが、捜査を続けた結果、 友人の死が、偽装であったことを知る。 彼は作家夫人を自分の女にして、莫大な作家の遺産を手中に収め、のうのうと暮らしていたのである。 男の友情を裏切られたマーロウは、友人を撃ち殺す。 帰り道で、何も知らない夫人の車とすれ違うが、お互い言葉は交わさない。 ラスト・シーンに、ざまあみろという気分になったのは、映画「さらば愛しき人よ」を観た後と同じです。 このストーリーは、コンチネンタル・オプの「金の馬蹄」に、シチュエーションがよく似ているな、 と思ったものでした。 あれも、男がティファナにいて、夫人の財産を頂くといった話でした。 もっとも、ラストの謎解きは、「湖中の女」にも似ていましたが…。 書かれたのが、ダシェル・ハメットのほうが先ですから、チャンドラーは、 多少自分の小説のヒントにしたのかな、などと無責任な想像をしていたものです。 主演のエリオット・グールドという俳優を知らないので、愛着が湧かないのは仕方ありませんが、 フィリップ・マーローとは違う主人公だと思って映画を観ていたので、 退廃的で、見栄えのしないキャラクターの探偵は、なかなか魅力がありました。 実際の探偵がそうだろうと思わせる、自然な感じがよく出ていましたが、 欲を言えば、主人公には、もう少しスタイリストであってほしいものです。 あまり、みすぼらしいと、映画そのものの品位が下がるというものです。 伝統的な推理小説は、論理的な筋立てによって、謎解きをすることに主眼が置かれ、 探偵自身の人間性には、ほとんど踏み込んでいないという不満がありますが、 アメリカのハードボイルド小説の特徴が、謎解きより、探偵のキャラクターや、 気の効いた描写に重点があり、そこが、ハードボイルド小説の大きな魅力となっています。 そう考えると、エリオット・グールドの演じたフィリップ・マーローも、原作とは離れたものの、 かなり独創的なキャラクターで、ある意味、ハードボイルドの世界を表現している、と言えそうです。  ギャングのその他大勢の中に、 若き日のアーノルド・シュワルツネッガーが出ていましたが、 資産家の作家を演じたスターリング・ヘイドンが懐かしかったものです。 「大砂塵/ジャニー・ギター」の主役ですが、 私は「アラモの砦」のほうが印象に残っています。 アラモの戦い前夜といったストーリーで、 彼はジム・ボウイを演じていました。 アラモをテーマにしながら、ハッピー・エンドだったので、好きな映画です。 ジム・ボウイは、ナイフ使いの達人で、映画の中でもスリリングで かっこいいナイフでの決闘シーンがありました。 あの映画を観て、ナイフに魅せられて、密かに飛び出しナイフを買ったものでした。 グリップの横に、ベロが付いていて、それを押すとナイフがシャッと出てくるのですが、 あのてのナイフは危険ということで、その後発売禁止されたはずです。 当時は、子供でもあんな危険なものが買えたのですから、今思うと不思議です。  男の趣味のコレクションとしては、ナイフは最高ですが、 今は、せいぜいパイプや、モデルガン、 カメラ程度にしておいてよかったと思っています。 銃刀法にひっかかるようなものは、 さすがにコレクションするわけにはいきません。 もっとも、以前ミラノに行った時に、ガレリアの金物店で、ミニ・ナイフを買ってきて、 今でも、キー・フォルダーに取り付けて、日々眺めていますが〜。 「かわいい女」と「プレイバック」も手元に本が残っていませんが、 この2作は、当時からあまり気に入っていませんでしたから、特別な想い入れもありません。  「かわいい女」 ジェームス・ガーナ−主演で映画になりました。 彼のフィリップ・マーローは微妙ですが、 あまりシリアスな映画にしないために彼が選ばれたのかな、 と思っています。 私は彼が大好きですが、彼のイメージは、 この映画以前に観た、「女房は生きていた」という ロマンティック・コメディ映画で、ドリス・デイを相手に軽妙な役を演じる ダンディな弁護士役で出来上がっていました。 50年代後半から60年代の始めには、当時大女優だった、ドリス・デイの ロマンティック・コメディ映画が、立て続けに上映されました。 相手役はクラーク・ゲーブル、ロック・ハドソン、ケーリー・グラントなど、ハンサム男優ばかりでした。 ジェームス・ガーナ−が仲間いりしたことで、彼の俳優としての成功は約束されたのかな、 などと、今頃適当に想像しています。 この映画のマーローも、飄々としたおとぼけ探偵でしたから、少しも変わっていませんでしたが、 このキャラクターは、そのまま、テレビ・シリーズ「ロックフォードの事件メモ」に つながっていったのだと思っています。 「マーべりック」も、オシャレで面白いシリーズものでした。 大柄でお人よしといった風貌ですから、ちょっとユーモアのあるハンサム・ボーイ役が、 彼には似合っています。 「プレイバック」は、本も無く、映画化されたかどうかも知りませんから、省略します。 彼の名言:“男はタフでなければ生きていけない、優しくなければ生きていく資格がない。” は、この小説に書いてあったんじゃないかな、と思うのですが、 今では、名文句だけが記憶に残っていると言う有様です。 「大いなる眠り」 「さらば愛しき女よ」「高い窓」「湖中の女」など、 戦争直前から、戦時中に書かれた小説の中に、グレン・ミラーの♪「ムーンライト・セレナーデ」や、 フランク・シナトラの♪「アイル・ネバー・スマイル・アゲイン」などの曲の記述があれば、 もう一度、今度はCDで30〜40年代のヒット曲を流しながら、是非、フィリップ・マーローの世界に 浸りたいものですが、残念ながら、ロマンティックな音楽の話が出てこなかったようです。 そこがまた、ハードボイルドたる所以なのかもしれませんが、残念です。 レイモンド・チャンドラーについては、このあたりで終わりにして、 一休みしてから、ダシェル・ハメットの作品について少し触れてみようと思います ★ ダシエル・ハメット  ロス・マクドナルド、レイモンド・チャンドラーに比べて、一番遠くの存在ですが、 彼が最も活躍した時代は、私の生まれるはるか昔ですから仕方ありません。 彼が、ハードボイルド小説というジャンルを作りだし、 その後、彼を手本としたこの分野の小説が、世界中で沢山書かれることになったようです。 彼の作品は、単に推理小説にタフ・ガイが登場したといった生易しい革新ではなく、 いかなる状況でも、自己の信念を貫き通すという、新しいタイプのヒーローの目を通して、 物語が展開していくところに、従来の小説ではみられなかった斬新さがあるということは解ります。 それだけに、伝統的な本格推理小説を期待していると、がっかりするということにもなります。 その典型的な作品が、「マルタの鷹」です。 彼の作品は、その昔創元推理文庫でお世話になったものが多く、それらは全て失いました。  「マルタの鷹」 後年、買いなおした文庫本です。 私立探偵サム・スペイドは、 若い女から、ある男の見張りを依頼された。 しかし見張りの役を買って出た同僚はその夜、射殺され、 続いて問題の男もホテルの正面で惨殺される。 事件の口火を切った若い女。 彼女を追って東地中海から来た謎の男。 ギャング一味の暗躍…その昔、 マルタ騎士団がスペイン皇帝に献上した純金の鷲の彫像。 その血みどろの争奪戦に介入したタフ・ガイ、スペイドの活躍。 推理小説の歴史を通じて最高の地位を要求できる傑作…と ヘイクラフトが絶賛するハードボイルド不朽の名編!(創元推理文庫/村上啓夫氏:訳) サミュエル・スペイド…サム・スペードの正確な名前のようですが、 ハヤカワ・ポケット・ミステリーブックではダシェル・ハメット、 創元推理文庫ではダシール・ハメットと、作者名も微妙に違いますから邦訳は難しいところです。 いずれにしても、たった1作でサム・スペードは永遠のヒーローになったのですから、驚きです。 彼の場合、自分のことを“おれ”と言ったほうが似合っていると感じていたのは、 マーローやアーチャーに比べて、ずっとタフなキャラクターだと思いこんでいたせいですが、 読み直して、女性との交友関係にも倫理観が欠落していることを再発見しました。 同時に、ハンフリー・ボガートのサム・スペードのほうが、ずっと魅力的だったことも再認識しましたが。 子供の頃観た映画での、ラスト・シーンに強烈な印象が残っています。 好きだった女性を、正義のためにと冷たく警察に引き渡して、 ハードボイルドとはこういうことを言うんだな、と長く思い続けていたものです。 小説では、それほど崇高な正義感からではなく、冷酷で利己的な理由だったことに驚きました。 ただ、自分の価値観を守り抜くためには、たとえ女性に対しても厳しいんだという姿勢が、 ハードボイルドの大きな特徴だということは、この小説のラストでも強く印象づけています。 彼の風貌が、小説の冒頭に書かれています。 “サミュエル・スペイドのあごは、骨ばっていて長く、 そのさきはV字形にとがっており、それよりももっとなだらかではあるが 同じようにV字型をした口の下に、つき出ている。 鼻のさきも、小さなV字型をなして垂れ下がっている。 黄味をおびた灰色の目だけは水平だが、同じVの字のモチーフは、 鈎鼻の上部にきざまれた一対の縦じわから外側につり上がっている濃いまゆの 形にも、あらわれており、薄茶色の髪までが…高い平らな両のこめかみから… 前額の一点に向かって生えさがっている。 その顔つきはなんとなく愉快な、ブロンドの悪魔といった感じだった。”(訳:村上啓夫) これだけ読めば、スペードがハンフリー・ボガートで間違いないと思うのですが、 次のページにこんな記述があります。 “彼は身の丈六フィートからある大男だが、両肩が盛り上るように まるまると肥え、厚さが幅ほどもあるので、全体のかっこうが まるで円錐形をさかさにしたように見え、ぴんとプレスした服も、 あまりからだに合っているとはいえなかった。”  映画で知っているボガートとは、印象が違います。 子供の頃観た映画では、彼は背広姿がダンディな、 どちらかというと小柄な俳優でしたから〜。 小説の主人公に俳優を特定することがナンセンスな話ですが、 ストーリーを読んでいて、イメージする俳優といったら、 ボガートしかいないのも確かです。 それに、彼が演じなかったらスペードもここまで有名になれたか疑問です。 それまでの小説で、宝探しというストーリーは沢山あったでしょうが、 ここでは、小説の内容のほとんどが、登場人物とのやりとりに 主眼が置かれていて、宝捜しや謎解きには一向に無頓着のようです。 そもそも、警察から疎ましく思われている、一匹狼の私立探偵という設定が斬新ですし、 依頼人が謎を秘めた美人というのも、その後の小説家に大きなヒントを与えたことになるのでしょう。 美人とか大金持ちが依頼人というのは、それだけで華やかな内容を予感させるものです。 また、ハードボイルド小説では、お約束の用心棒や黒幕も登場していますから、 エンターテインメントに必要な要素を、一冊の本の中で、ほとんど披露していることになります。 この小説は意外なところでリュー・アーチャーと関っています。 いきなり殺されてしまうスペードの同僚の名前が、マイルズ・アーチャー。 その名前を頂いたのが、ロス・マクドナルドのリュー・アーチャーというわけです。 小説では軽い役回りの男性で、しかも奥さんとサム・スペイドはできているし、 サムは彼が大嫌いで、次の契約更改のときは首にしようと考えていた、というのですから、 ロス・マクドナルドも、もう少しまともなキャラクターを探せばよかったのに、と思います。 まあ、そんな些細な事を考えて、ロス・マクドナルドを読んではいませんが〜。 私は、昔観た映画を観直したり、昔読んだ小説を読み返すのがあまり好きではありません。 藁をもすがる思いで、忙しい時間を割いて、なけなしのお金をはたいて見たものは、 当時の想い出とともに、今やかけがえの無い、心の財産になっています。 ストーリーと昔の生活が繋がっていて、強い想い入れがあるものです。 ところが、特に映画などは、想像力が入り込む余地がないので、 昔観た映画を偶然観る機会があると、現在の目で厳しい評価をしてしまいがちです。 “こんな映画で、昔は感動していたのか。”とバカらしくなる事すらあります。 どんなに、稚拙な映画でも、あの当時は素晴らしい感動を与えてくれたのですから、 出来るだけそのままそっとしておきたい気分です。 もちろん、観た事の無い映画については別ですが、 映画に関しては、子供の頃から沢山観ていますから、つまらないこだわりがあるようです。  「マルタの鷹」も出版当時は、その斬新な内容に、 読者はとまどい、同時に新鮮な驚きを感じた事でしょう。 私も、数十年前に読んだ時は、 それに近い興味を抱いていたのかもしれません。 あるいは、映画の原作を読んでみたかっただけかもしれません。 その後、彼の小説よりもっと刺激的な作品に沢山触れ、 信じられないような、実社会での様々な事件を見聞きしてきたせいか、 今読み直してみると、ストーリーにはやや退屈します。 古き良き時代を感じる事はできますが、ミステリー小説の世界で、 70年以上も昔の作品とあっては、さすがに色あせるのは当然のことかもしれません。 その点、音楽の世界では、古いとか新しいということは関係なさそうですし、 むしろ今でも、古いもののほうに高い音楽性を感じてもいます。 「マルタの鷹」が出版されたのは、世界恐慌が始まった翌年ですから、 音楽の世界でいえば、それまでジャズの中心地だったシカゴから、 サッチモやエディ・コンドン達が、新天地での成功を夢見てニューヨークに進出し、 活躍し始めた頃、ということになります。 そして彼らの演奏は、それ以前のものでも、それ以降のものでも、 少しも色あせない魅力をもっているところが最大の魅力です。 昔聴き馴染んだ音楽は、そのメロディと共に当時の自分が蘇ります。 耳からの情報というのは、空想の世界を漂う余地があるからでしょう。 でも、音楽を聴きながら、楽しかった日々、辛かった日々を懐かしく感じるようになるには、 ある程度の年令にならないと味わえませんから、今となっては貴重な財産です。 古い娯楽小説というのは、想い出だけに止めておいたほうがよいのかもしれませんが、 ストーリーは陳腐になっても、サム・スペードの個性はいまだに生き生きと残っているのですから、 これが、ハードボイルド小説の本来の狙いなのかもしれない、などと考えています。 なんと言っても、謎解きより、主人公の強烈な生きざまが魅力のハードボイルド小説ですから。 トレンチコートの襟を立て、橋の上からタバコを指先でピシッと弾き飛ばす〜、 ボギーを気取って、私も随分やったものですが、 今の時代、その行為は迷惑条例違反に該当します…、すっかりせちがらい世の中になりました。 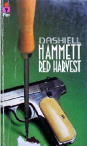 「Red Harvest/血の収穫」 「Red Harvest/血の収穫」ダシエル・ハメットの初の長編小説で、 ここで活躍する主人公は、名無しの探偵:コンチネンタル・オプです。 「マルタの鷹」でサム・スペードが誕生する以前の、 世界大恐慌をまもなく迎える、1920年代末期に書かれたものです。 舞台は、架空の鉱山町「パーソンズヴィル」、 その腐敗ぶりから、別名「ポイズンヴィル」と言われる所です。 コンティネンタル探偵社のおれは、小切手を同封した事件依頼の手紙を受け取って、 ある鉱山町に出かけたが、入れ違いに依頼人が銃殺された。 利権と汚職とギャングのなわばり争い、町は不気味な殺人の修羅場と化した。 その中を、非情で利己的なおれが走りまわる。 リアルな性格描写、簡潔な話法で名高いハードボイルドの先駆的名作。 巻末に書いてあるこの本の紹介文です。 ギャング、悪徳警官、密造酒販売、ばくち打ち、金が命の娼婦などなど、 多彩な顔ぶれですが、彼らが順を追って殺されていくのですから、 ハードボイルド小説というより、バイオレンス小説といったおもむきですが、 不思議なことに、生々しい殺戮場面が出てきません。 主人公自身も、「ポイズンヴィル」に毒され、悪人同士の殺し合いを仕組んだり、 探偵としての立場を見失った行動をとりますから、 推理小説での、殺人犯を探し出す熱血探偵の活躍物語とは、全く違います。 この話は、町を牛耳る依頼人の父が、 以前、労働者のサヴォタージュや、ストライキを回避するために、 あくどい手を使ったことが、様々な殺人事件の根底にあります。 恐らくこの小説の発表当時の実際のアメリカ社会では、珍しくない状況だったはずです。 1人の悪人と被害者という単純な構図ではなく、社会全体を覆うほどの 複雑に絡み合った腐敗が蔓延し、そのこと自体に国民が麻痺していた時代で、 発表当時は、リアリティのある身近な話として受け止められたのではないでしょうか。 ハードボイルド小説としての面白さをそれほど感じませんから、 著者は探偵小説の形で、アメリカ中にはびこる社会悪を告発するつもりだったのかもしれない、 などと勝手に推測しています。 この時代の大資本と労働者の闘争、腐敗した社会の様子は、 私も、映画や小説で沢山目にしてきました。 1920年代のアメリカというと、ジャズの最も栄えた時代で、 そのバックグラウンドとしての、禁酒法、酒場、それを経営するギャング、 汚染された政治家や警察など、外野席から見ているかぎり、興味が尽きません。 残念ながら、この小説には、サッチモもエディ・コンドンも出てきませんが、 ジャズは、こういった社会の影の部分を舞台に、繁栄を謳歌していたことも事実です。 洋書の表紙は、なかなかショッキングなデザインですが、 娼婦を刺したアイスピックを暗示しているのでしょう。 “My right hand held the round blue and white handle of Dinah Brand's ice pick. The pick's six-inch needle-sharp blade was buried in Dinah Brand's left breast. She was lyin on her back, dead.”…小説のものとは違うアイスピックようですが〜。 ハヤカワ・ポケットミステリー・ブックが、全ての本の表紙に、抽象画を使っているのに対して、 円形のラックに並んでいた、このような洋書は、表紙デザインだけでも興味をひくものばかりで、 内容も確認しないで、思わず買ってしまったものも多くあります。 英語が得意では決してないのですが、「Red Harvest」は、 会話が主体の小説ですから、比較的理解し易かったものです。 それに、1人称のハードボイルド小説というのは、 それが特徴なのでしょうが、難しい単語や言い回しが少ないようです。 もっとも、私はかなりの感覚人間ですから、アーティストの情報や、曲の評価などに関係なく、 自分の好みで音楽を楽しむように、たとえ知らない単語が出てこようと、辞書などひいたこともなく、 自分勝手な言葉の解釈をして、読み通したものです。 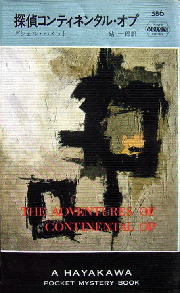 「探偵コンティネンタル・オプ」 彼は、短編集を沢山書いていて、 創元推理文庫、ハヤカワ・ポケット・ミステリーブック、 洋書のほかに、昔は、エラリークイン・ミステリー・マガジンの中でも 彼の短編が載っていました。 写真のポケット・ミステリーブックには、 「シナ人の死」「メインの死」「金の馬蹄」 「だれがボブ・ティールを殺したか」「フウジス小僧」の5作が入っています。 また、Panの洋書で、同名のペーパー・バックには、 「The Tenth Clew/10番目の手がかり」 「The Golden Horseshoe/金の馬蹄」 「The House in Turk Street/ターク通りの家」 「The Girl with the Silver Eyes/銀色の目の女」 「The Whosis Kid/フウジス小僧」 「The Main Death/メインの死」 「The Farewell Murder/フェアウェルの殺人」の7作が入っています。 彼がこれらを書いたのが1920年代のことですから、アメリカ社会は、 「血の収穫」で触れたような状況で、彼自身が苦心して小説の題材を探さなくても、 身近なところで殺人や不正が行われていた時代のはずです。 主人公は当然、コンチネンタル・オプという名無しの探偵で、 「私」の活躍するものばかりです。 内容は省略しますが、どれも謎解きの魅力に溢れていて、 短編だけに、より内容の面白さが凝縮されている感じがします。 謎解きに加えて、アクション・シーン、気の効いた会話など、 ハードボイルド生みの親、といった内容であることは間違いありませんし、 どちらかというと、長編小説より今の時代でも古さを感じさせない 優れた作品ばかりのような気がしています。 他にも「デイン家の呪い」「ガラスの鍵」「影なき男」という作品があるのですが、 昔読んだときもあまりピンとこなかったので、今では著書も残っていません。  サム・スペードといったら、 ハンフリー・ボガートというのが、私の場合セットになっていますが、 リアルタイムで観た「必死の逃亡者」… ボガートが脱獄囚役を演じ、悲劇的な最後を迎えるという、 私にとっては納得できない内容の映画でした。 ハメットの作品ではありませんが、不思議といつまでも心に残っていて、 ハンフリー・ボガートの話題が出ると、先ずこの映画のラスト・シーンが蘇ります。 この話になると長くなりそうなので、ハメットの著書についてはこの辺にして、 次に移りたいと思います。 ★ ロス・トーマス  「冷戦交換ゲーム」 「冷戦交換ゲーム」これを読んだ頃は、丁度東西の緊張が高まっていて、 ソ連とアメリカによる、一触即発の恐怖が身近に感じられた時代でした。 この小説も、リアル・タイムの東西のスパイ活動を主題としているので、 強いて分類すれば、スパイ小説ということなのでしょう。 でも私は、これをハードボイルド小説として読んでいました。 サスペンスに富んだストーリーそのものより、登場人物の人間的な魅力や、 粋な会話は、チャンドラーやロス・マクドナルドの仲間、と言う感じがしましたし、 そもそも国家のために必死になって諜報活動をするなんていう、 イギリスの本格スパイ小説の主人公とは、全くタイプの違うキャラクターでしたから…。 唯一残っている、ボケット・ミステリー・ブックの裏にある解説です。 <マックの店>でこんな事件が起こったのは初めてだった。 覆面姿の二人組が拳銃を持って闖入し、客に銃弾を撃ち込んで逃げたのだ。 ボン近郊に退役軍人マックがこのバーを開いたのは十年前、 アメリカのスパイという身分を隠すためおしかけ、経営者となったパディロと始めた。 以来、マックは相棒の裏の仕事には口をださず、パディロは腕利きスパイとして、 マックの片腕として大過なくすごしてきた。そこへこの事件だ。 パディロは訳もわからぬまま。正体不明の男たちを追って飛び出していった…。 事件の直前、アメリカ政府内では大変な事が起こっていた。 米国安全保障局<NSA>で暗号解読に携わる数学者二人が ソ連に亡命したばかりか、彼らが同性愛の関係にあったことが判明したのだ。 機密が洩れる恐れがあるばかりか、 もし亡命者がホモだとわかれば大変なスキャンダルになる。 何としても内密に解決しようとするNSAは、苦肉の策としてKGBに対し、 一流の諜報員パディロと亡命者の交換を提案したのだ。 真相を知らない彼はスパイ交換という陰謀に巻き込まれ、 彼の窮状を知ったマックもこの危険なゲームの渦中に…。 緊張みなぎる東西ドイツを舞台に、実際に起こった亡命事件をもとに 熱いスパイ戦を描く実力派のデビュー作!。 アメリカ探偵作家クラブ最優秀新人賞受賞。 ともかく、凄くオシャレな小説家が出てきたものだと、喜んだものです。 今は手元に無い、マッコール&パディロもの:「クラシックな殺し屋たち」では、 いかなる時もプロフェッショナルな行動をとるパディロと、 チョイとおとぼけのマッコールのやりとりは、もっとシャレていて、 面白かったような気がしています。 このハードカバーの表紙は、確か可愛らしいイラストでしたから、 ハヤカワ・ポケット・ミステリーではなかったのでしょう。 今頃になって、手放してしまったのが悔やまれます。 私のロス・トーマス=オリバー・ブリークに対する好印象は、 パディロとマッコール、そしてセント・アイブスの魅力で決まりました。 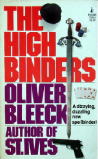 「The High Binders」 金持ちで、今はロンドンにすむ友人エディの依頼で、 現地ロンドンに飛んだセント・アイブス、 早速指定のパブへ行き、ある男におごられた酒を飲んだら、 なぜか急に前後不覚になり、 あげくに警官に暴行をはたらいたらしく檻の中…、 間もなく出所し依頼人の家へ〜、 そこで若い妻セイルを紹介される。 セント・アイブスへの依頼の内容は、 実家の家宝の剣が盗まれてしまったので、盗んだ泥棒と交渉して取り戻してくれというもの。 交渉の金額は10万ポンド、しかし実際の価値は安く見積もっても300万ポンド。 「セント・ルイスの剣」…握りのオシリに卵大のダイヤモンドがはめ込まれている 代物ということなのですが、セント・アイブスはこの話には裏があるとにらむ…。  オリバー・ブリーク名義で書かれた、 セント・アイブスのシリーズです。 二作しか読んでいませんから、勝手な事は言えませんが、 どうやら、このシリーズは、金持ちから盗まれた大切なものを、 金と引き換えに取り戻す、という筋立てがベースにあるようです。 セント・アイブスはその仲介人ということで、 取り戻す過程で、殺人あり裏切りあり、徐々に真相が明らかになり、 あっと驚くどんでん返しの結末が待っている、面白いサスペンス小説です。  「強盗心理学」というセント・アイブスものは、 和訳もされました。 そして、これはずばり 「セント・アイブス」 という題名で映画化されましたから、 よく憶えています。 本はもう手元にありませんが、確か舞台はニューヨークから サンフランシスコに変わっていましたし、 ストーリーも随分原作とは違っていたはずですが〜。 主人公のセント・アイブスは、元一流の事件記者で、今は売れない小説家。 金持ちの老人の依頼で、盗まれた大切な日記を取り戻すために、 10万ドルを泥棒に渡す仕事を引き受けたものの、 受け渡しのセルフ・クリーニングの店で、回転するドラムの中に人が…。  知らず知らず殺人と陰謀に巻き込まれていく主人公、 そして、老人の美しい秘書との一夜の秘め事、 (その瞬間、花火が上がるユーモアはなかなかのものでした)。 ラストでの、マクシミリアン・シェル、ジャクリーン・ビセットの意外な本性、 そしてセント・アイブスとの撃ちあいによる、 ハードボイルド独特の無情な結末。 複雑なプロットで、ディテールは忘れましたが、面白い映画でした。 もし、主人公がチャ−ルス・ブロンソンでなかったら最高でした。 今でも、なぜ彼にこの主人公をやらせたのか、大いに疑問と不満を抱いています。 ポール・ニューマンなら、文句なしに最高のハードボイルド映画でした。 70年代、チャ−ルス・ブロンソンは凄く人気が高かったので、 興行的な意味合いが強かったのでしょうが、残念です。 私は、彼の作品をほとんど観ていますが、魅力を感じた事が一度もありません。  でも、映画自体は面白く、紅一点:謎に満ちた美貌の秘書役を演じた、 ジャクリーン・ビセットが素晴らしかった事で、満足はしています。 もし、あの役を例の如くブロンソンの妻のジル・アイアランドあたりが演じていたら 全く下品な三流映画になってしまったことでしょう。 私がジャクリーン・ビセットを最初に観たのは、 スティーブ・マックィーンの「ブリット」でしたが、 退廃的な雰囲気を漂わす美人として、心に残りました。 その後、「大空港」では、スチュワーデスでディーン・マーティンの恋人、 また、チョッと変わった西部劇「ロイ・ビーン」では、ポール・ニューマンと共演して、 その美貌を惜しげもなく披露してくれました。エヴァ・ガードナーの娘役だったかな…。 「ポークチョッパー」 「可愛い娘」 「The Money Harvest」 あたりまで読んで、 ロス・トーマスについては、お終いと思っていました。 恐らく、私の仕事とか生活上の都合でそうなったのだと思いますが…。 読書については、一気呵成に読み続け、読まないとなると全くその気にならない、 というのが癖ですから、そんなせいもあったのかもしれません。 後に偶然、店頭でオレンジ色の表紙の文庫本で彼の作品に再会し、 懐かしくなって何冊か読むことになりました。  「八番目の小人」 「モルディダ・マン」 「五百万ドルの迷宮」 ロス・トーマス名義のものは、相変らず、 一人のヒーローが活躍するのではなく、 仲間と一緒という設定は変わらないものの、 何か物足らない感じを受けました。そこそこ楽しめたことは確かですが、 それほどの感動もないので作品の内容は省略します。 それぞれのグループが、マッコールとパディロのコンビほどの 信頼で結ばれているわけでもなく、洒脱な会話からも遠ざかってしまい、 複雑なプロットだけが、妙に心に残る作品ばかりです。 ロス・トーマスを“クライム・ノヴェルの最高峰”と、 「八番目の小人」の解説で称しています。やや抵抗のあるところです。 謎解きや、スケールの大きさだったら、最近の方が優れているのかもしれませんが、 私が胸ときめかせて読んだロス・トーマスではありませんでした。 これは、彼の作風が変わったこともあるでしょうし、 私自身の心の変化に起因しているのかもしれません。 私が抱いていた彼の印象は、ミステリー作家としてみると、 プロットは面白いけれど、チョッと迫力に欠けるという点で、 ジェフリー・アーチャーに近いものがありました。 ユーモアのセンスに関しては違いますが〜。 昔の作品は、主人公のキャラクターや、シャレた会話が魅力的でした。 それだけにハードボイルド作家というイメージなのかもしれませんが、 ジャンルなど、音楽同様あまり作品とは関係ありません。 彼の、上品で洒脱な文章によって心癒された良き想い出は、 いつまでも忘れる事が無いでしょう。 「黄昏にマックの店で」という本が出ているようですが、 もし、その後の二人が、本当にたそがれてしまっていると淋しいので、読まずにいます。 彼の作品が、ポケット・ミステリー・ブックで全て出版されていたら、 間違いなく読み通したはずですが、彼の著書はなぜかあっちこっちに分散されて、 私も振り回されたというのが実感です。 このまま、マイケル・リューインやロバート・パーカーに つなげようと思ったのですが、彼らは新しい時代の小説家ですし、 私の心の中では、それまでの作家とは大きな落差があります。 そこで、ハード・ボイルドといったら、一般的には彼抜きには語れないということで、 ここらでミッキー・スピレインとマイク・ハマーの想い出について、チョッと触れてみたいと思います。 ★ ミッキー・スピレイン  「Mickey Spillane/Mike Hummer」 「Mickey Spillane/Mike Hummer」マイク・ハマーは、私が最初に好きになった私立探偵かもしれません。 私立探偵については、既に「ペリー・メイスン」の相棒:ジョン・ドレイクでお馴染みでしたが、 その後のテレビ・シリーズで観た「マイク・ハマー」は、探偵が主人公のドラマという面白さと、 主演のダーレン・マッギャビンに魅力があり、大いに気に入っていました。 チョッと苦みばしっているけれど、妙に人なつっこい顔が好きで、 白黒の30分番組でしたが、毎週楽しみに観ました。 けだるい感じの♪「ハーレム・ノクターン」 が流れる中、 “俺はマイク・ハマー、私立探偵だ!〜”…そんなセリフと一緒にタイトルが出て、 毎回面白いエピソードが展開する、何ともオシャレな番組でした。 今でもマイク・ハマーといったら、マッギャビンがまず頭に浮かびます。 同じ頃「ピーター・ガン」という私立探偵ものもありましたが、内容はやや地味でしたから、 憶えているのは、カッコのいいテーマ・ミュージックだけです。 思い返してみると、当時、外国テレビ映画のテーマ曲は、素晴らしいものばかりでした。 夢の世界のような、私立探偵とか秘密諜報員が活躍する外国の映画には、 無条件で飛びついたものですが、40年以上経っても憶えているヒーローは少ないものです。  「Darren MacGavin」 彼がいつでもくわえているタバコ:ラッキー・ストライクを見て、 ペリー・メイスンのお気に入り、ポール・モールにしようか、 こちらにしようかと、随分迷った時期があるくらいです。 アメリカ人には、ミッキー・スピレインのファンが多かったようで、 ラッキー・ストライクがよく売れた、と聞いた事があります。 昔も今も、イメージ・キャラクターというのは大事という話ですが、 私は、デザインの上品さから、ペリー・メイスンの方を選びました。 「俺の拳銃はすばやい」は小説を読んでいませんが、映画を観た憶えがあります。 ストーリーは忘れましたが、友達との間で“俺の拳銃は素早い”という言葉が流行りました。 ハード・ボイルドという言葉を、そんな映画で知ったのか、 マイク・ハマーのテレビ・シリーズで覚えたのか、 大藪春彦の「野獣死すべし」の宣伝文句で知ったのか、今となっては想い出せませんが、 日本でも、ハードボイルドという言葉が随分流行りました。 当然日本のハードボイルド小説などには、見向きもしませんでしたが…。 「堅ゆで卵」…感傷を排した冷静な思考と、 強い信念に基づいて行動する主人公の目を通して描かれる、非情な世界〜、 ハードボイルド小説を定義すると、恐らくそんなところかもしれませんが、 曖昧な言葉だけに、解釈も分かれるところです。 トレンチコートを着て、ソフト帽を被り、いつもタバコをくわえていればハードボイルド、 というわけでもありませんし、私も、勝手に自分なりのハードボイルド観をもっています。 社会人になって、テレビ時代の懐かしさから、 ペリー・メイスンや87分署を小説で読むようになって、 ポケット・ミステリー・ブックで、ミッキー・スピレーンに再会しました。 そして、それが私のマイク・ハマーのイメージを大きく崩すことになりました。 テレビと違って、小説でのハマーは、サディスティックで女にだらしない探偵でした。  「大いなる殺人」 低くたれこめる空から、激しい雨が降りしきる、ある小都会…。 私立探偵マイク・ハマーは夜更けのバーで飲んでいた。 かなり酔いがまわったと思われる頃、 シャツ一枚の、全身ずぶぬれの一人の男が 赤ん坊を抱いて入ってきた。〜” これが、「裁くのは俺だ」とともに、 彼の代表作になった「大いなる殺人」の書き出しです。 内容については省略しますが、この赤ん坊の、常識では考えられないような 行動によって、事件が終息する巻末には、正直呆れたものです。 巻末にある編集者の文章を載せてみます。 “この「大いなる殺人/The Big Kill」は <101>というシリーズ・ナンバーでおわかりのように、ハヤカワ・ミステリの第一作目である。 ハヤカワ・ミステリは1953年(昭和28年)9月、この「大いなる殺人」でスタートした。 そして、そのときには、江戸川乱歩氏がこの作品の解説を書かれた。 それから7年、ハヤカワ・ミステリは待望の第一期500冊刊行を果たし、 その間に、ためらうことなく、つねにすぐれた作家を紹介してきた。 ロス・マクドナルド、E.S.ガードナー、エド・マクベインといった作家は、 今でこそ人気作家だが、その紹介の光栄はハヤカワ・ミステリがになうものだ。〜〜。 スピレインの創造したマイク・ハマーは、 アメリカで生まれるべくして生まれた私立探偵である。 さんざんな悪評をこうむりながらも多くのひとに読まれたのは、 やはり彼の小説にはいくつかの魅力があったからだ。 セックスとサディズムと暴力…、 この3つをスピレインほど効果的に用いた探偵作家はほかにいまい。 だが、それだけがスピレインのすべてではないのだ。 具体的にいえば、彼が登場するまでの20年間は、世界戦争、政治的追放、 ナチの残虐といった巨大な悪がはびこった。 アメリカだけにかぎっても、大規模な犯罪組織、汚職、売春の発生が アメリカ人の個人生活に一種の挫折感をあたえていた時期だった。 それはつまり、個人の力ではどうしようもないといった絶望感でもあった。 ここに、マイク・ハマーの存在理由もあったのである。 〜〜ここで私立探偵、マイク・ハマーの横顔をえがいてみよう。 彼はニュー・ヨーカーだ。 ラッキー・ストライクをたえず吸い、かなり酒もいけるが、けっして酒には飲まれない。 好きな料理はステーキとフライド・チキンとパイである。 旧式の自動車をもっているが、エンジンは特製の強力なやつだ。 子供の事となると、ハマーはセンチメンタルな男であるくせに、 女性のネックラインとか、乳房に病的愛着を持っている。 そして、身長6フィート、体重190パウンドのマイク・ハマーは 探偵史上、もっともタフで、もっともサディスティックな探偵である事は確かである。 しかし、秘書のヴェルダに対してはまったくロマンチックな探偵になる。” こんな文章を、昔読んだのかどうかすら忘れましたが、 ともかく、これほどイメージ・ギャップを感じた主人公はいません。 マイク・ハマーの良いイメージは、 ダーレン・マッギャビンの個人的魅力で生み出されたもので、 小説を読んで、原作者のスピレインにはすっかり幻滅したものです。  「復讐は俺の手に」 “その男はぶち殺されていた。 パジャマのまま床に横たわり、絨毯の上に 脳髄をまきちらして、手には私の拳銃を握っていた。〜” 私が、ミッキー・スピレインを本格派ハードボイルド作家ではない、 と思うようになったのは、これを読んでからです。 品のない文章は「大いなる殺人」でも気になったのですが、 それ以上に、ここでのマイク・ハマーは、いろいろ理屈はこねているけれど、 自分の信念など希薄で、単なる暴力好き、女好きとしか思えない男として描かれています。 そして、極め付きがこの小説の結末…。 ハマーが熱を上げる、女性として欠点の無いほどの美人で、モデル・クラブの経営者:ジュノーが、 実は一番の悪党だと知って、ハマーが残酷に撃ち殺してしまうのですが、 この綺麗な女…なんとビックリ、男だったというお粗末なオチまでついています。 このシーンはテレビ映画でも観たことがありますが、それまで、か細い体で 顔も美しかった女性が、突然、いかつい体の男に代わりハマーに襲いかかる〜、 映像としても相当無理があるな、と感じたものです。 ヴァイオレンス、サディズム、セックス…、彼の描く世界は、 アブノーマルで、とても正統派ハードボイルド小説とは、言いがたいものがあります。 ミッキー・スピレインや、大藪春彦が人気があったということで、ハードボイルドというのは、 その程度の意味しかないのかもしれませんが、それでは夢がないというものです。 自分の信念に基づいて行動するために、心ならずも危険な世界へ巻き込まれてしまうのと、 自らが暴力を撒き散らすというのは、決定的に違います。 正統派ハードボイルド探偵小説というのは、上記を指すのだと思いますし、 一般的に言われる、ハメット→チャンドラー→マクドナルドという系譜は、 その意味では正しいのではないかと思っています。  「裁くのは俺だ」 手元に本が無いのですが、 これは比較的新しい映画で観ましたから、よく憶えています。 題名は「俺が掟だ!」 主演のアーマンド・アサンテは、 私の抱いていたハマーのイメージとは、全然違いますが、 映画としては良く出来ていたと思います。 戦友が無残にも殺され、その復讐を誓って事件を捜査するのですが、 彼が性的に不能でクリニックへ通っていたことや、大きな儲け話をしていたことを、 別居している女房から聞き出します。 その後、元CIAの大佐やクリニックの主催者の女性が、治療の裏で、 覚せい剤を使った、あくどい商売をしていることを付きとめます。 そこからがお決まりの銃撃戦…、そして、親友を殺した犯人が美しい クリニックの主催者だと知り、 彼は、親友が殺されたような残酷な手口で、その女性を撃ち殺す。 エロ・グロ・ナンセンスという言葉が、昔流行りました。 ストーリーはそんな感じですが、映画でのハマーは、 アーマンド・アサンテが、あまり嫌らしくなく退廃的な雰囲気をかもしだして、 私立探偵の孤独感とか、男のロマンといったものを上手に表現していました。 小説を映画化すると、大抵は、作者の繊細で豊かな表現が飛んでしまい、 俳優のキャラクターだけが強調されて、不満に思うことが多いのですが、 マイク・ハマーだけは、ミッキー・スピレインの手を離れた方が、 よほど魅力的だ、と皮肉な見方をしています。  「寂しい夜の出来事」 “こんな夜に、橋を歩いて渡るなんかいやあしない。 雨は濃い霧といっていいほど煙っていた。 その冷たい灰色のカーテンは、 鋭い音をたてて通り過ぎる車と おれをへだてている。 車の曇った窓の中に閉じ込められている顔が、 白いぼんやりした卵型に見えた。 夜のマンハッタンの華やかな輝きさえ、 はるか彼方にあるニ、三の眠たげな黄色い光に変わっていた〜。” 彼の著書は、わずかしか読んでいないのですが、 詩的なイントロに負けず、題材も面白くプロットも巧みで、 唯一、読み応えがある小説だったという記憶があります。 テーマになっている、 戦後間もなくの、アメリカ社会における、共産主義の台頭と弾圧。 「赤狩り」の、リアル・タイムに書かれた作品であることが、 今になって、歴史的な意味を強く感じます。 チャップリンも、ハードボイルドの父:ダシエル・ハメットも、 このマッカーシー旋風の被害者だったようですし、フランク・シナトラも、 疑いをかけられたと、どこかで読んだ憶えがあります。 文中に見え隠れする、ソ連共産党員の活躍をメインに扱ったら、 また違った面白さがあるのですが、 なにせ、我がマイク・ハマーは、ノンポリで、独りよがりの男ですから、 そんな政治的な動きとは関係なく、独自の捜査を展開します。 相変らず、女の体に夢中になり、45口径やトミーガンをぶっ放す、 破廉恥な行動は健在です。 しかし今回は、最後にアメリカの危機を救うような大手柄をたてます。 デズモンド・バグリーの「マッキントッシュの男」…、 イギリスの国会では、超タカ派で愛国者の如く振る舞い、 国民から高い支持を得ている男が、実はソ連のスパイだった。 今で言えば、韓国政府内に潜入する北朝鮮スパイ〜。 このアイディアがミッキー・スピレインの創作だとしたら、大したものですが、 世界大戦が終わって、ソ連の共産主義が台頭した時代には、 この小説のモデルのような人物が、現実にいたのかもしれません。 二大強国によるイデオロギー戦争も、 ベルリンの壁が取り除かれ、ソ連の崩壊によって終息した今、 初めてこの本を読んだ人には、何の感慨も沸いてこないのでしょうが、 私は、戦後の混沌とした時代、東西の裏舞台で行われたスパイ戦争モノは、 一番のお気に入りですから、この本も興味深く読みました。 長くなりましたから、最後に、マイケル・リューインとロバート・パーカーについて、 簡単に触れておこうと思います ★ マイケル・リューイン  「消えた女」 「消えた女」彼の作品は、ネオ・ハードボイルド小説というのだそうです。 気付かないうちに、ハヤカワ・ポケット・ミステリ・ブックの棚に、 次世代私立探偵が何人も登場し、時代の変化を感じたものですが、 私がマイケル・リューインを知った頃は、私生活でも最悪の状態を脱していて、 マクドナルドやチャンドラーに出会った頃とは、全く違う心境でした。 そのため、ロス・マクドナルド以降の私立探偵に、 想い入れがグッと希薄になってしまったのは仕方ないところです。 音楽や小説は、そのものの価値とは関係なく、 それに初めて接した時代の自分が投影されているものです。 同じ頃、有力候補として、ロジャー・サイモンの「大いなる賭け」、 ロバート・パーカーの「ゴッドウルフの行方」などがありました。 当初は、こちらの方が面白そうだな、と感じていたのですが、 続編を読んでいくうちに、マイケル・リューインが本流だろうなあ、 と思うようになったものです。 拳銃を持ち歩かず、肉体的にも自信がなく、そもそも暴力嫌いという、 心優しい私立探偵なんて、およそ魅力を感じないのですが、 プロットも描写も、奇をてらったものではないところに好感がもて、 他の作家より、引き込まれるものがありました。 それにしても、私立探偵が決して拳銃を携帯しないなんて、 読む前から解っていたら、決して彼の本を手にしなかったはずです。  「A型の女」 “傷ついた小鳥のように 少女エロイーズはサムスンのオフィスに 飛び込んできた。 お願い、わたしの生物学上の父親を 探してと言いながら…。 七年間の私立探偵稼業をふり返っても、 サムスンはこんなに面食らったことはない。 依頼人は十六歳、しかも大富豪クリスタル家のひとり娘だ〜。 ”(巻末解説) 何となく、リュー・アーチャーが登場しそうな雰囲気があります。 マイケル(マイクル)・リューインの描く、私立探偵:アルバート・サムソン(サムスン)…、 ( )内の名称が正しいことに気がつきましたが、今更変えても仕方ありません。 確かに新しい時代の探偵稼業とはこんな感じかな、と思わせる親近感がありますが、 それにしても、ハメット、チャンドラーとは随分キャラクターが違います。 探偵は西海岸、という常識?も破り、 馴染みのないインディアナポリスが舞台というのも、時代を感じさせます。 新しい世代にとっては、サムソンのライフスタイルがカッコよく見えるのでしょうが、 私の場合は、ロス・マクドナルドのタッチとよく似ているということで、 やや物足らないものは感じながら、この新人に期待したものです。 ともかく、拳銃も持たず暴力嫌いというハンディキャップ?をもちながら、 これだけ熱中させるのですから、只者ではありません。 対照的な作家が、ロバート・パーカーですが、彼については後述します。 依頼主が富豪であることや、捜査をしていくうちに、 忌まわしい過去の出来事へ移っていくところなど、お約束どおりの設定ですが、 オーソドックスで丁寧な描写からは予想もつかない、ドラマティックな結末へ展開する、 見事な手腕には大いに満足しました。 言葉の断片や表情の変化などの描写を通して、登場人物が生き生きと描かれている点や、 主人公に、やや厭世観が垣間見えるところも、私好みです。 私立探偵はこうでなくては、と納得させられる作品でした。 「消えた女」は、より複雑に絡み合った人間関係と、謎解きの面白さに溢れた作品で、 ハメット・チャンドラー・マクドナルドの正統な後継者を感じさせる、 本格ハードボイルド小説の醍醐味が味わえます。一番気に入った作品です。  「夜勤刑事」 リーロイ・パウダーというインディアナポリス警察の 警部補を主人公とした物語で、 サムソンは脇役で登場します。 “パウダーのイメージはいかにもこわもてのする、 タフで荒々しく、かつ敏腕そのものというところだが、 その実体は夜勤から抜け出られそうもない。 しかも定年も間近の窓際族警官なのだ。” どちらかといえば、従来のハードボイルド小説のキャラクターは、 サムスンよりパウダーのほうが近い感じで、こちらもかなり魅力的なのですが、 警察ものは「87分署」以上の作品はないと思っていますし、 個人的には、体制に反抗する、しがない私立探偵に共感していますので、 これ以上を望まないというのが、正直なところです マイケル・リューインが、同時並行的に二人の全く異なったキャラクターを 主人公にした小説を書いているのは興味深いところです。 商業的な意味合いもあったのでしょうが、 恐らく、新しいハードボイルド小説のあり方を探る中で、 サムソンだけでは表現できない主張を、補完する意味で、 リーロイ・パウダーシリーズを書いたのではないかと、勝手に想像しています。 新時代のハードボイルド小説…、 さすがに、伝統的な私立探偵・警察官のヒーロー像とは程遠い存在です。 アルバート・サムソンは、リューイン自身かと思わせるほど、 自然体で平凡な私立探偵で、自虐的なほど内省的な性格。 一方のリーロイ・パウダーは、短気で強引で、独りよがりなため、 警察署内でも浮いている存在にも関らず、この仕事を天職だと思っている、 タフなワークホリック。 それに、従来のハードボイルド小説には欠かせない三点セット、 酒・暴力・セックスに無縁というのも、随分大胆な発想ですが、 現代における等身大のキャラクターや描写が、逆に読者の共感を得たのかもしれません。 彼の作品について書き始めると長くなるので、あとは読んだ作品を列挙するにとどめます。  「内なる敵」 「季節の終り」 「死の演出者」 「豹を呼ぶ声」 「沈黙のセールスマン」 「表と裏」 マイケル・リューインは、時代が変わっても、たとえ拳銃を所持しなくても、 上質な内容さえ備わっていれば、読み応えのある探偵小説になる…、 そんな読書の楽しさを教えてくれた、優れた作家だと思っています。 ★ ロバート・パーカー  「ゴッドウルフの行方」 「ゴッドウルフの行方」彼については、簡単な感想にとどめたいと思います。 「ゴッドウルフの行方」 “この本はロバート・B・パーカーの処女作である。 彼は1932年に生まれ、ボストン大学を卒業し、 ダシェル・ハメットとレイモンド・チャンドラーを研究して博士号を得た。 1968年以来、ボストンのノースイースタン大学の文学部助教授として、 アメリカ文学と、暴力を扱った小説について講義をし、 アメリカ小説研究会の会員でもある。 その上、毎日ウエイト・リフティングの練習をかかさず、 その方面の著書もあり必ず4キロか5キロは歩き、 熱心なテニス・プレーヤーだ。 「ゴッドウルフの行方」は、1974年1月、 ボストンのモートン・ミフリン社から発刊された。 <ウイークエンダー>という週刊誌の書評によると、 ‘フィリップ・マーローの再来’という見出しで紹介されている。 しかも、彼が今後、推理小説を書き続けていくならば、 ハメット〜チャンドラー〜マクドナルド・スクールの中で、 目ざましい活躍をするだろうと評している。 さらにボストン・サンディ・ヘラルド紙には、 パーカーは人物描写や、気のきいた会話に すぐれた手腕があると述べられている。 訳者も翻訳しながら、スペンサーという詩の好きな私立探偵が、 どこかレイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーローに、 ダシェル・ハメットのサム・スペンサーに、ロス・マクドナルドの リュウ・アーチャーに似ているような気がしないでもなかった。” (訳者:渡辺栄一氏の解説) 1作目のこの本を読んで、 誰でもがそんな期待を、この作家に寄せていたのだと思います。 その後、彼はベストセラー作家として、有名になったようですから、 世の中の彼の作品に対する評価は、好意的なものだったのでしょう。 …私は、新刊を読むたびに嫌いになっていったものです。 なぜか、「約束の地」「ユダの山羊」「銃撃の森」は、 ハード・カバーで読んだので、今は手元にありませんが、 愛人のスーザンと、相棒のホークが登場してからの、これらの作品は、 すっかり、ヴァイオレンス小説に変わってしまって、 期待を裏切られた感じを抱いだものでした。 「ゴッドウルフの行方」でも、すでに、彼の横柄な口調や態度、 また、体力や腕力への自慢と、自ら争いを巻き起こすようなキャラクターが、 気になっていたのですが、それがどんどん過激になっていったようです。 正統派ハードボイルドの私立探偵とはかけ離れようが、 私のようなこだわりがなければ、それはそれで面白いのでしょうが〜。 それでも、後に何作かは文庫本で読んだのですから、 未練がましく、まだどこかに期待する気持ちがあったのかもしれません。  「失投」 「残酷な土地」 「キャッツキルの鷲」 「レイチェル・ウォレスを捜せ」 悪口を書いても仕方ないのですが、 マイケル・リューインが、彼自身の人柄を反映したような、 素直で安定した作風を、どの小説でも一貫して保ち続けているのに対して、 ロバート・パーカーは、偽善的なキャラクターに加えて、作為的な描写が、 鼻につく作家だという感想をもっています。 恋人スーザンへの盲愛については目をつぶるとしても、 自分の暴力を正当化するのための詭弁には、ほとほと嫌気がさします。 「一乗寺下がり松の決闘」で、幼い吉岡の跡取り息子や、沢山の門弟を容赦なく 切り捨てた後、“我、ここにおいて後悔せず!”と、たった一言独白する、 錦ちゃん扮する宮本武蔵のあの態度が、戦う男のあるべき姿です。 その点では、マイク・ハマーのほうがよほど潔いというものです。 ここまで酷評するのも、人気作家に対して失礼な話ですが、 これは、あくまで私個人の評価ということで、勘弁して頂きたいところです。 世の中も、私の生活状況もすっかり変わり、 昔のように、正統派ハードボイルド小説を捜し求める気持ちも、 いつの間にか薄らいでしまったようです。  「ロジャー・サイモン」「マイクル・コリンズ」「スティーヴン・グリーンリーフ」「レス・ロバーツ」「ジェレマイア・ヒーリイ」 新時代の私立探偵には、キャラクターに必然的な性格づけをもたせることがお約束なのか、 離婚歴のある中年男、肉体的にハンディキャップをもつ男、麻薬中毒者、ユダヤ人…多彩です。 これだけ複雑な世の中で、しかもすでに語り尽くされた感のあるこの分野で、 私立探偵が生き長らえるということは、至難の業なのでしょう。 ハードボイルド小説の想い出はこの辺で終りにして、 いずれ、音楽に関係のある話題に戻ろうと考えています。 このページトップへ 次のページへ 目次へ ホームへ |